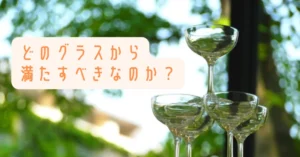※本ページにはアフィリエイト広告が含まれています。
こんにちは。柴山です。
職場や家庭で、いつも自分のことよりも
他人から頼まれたことを優先している
その割にあんまり感謝もされてなさそう…
そんな風に感じることがないでしょうか?
SNSなどでたびたび話題になる「シャンパンタワーの法則」は、自己実現や充実感と深く関わる考え方で、「まず自分の心を満たすことが大切」と説いています。この考え方は、マツダミヒロさんという方が提唱したものです。
今回の記事では「シャンパンタワーの法則」をビジネス・家庭・個人の様々なシーンに当てはめて、そこから充実感、自己肯定感を高める考え方についてまとめてみました。
シャンパンタワーの法則が伝えたいこと
まずはイメージしてみてください。
シャンパンタワーにシャンパンを注ぐとき、まずは最上段のグラスから注いでいきます。そして溢れ出たシャンパンが次々と下の段のグラスを満たしていく、この順番が重要です。

最上段、中心にあるグラスを「自分の心」だと考えます。
シャンパンタワーを人間の心理に当てはめてみると…
最上段、かつ中心部に立つグラスが自分の心、
次の段のグラスは家族、パートナーなど近しい人の心、
3段目は職場の同僚や友人など、家族ほどではないが自分に関わりが深い人たちの心、
さらに下の段のグラスは自分との関りが薄くなる代わりに、より広い範囲の交友関係の人たちの心
…といったイメージです。繰り返しますが、この順番が重要です。
そして、グラスを心に例えたということは
グラスを満たす = 心を満たす
ということになります。
そして、一番初めに最上段のグラスから注いでいくということは、
まずは自分の心から、次に自分に近しい人の心を満たしていくことが大事!
ということの比喩表現となります。
この考え方に対する反論として
それって、ただの利己主義、自分勝手では?
商売だったら、まずはお客様を満足させてあげて、その結果として自分にも利益なり感謝の心が還元されて
…うんぬんかんぬん
という意見もあり得ます。
そこで、「まずは自分の心から」という考え方が、いけないことなのかが、最初のポイントになりそうです。
いつの間にか染みついた「自己犠牲の美学」を見直そう
もしも、あなたが「まず自分を満たす」という考え方に強い抵抗を感じる場合、知らず知らずのうちに「自己犠牲の美学」が心に染みついてしまっている可能性があります。
「自己犠牲の美学」とは、
- 親は子どものためにすべてを犠牲にするべき
- 社員は会社のためにプライベートを犠牲にすべき
- 部下は上司のために常に耐え続けるべき
こういった、
「大切な事の為に自分を犠牲にするのは素晴らしいことだ」
みたいな考え方のことです。
ありがちな例を挙げてみると、

・家族旅行のために取りたかった有給を我慢
・家族の誕生日なのに仕事を優先して残業
…など
このような考え方に、少なからず美徳を感じて育ってきた人も多いはずです。
もちろん、会社のために頑張ること自体は悪いことではありません。しかし、それは自分の心をすり減らしてまで続けるべきものでしょうか?
「まずは自分たちを大事にしよう」と考える、名だたる企業たち
ここで、視点を個人の心の問題から、企業のあり方に移してみます。
例えばここに「お客様第一」を掲げている一方で、過剰な残業が横行、その結果として退職者が続出している企業があるとします。
そういった企業では業務を回すだけでいっぱいで、顧客への細やかな気配りどころではなくなります。競合他社に比べてサービスを充実させることも難しく、「お客様第一」のスローガンも絵に描いた餅になってしまうでしょう。
普通に考えて、
こんな会社、とっとと辞めてやる!
従業員みんながそう考えているとしたら、サービスの質は当然ながら低下します。
残念ながら世の中にはこういった、ブラック的な会社がまだまだありそうですが、一方で競争力を高めるために従業員を大事にしよう、という考え方の会社もあります。
そこで「シャンパンタワーの法則」とリンクしそうな、経営・マネジメントの考え方をいくつか挙げてみると
ES(Employee Satisfaction=従業員満足度)
職場環境や福利厚生などを向上させることで、従業員の方が「ここで働けて良かった」みたいに思える度合い。これが高まることで離職率も下がり、従業員の自発的な努力も期待できるようになります。
エンゲージメント
ビジネスの場面では大体以下2つの意味で使われます。
①消費者がブランドに対して持つ信頼や好感度
②従業員の勤務先企業に対する愛着や思い入れ
企業にとってみれば、①はもちろん重要ですが、②の気持ちが高まれば自然とサービスの向上が期待できます。
インターナルマーケティング
顧客満足度向上のために、まずは従業員満足度やエンゲージメントが高めようという考え方、およびそのための施策。それにより自然と顧客へのサービスも向上するはず、という考えに基づきます。
これらは、「まずは自分たちから」の考え方といっても良さそうです。
ちなみに、「インターナルマーケティング 実施企業」で検索すると、トヨタ、資生堂、スターバックス、USJなどそうそうたる企業の名前が挙がってきます。厳しい競争を勝ち抜いてきた一流企業ほど、社員を大切にする重要性を理解しているのと言えそうです。
インターナルマーケティングについて興味が湧いた方は以下の記事もご覧ください。
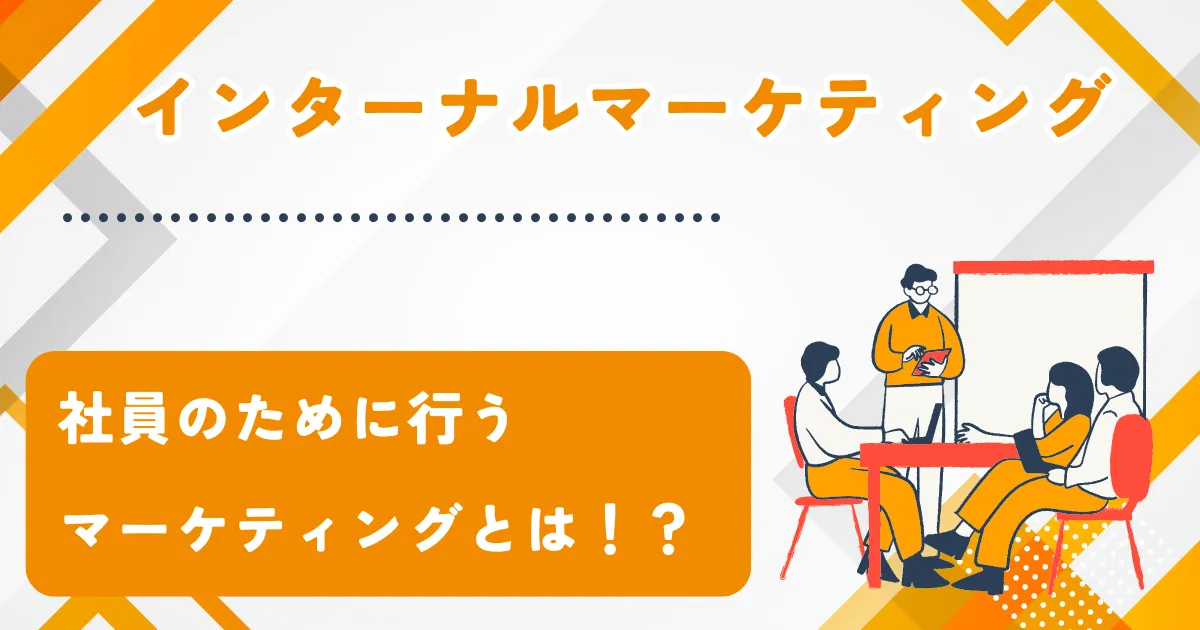
気持ちに余裕が無いと、他人への配慮は難しい
ここで再び、個人の心に話の焦点を戻します。
個人の場合でも、例えばストレスや疲労で一杯一杯になっている状態で、あなた本来の姿で他人と接することは難しいはずです。表面的には元気そうに見えても内側では余裕がなく、ちょっとしたことでイライラするなど、周囲の人からも話しかけづらくなってしまいます。
こうして貯めこんだ感情は、色んな形で現れます。
- 子どもが言うことを聞かないと怒鳴ってしまう
- 職場で部下や後輩に対して怒りをぶつける
- 医療施設や介護施設にてケアに配慮が無くなる
これらの背景には、自分を労わる時間や、自分を満たす行為が極端に少ないのが原因です。つまり、自分の心に余裕が無いのに、他人に気を配ろうとして空回りしているのです。
特に医療や介護、教育、営業といった対人の仕事は、自分の感情を常にコントロールする必要があり、感情労働と呼ばれることもあります。
こういった職業の方が、自分の気持ち、感情に余裕が無い状態が続くと、燃え尽き症候群(バーンアウト)へとつながってしまう危険性すらあります。
 | 感情労働マネジメント 対人サービスで働く人々の組織的支援 [ 田村尚子 ] 価格:2200円 |
 | ひと相手の仕事はなぜ疲れるのか 感情労働の時代 [ 武井麻子 ] 価格:1650円 |
医療現場での事例
人手不足への危機感から、スタッフの離職を防ぐために福利厚生の充実をうたっている医療機関が多くなりました。気持ちの余裕とともに、「ここで働けて良かった!」という気持ちが高まればサービスの向上も期待できます。
事例①:
短時間正社員制度や、子育て中のスタッフ向けのフレキシブルタイム制度を導入。急な子どもの発熱などにも対応できるよう、スタッフ間の協力体制を強化し、相互にサポートし合える環境を整備。
事例②:
職員向けの社食の充実、提携している保育園の優先利用、スポーツジムの割引制度など、多様な福利厚生を提供。
自分の心を満たすのは、簡単なようで難しい
とはいえ「自分を満たす」と言われても、何をどうすればいいのか分からない、ということは充分あり得ます。
多くの人は小さい頃から
「人に優しく」
「わがままを言わないように」
と教わってきてします。
その結果、真面目な方ほど「自分を大切にするってなんだっけ?」となりがちです。
自分の心をを満たすためには、自分が何が欲しいか、何が一番やりたいのか分かっている必要があります。しかも、努力したからといって必ずそれが手に入る訳では無いのは世の常です。
そこで、まずはささやかなところからスタートするとして、
- 些細な事でも良いので、とにかく自分を褒めるようにする
⇒「今朝は時間通りに起きれた、自分エライ!」など - 時と場合によっては「NO!」と言ってみる
⇒仕事の無茶振りに対して、無理なものは無理と意志を伝える - 少しでも良いので自分だけの時間を作り、自分の欲求を満たす
⇒家族に内緒で自分だけ美味しいスィーツを食べるなど - 自分の感情をに気づき、受け止める
⇒誰かに嫌なことをされた後、それを思いだす度に怒りが湧いてくる、ということがあります。自分で自分の感情に火をつけるのはやめて「自分は今、怒っているんだな」と一歩引いて自分を眺めるようにすることで、嫌な感情をスルーする練習になります。
とにかく日頃から「いい人」であるために消耗してきたエネルギーを、少しずつでも良いので自分の為に使うことを意識します。
「自分充実」のための心理学あれこれ
せっかくなので「自分を満たす」ことに関係が深い、心理学の考え方を取り上げてみました。
マズローの欲求段階説
「マズローの欲求段階説」は様々なところで紹介されているので、ご存じの方も多いと思います。
人間の欲求は以下のようにピラミッド状に積み重なっていると考えます。
①「自己実現欲求」(自分らしく輝きたい)⇦最上位
②「承認欲求」(認められたい)
③「所属と愛の欲求」(誰かと繋がりたい)
④「安全欲求」(安心して暮らしたい)
⑤「生理的欲求」(食べたい、寝たい)⇦最下位
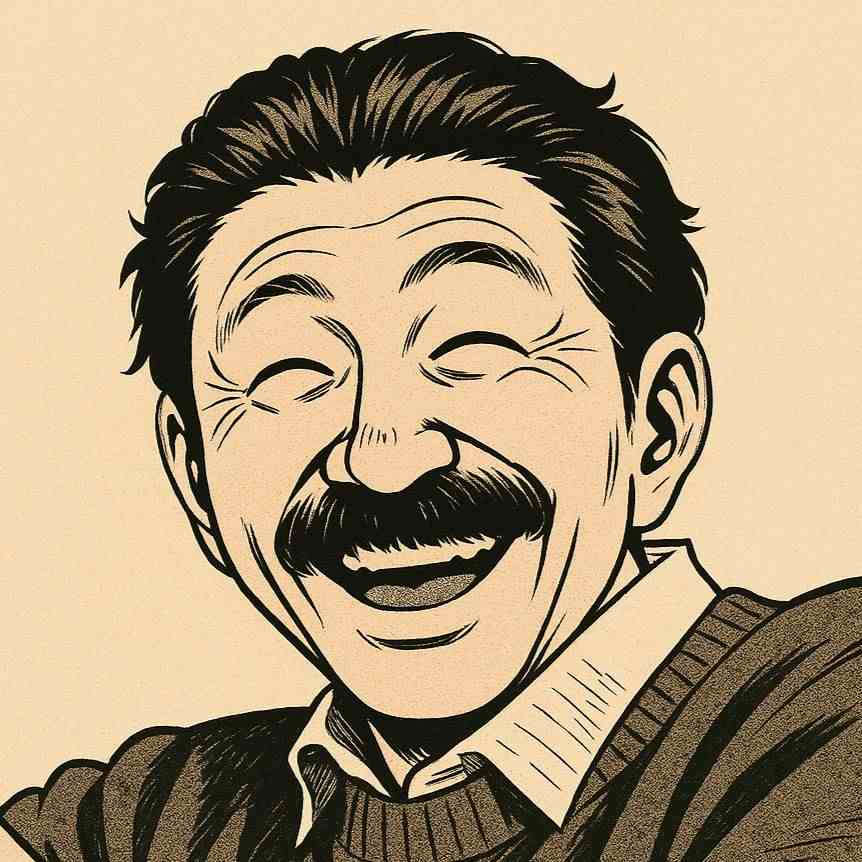
AIで作った、マズローさんの似顔絵
この考え方もシャンパンタワーに似た階層構造ですが、異なるのは「下から上」の順番となっている点です。
心の充足の為には、まず一番下の欲求である⑤「生理的欲求」が満たされる必要があり、続いて④③②の欲求が満たされ、最後にやっと①「自己実現欲求」を満たすことができる、という考え方です。
人間も生物である以上、まず生きるための欲求を満たしたり安全に生きられる状況を確保したい、というのは当然です。ただ、「自分らしく生きたい」という欲望の前に、「承認されたい」(他人から認められたい)という欲望が来ているのは意外な気がします。
あくまで1つの考え方ですので、無理に賛同する必要はありません。
 | お客様のことが見えなくなったら読む本 売れる人の超訳マズロー欲求5段階説 [ 松野恵介 ] 価格:1540円 |
アドラー心理学と「自己受容」・「嫌われる勇気」
アドラー心理学も超有名です。「嫌われる勇気」との関連で話題になったりしました。

AIで作った、アドラーさんの似顔絵
 | 嫌われる勇気 自己啓発の源流「アドラー」の教え [ 岸見一郎 ] 価格:1650円 |
アドラー心理学の本質は「他者の期待に生きるのではなく、自分の人生を選び取る勇気を持つ」とのことだそうです。
たとえ欠点や弱さがあっても、それを認めたうえで
それでも自分には価値がある
と、ポジティブに自分を信じる心(自己受容・自己肯定感)を大切にします。
さらに、
他人に好かれることを目的とするのではなく、自分の軸で判断・行動し、時に嫌われることを恐れないことで自己充実を目指す
という生き方を良しとします。
これを人生の全ての場面で貫くのは相当な困難です。
ですが、手始めに自分や家族の誕生日に有給を取るぐらいならなんとかなるはずです。
ハーズバーグの「衛生要因」・「動機付け要因」
マズローの「欲求段階説」から派生したものに、ハーズバーグの「衛生要因」・「動機付け要因」があります。
これは経営者にとっては結構重要な、知っておくべき考え方だと思います。

ハーズバーグさん(あんまり似てません)
たとえば
給料をUPしたのに、なぜ社員のやる気が出ないのか?
といった、従業員のモチベーションに関連して語られることが多い理論です。
衛生要因とは「不満を防ぐ土台」
まず、「衛生要因」とは、職場環境や待遇など、整っていないと不満につながるもののことを指します。
たとえば:
・給与
・勤務条件(労働時間、職場の快適さ)
・上司との人間関係
などです。
これらは最低限整っていないと従業員は不満を抱きます。しかし、どれだけ改善しても「やる気(モチベーション)」には直結しないとハーズバーグは説きます。
意外に感じるかもしれませんが、この理論では給与の高さは「辞めない理由」にはなってもモチベーションUPにはつながらないと考えます。
これは給与をアップしても、時間が経つにつれてそれが当たり前に感じる様になってしまうからです。
動機付け要因とは「やる気を生む火種」
一方で、「動機付け要因」とは、仕事そのものに内在する「やりがい」や「達成感」など、ポジティブな満足感をもたらす要素です。
具体的には:
・達成感
・他者からの承認(認められること)
・仕事自体の面白さ・やりがい
・責任の重さ(任されること)
・成長や昇進の機会
などです。
これらが、人の内側から湧き上がるモチベーションの源泉となります。
ポイント:報酬だけでは人は満たされない
この理論で興味深いのは、報酬(給料、お小遣い、プレゼントなど)があったとしても、心理的な充足(感謝の言葉、達成感、他人から認められること、など)なければ、モチベーション向上にはつながらないという点です。
例えば、資料を上司に提出したらそれっきり、となるよりも、上司からなんらかのフィードバック(感謝の言葉や評価等)が有った方がモチベーションにつながるのは容易に想像がつくと思います。
職場に限らず、お互いに感謝を伝えたりなど日頃のコミュニケーションがとても重要なことを改めて考えさせられます。
まとめ:シャンパン本来の使い道
真面目な人ほど、自分を優先することに、どこか罪悪感を覚えてしまうことがあるかもしれません。
ですが、ここまで見てきた通り、自分を削ってまで他人に奉仕するのは、本当の意味での心の充足にはつながりません。
いきなり完璧な「なりたい自分」になることは難しくても、まずは自分のために一息つける時間を作ったり、美味しいものをこっそり食べるなど、少しだけワガママになることを自分に許すことから始めましょう。
もちろん、あなたがお酒が好きなら、休日に自分だけで美味しいシャンパンを飲んで気分を晴らすという方法もアリです。(それが本来のシャンパンの使い道です)
それでは今回はここまで。