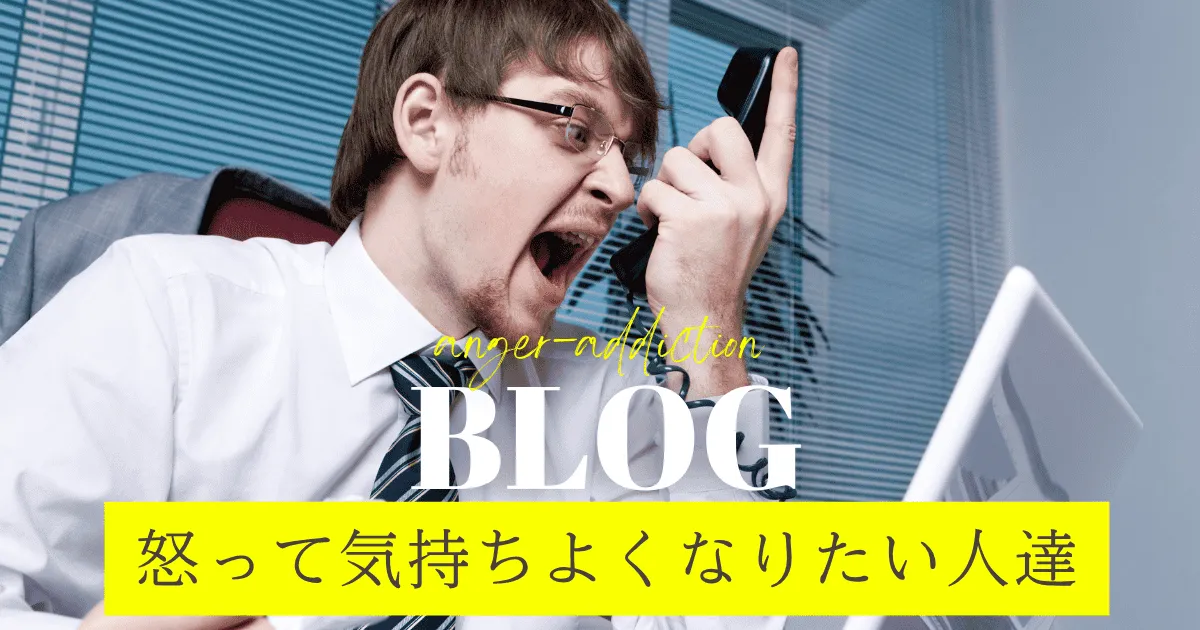※本ページにはアフィリエイト広告が含まれています。
こんにちは、柴山です。
唐突ですが、人間の三大欲求といえば
- 食欲
- 性欲
- 睡眠欲
…ですが、もしここにもう1つ加えて「四大欲求」とするのであれば、4つ目は「支配欲」がくるのではないかと、勝手に思っています。
支配欲と言っても、

愚かな人類よ、
我々ショ〇カーが支配してやる…!!
こういうスケールの大きなものばかりではなく、もっと身近な場面であちこち見られます。
今回は職場であなたの「上司力」を低下させる
- 「部下を思いのままに動かしたい」
- 「部下の仕事の細部まで自分のコントロール下に置きたい」
といった欲望、および、そこから生まれるマイクロマネジメントについてまとめてみました。
支配欲とマイクロマネジメントの関係
「支配欲が強い」というと、何だか悪者のような響きがあります。が、この欲望はヒトが群れの中で生き残っていく上では非常に重要です。
群れの中でボス的な地位にある個体は、食料、水、安全な場所といった生存に不可欠な資源を優先的に確保できる可能性が高くなります。当然、子孫を残す上でも有利です。
そう考えると、
- 生き残るために群れの中で強い立場を手に入れてやるぞ!
- 他の個体に命令できるようになってやるぞ!
…というのが、支配欲の起源のようです。
また、支配欲は集団の中で優越感を感じたいという感情とも密接なつながりがあると思われます。
支配欲は職場でどのような形で現れる?
とはいえ、いくら支配欲が人間の本能だとしても、その赴くままに職場で振舞われては、部下はたまったものではありません。
支配欲が強い上司は、何事も自分の思ったように進めないと気が済まないので
- マイクロマネジメント
- 会議・ミーティングでは、多様な意見が出ることより自分の考えに沿って進めることを優先
- プライベートの用事にも部下をこき使う
- 部下を人間扱いしないようなパワハラ
- 手柄を横取りしたり、責任を押し付けるなど踏み台にする
- とにかく色々と仕切りたい(鍋奉行的な)
などの行動に走りがちです。
③④⑤は論外として、ここでは通常業務の範囲内で行われれる①について考えてみたいと思います。また②については、いずれ別の記事でまとめたいと思っています。
マイクロマネジメント=支配欲がもたらす過干渉
マイクロマネジメントとは、上司が部下の業務に対して過度に干渉し、細部にわたって指示を出す管理手法のことです。部下の自主性や創造性を奪い、モチベーションを低下させる可能性があるため、一般的にはネガティブなイメージを持たれています。
マイクロマネジメント上司(A)と事務スタッフ(B)の会話:
A:「Bさん、例の企画書、進捗どう?見せてくれる?」
B:「はい、ざっと構成を考えてみたんですが…」
A:「ふむ。ちょっと待って。このタイトル、文字サイズが18pt?俺はいつも20ptにしてるんだけど。あと、このグラフの色、もっと明るい方がいいんじゃないか?あと、ここにこの文言はいらないな。削除して。」
B:「あ、はい。まだ仮なので、調整しようと思ってました。」
A:「いや、仮でも最初から完璧を目指さないと。あと、この箇条書きのインデント、揃ってないぞ。俺がいつも使ってるテンプレート使うのが一番早いんじゃないか?」
B:「…はい、そうします(ウザいなぁ)。そうして欲しいなら最初から言ってくれればいいのに」
マイクロマネジメント上司(C)と営業部員(D)の会話:
C:「Dさん、今日の商談、俺も同行するぞ。」
D:「ありがとうございます。助かります。」
C:「先方の部長には、まずゴルフのネタから入るんだ。頃合いを見て新製品の説明を始めて、次に直近の導入事例を出す。そして部長の反応を見てから価格交渉に入るんだぞ。部長がまだ食いついてないのに価格の話を始めるのは絶対ダメだ。質問が来ても、これ以外のことは話すな。いいな?」
D:「はい、承知しています。」
C:「本当に分かってるのか?資料を見せる順番は、最初にこれ、次にこれだ。こっちの資料を先に見せてしまうと分かりづらいからな。」
D:「…はい。分かりました(今日も安定してウザいなぁ)。先方は既に乗り気だから余計な前置きは不要なのに」
上記はあくまで例です。また、入社したての新人に対しては、細かい指示が必要な場合も、もちろんあります。
マイクロマネジメントを行う上司の心理
次にマイクロマネジメントを行う上司の心理を分析してみました。
①仕事をミスなく終わらせようという責任感はある
マイクロマネジメントをする上司の多くは、業務の品質や目標達成への強い責任感を持っています。ミスが発生すること、あるいは非効率な進め方をされることへの不安や嫌悪感が強いため、ついつい細部にまで介入してしまいます。
②部下を育てたり、モチベーションを高めるのも上司の仕事だという観点がない
上司自身が「自分が仕切った方が早いし、確実」と考えているため、部下に試行錯誤させたり権限を委譲して成長を促したりする視点が希薄です。その結果、部下のモチベーション向上や育成が意識から外れてしまっています。
③多くの場合、部下に対する悪意は無い
マイクロマネジメントを行う上司の多くは、部下に対して個人的な悪意や嫌がらせの意図を持っているわけではありません。むしろ、前述の通り「業務を確実に成功させたい」「部下に失敗してほしくない」という善意(という名の不安や完璧主義)から来ていることがほとんどです。
④自分の支配欲や優越感に無自覚で、部下を過度にコントロールしたがる
上司は業務の確実な遂行を目的としている一方で、その根底には「全てを自分の管理下に置きたい」「自分のやり方が正しい」という無自覚な支配欲が存在します。この欲求が満たされることで得られる優越感や安心感が、マイクロマネジメントの動機になっています。
普通に考えて、

「さあ、今日も一日、マイクロマネジメントを頑張って、優越感を満喫するぞ!
という人は多分いないはずです。
上司本人は、あくまで適切な管理だと考えてやっていますが
- 無自覚な支配欲が過度なコントロールにつながっている
- 目の前の仕事の達成を優先した結果、部下の育成を後回しにしている
という点が問題です。
なお、部下への支配欲があまりに過剰で、かつ部下を踏み台にする傾向がある人は「クラッシャー上司」と呼ばれる場合があります。(以下は姉妹サイトの記事です)
リーダーシップ論:部下を育てる上司の在り方
中小企業診断士試験にはリーダーシップ論も含まれているので、私も学びました。
結論から言うと「絶対に間違いのない唯一無二のリーダー像」というものはありません。上司の在り方や役割は状況により変わる、というのが現代のリーダーシップ論やマネジメントの考え方です。
マイクロマネジメントが日常化してしまっている方が、自らマネジメントスタイルを見直すうえで、以下の内容がヒントになれば幸いです。
部下が成長しないと上司も(本来は)困るはず
先にも少し触れましたが、入社したばかりで右も左も分からない新人に自主性を期待するのは無謀です。
とはいえ、
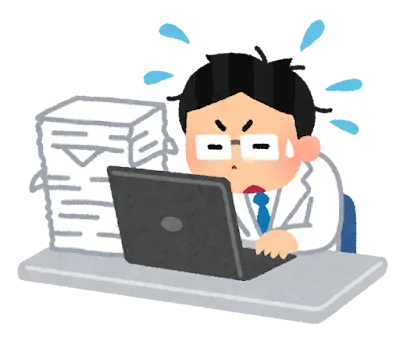
部下に任せるよりも
残業してでも自分がやった方が早い!
いつまでもこんなことをやっていたら部下が成長しないだけでなく、上司自身も今やっている仕事をこの先ずっとやる羽目になります。
「チームの目標達成のためには、もっと考える時間を確保したい」
…などのように考えているなら、自分の仕事を手放して、少しずつでも部下に渡していくことが必要です。
なお、たくさんの仕事を抱えていることを自分の存在理由のように考え、部下や同僚に仕事を渡したがらない人もたまにいますが、今回の記事ではいったん置いておきます。
SL理論:部下の成熟度により、上司の役割は変わる
部下の成熟度に合わせて上司の役割をどう変えていけばよいか、簡単な例を挙げつつ「SL理論」に基づいて整理してみます。

成熟度1:やって欲しいことを明確に指示
例:明日○○行きの新幹線のチケットを手配して
業務未経験、また経験が浅い人への指示は、曖昧な点の無い具体的な指示が必要です。
成熟度2:やって欲しいことの指示+目的を伝達
例:新規開拓のために○○社を訪問するから、明日○○行きの新幹線のチケットを手配して
目的を伝えることで、部下が自分なりに考える余地が生まれます。
⇒部下のリアクション:それならサンプル品も準備した方が良いのでは
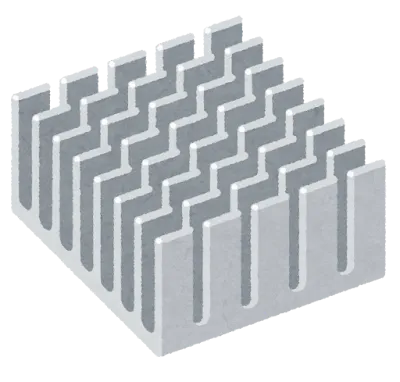

成熟度3:意志決定に部下も参加させる
例:○○社に営業をかけるべきだろうか?
部下に経験を積ませてから、その意見も取り入れるようにしていきます。
⇒部下のリアクション:営業をかけるべきだが、訪問は新製品発表のタイミングにした方が良いのでは
成熟度4:意志決定も部下に任せる
例:○○社への対応は君に任せた
上司の責任の下で、部下に裁量を与えます。
⇒部下のリアクション:分かりました!何かあったら報告します!

SL理論について、もう少し正式(?)にまとめると以下のようになります。
SL理論まとめ(⇒クリックすると開きます)
| 成熟度1:教示型(Telling) 対象:業務未経験の部下 上司の役割:何を、いつまでに、どうやるか具体的に指示 (指示的行動) |
| 成熟度2:説得型(Selling) 対象:業務をある程度覚えた部下 上司の役割:指示するだけでなく目的を説明して本人なりの工夫を促す (指示的行動+援助的行動) |
| 成熟度3:参加型(Participating)) 対象:業務に習熟し、責任感を持たせたい部下 上司の役割:部下と共同で方向性を決めた後、実務は部下に任せて自分はサポート役に回る (主に援助的行動) |
| 成熟度4:委任型(Delegating) 対象:業務を任せられる部下 上司に必要な行動:方向性の決定・実務とも部下に任せる (部下を見守り、最終的な責任を負う) |
なお「SL理論」という名称のせいで難しげに聞こえますが、
指示の仕方・任せ方は、段階を踏んで変えていこうぜ!
という、ごく普通(かつまとも)な考え方です。
ポイントとしては、
- 何をして欲しいのか、指示は具体的に
- 部下に考えさせたいなら、目的や背景の説明が必要
- 段階を経て裁量を与えていく
この辺りが重要です。
ちなみに目的や背景の説明なしに「察しろ」という上司は、「察してちゃん上司」と呼ばれることになります。

まとめ:経営者の視点で考えてみると…
前半で書いた通り、支配欲は人間の本能の一部なので、自覚したところで消え去ったりはしません。
しかし、この記事をここまで読んで頂いた方は「上司力」の低い、支配欲ダダ洩れ上司にはならないのではないかと思います。
それでも
「ミスが怖いので、部下に対して細かく指示しないと気が済まない」
という方は一度、経営者になったつもりで考えてみてください。
社長の立場で考えてみると、
「マイクロマネジメントに割くエネルギーがあったら、会社の将来のために部下の育成に時間をかけてくれ」
と思うはずです。というか、そもそもそのために管理職としての給料を払っている訳ですし。
最後に「経営者目線」についての用語を2つ紹介しておきます。
ということで、今回はここまで。
関連記事はこちら