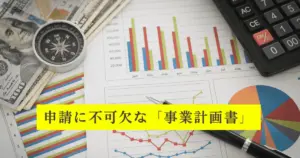※本ページにはアフィリエイト広告が含まれています。
こんにちは、柴山です。
補助金の申請において不可欠であり、いわば申請の「主役」といっても過言ではないのが事業計画書です。
事業計画書についてありがちな疑問としては
「設備を買いたいだけなのに、事業計画が必要?」
「ウチの強みとか、なんで書かないといけないの?」
といったものです。
今回の記事では、補助金申請における事業計画書の意味と役割、そして実際にどんなことを書くのかを解説します。
なぜ補助金に「事業計画」が必要なのか?
第1回目の記事で書いたように、補助金には様々な種類があるものの、共通した主旨は「未来への投資に対する支援」です。
補助金の審査では次のような点が評価されます:
- なぜその投資が必要なのか
- 投資によってどんな成果が見込まれるのか
- 事業として現実的か、自社の強みを活かせるか
こうした説明をする役割を担うのが、その補助金によってどのようなことを行うのかを説明する資料、つまり事業計画書です。
ありがちな誤解:「壊れた設備の買い替え」は新事業ではない?
補助金申請において「事業」(または補助事業、新事業)とは「補助金によって行おうとしていること」のことだと思っておいてください。
事業計画書の前に、補助金の対象となる(=補助金を受けられる)事業とはどういうものかの説明をします。
とある居酒屋の例
たとえば今、居酒屋A店とB店が、それぞれ小規模事業者持続化補助金により設備の購入を検討しているとします。
次のような場合、どちらの補助金申請が採択(採用)されやすいでしょうか?
A店:老朽化した調理器具の買い替え
→A店では、「どうせ買い替えるなら補助金を使った方がお得」と考えています。
B店:新メニュー「低温調理コース」のために調理器具を刷新
→B店では補助金を使った新メニュー開発と同時に「女子会コース」を設け、さらに広告をうつことで地域の新たな需要を掘り起こそうとしています。

新メニュー+広告実施で大繁盛しているお店
「現状維持のための支出」では採択されにくい
第1回目の記事から読んだ方はもうお分かりかと思いますが、採択されやすいのは圧倒的に②です。(そもそも①は補助金の対象になりません)
①はA店の現状維持でしかないのに対し、②では売上向上が期待できます。さらに上手くいけば従業員の賃上げや2号店の出店など、小規模とはいえ地域の経済や雇用にも好影響を期待できるでしょう。
事業計画書には何を書かなければならない?
ごく簡単に言えば、事業計画についてまとめたものが事業計画書です。
ただ「こういう新製品・サービスを始めたいから、こういう設備を買いたい」と書いただけでは補助金の採択を受けることはできません。
まずは以下のリンクから実際の事業計画書のサンプルをご覧ください。いきなり熟読する必要は無く、大体どんな感じのものなのか目を通す程度でOKです。
公式サイトで見る事業計画書のサンプル
中小企業基盤整備機構(J‑Net21)「事業計画書の作成例」
⇒こちら
飲食業、小売業、サービス業のサンプルが確認できます。
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金 参考様式「事業計画書 記載項目」
⇒こちら
事業計画書のテンプレートがダウンロードできます。
事業計画書に記載する項目とは
上のサンプルでもおおよそ確認できますが、事業計画書に求められる主な項目は以下のようになります。なお、補助金の種類によって違いがあるため、実際の申請の際には確認が必要です。
- 自社の現状分析(会社の沿革や概要、SWOT分析、経営課題など)
- 市場・競合分析(需要予測、ターゲット層の明確化)
- 今後の事業戦略(製品・サービス、販売計画)
- 収支計画・投資効果の見通し
- 人材・組織体制
- 補助事業の具体的内容・スケジュール
これについて
補助金が欲しいだけなのに、ウチの会社や業界のことをイチから説明しなきゃいけないの?
という疑問もあるかもしれません。
ですが、補助金を審査する側からすると、申請のあった事業が有望であるかどうか(=限られた予算から優先的にお金を出すべき事業かどうか)はこういった情報がないと判定できません。
これから始めようとしている事業が…
- 地域性や市場特性:地元ではライバル不在であり、市場を独占できる
- 自社の強み:自らの独自技術を存分に活かすことができ、ライバル他社と差別化できる
- 自社の弱み:自らのの弱み(例:取引先が1社に偏っている)の克服につながり、経営の安定につながる
など、しっかり説明してあれば審査がしやすくなるのは明白です。
B店の事業計画書(ダイジェスト版)作ってみた
ということで、先のB店が小規模事業者持続化補助金を使う前提でダイジェスト版の事業計画書を作ってみました。
さっと目を通しやすいように箇条書きで短く記述していますが、盛り込むべき項目はイメージできるかと思います。
B店の事業計画書(クリックにより開きます⇒)
事業名:低温調理器具導入による新メニュー開発
■ 1. 事業者の概要
- 屋号:居酒屋B店
- 所在地:〇〇県△△市(駅から徒歩20分)
- 設立:2014年(創業10年)
- 従業員:店主+アルバイト2名
- 主な業態:地元密着型の居酒屋、特に豚肉料理に定評あり
■ 2. 自社の強みと課題※1
【強み】
- 独自ルートによる「安くて質の良い国産豚肉の仕入れ」
- 仕込みに手間をかけた肉料理が高評価で、駅から離れているにも関わらずリピーターが多い
- SNSのフォロワーが徐々に増加中(Instagramなど)
【課題】
- 駅前再開発に伴いチェーン系飲食店の進出が顕著
- 顧客の流れが駅周辺に集中し、来店数・売上が減少傾向
- 女性客や若年層への訴求が弱く、新規顧客が増えていない
■ 3. 今後の取り組み(補助事業の内容)
【新メニュー導入】
- 低温調理専用機器を導入し、豚肉を活かした「低温調理メニュー」を開発
- 安心・安全を前提とした温度管理を徹底(食中毒リスクを抑制)
- 試作段階で顧客アンケートも実施中
【新規顧客の開拓】
- 女性グループ向けの「女子会コース」を新設
- チラシ・SNS・Web広告を活用し、集客キャンペーンを実施
■ 4. 市場動向と競合分析
- 【市場】:健康志向や「映える食事」ニーズの高まりにより、低温調理は近年注目されている
- 【競合】:周辺地域では低温調理を専門的に提供する飲食店はなく、差別化が可能
- 【顧客層】:30代~40代の女性グループやカップルが新たなターゲット層
■ 5. 投資計画と資金使途(補助金の使途)
| 項目 | 金額(概算) | 補足 |
|---|---|---|
| 低温調理器具(業務用) | 250,000円 | 正確な温度管理機能付き |
| メニュー開発・試作材料費 | 80,000円 | 試食用サンプル等 |
| 広告費(Web・SNS等) | 120,000円 | 期間限定キャンペーンなど |
※自己資金との併用で実施予定
以下を画像で挿入し、説明を加える
- 導入予定の調理器具
- 新しい調理器具を導入することで、調理過程がどのように変わるか
- 試作料理のイメージ、試食した顧客によるアンケート集計
■ 6. 今後の見通しと成果目標※2
- 低温調理メニューの導入により、月間売上20%アップを目指す
- 新規来店客数を前年比+30%へ
- SNSフォロワー数1,000名突破を目標(話題性向上)
- 売上アップを見込んで、アルバイトの時給○○円を賃上げ予定
■ 7. 実施体制とスケジュール(概要)
- 【担当】:メニュー開発・運用=店主、広告=知人のデザイナー協力あり
- 【期間】:補助事業開始=2026年4月、導入・PR開始=2026年6月予定
※上記はあくまで構成イメージです。
実際の補助金申請では、ここに「収支計画書」「リスク管理体制」「導入前後の比較資料」なども求められます。また審査員の方にとって分かり易いように画像やグラフの挿入が推奨されます。
内容や様式は補助金の種類によって異なります。
事業計画書を社内で作るためのハードルは?
ところで先のサンプルを見て頂いた方は
「これは作るのは結構大変そうだな」
と思ったのではないでしょうか?
大企業または中堅以上の企業であれば、株主や銀行への説明のために何らかの形で事業計画書を定期的に作成しているはずです。ですが多くの中小企業では事業計画書を作成することがあまりなく、経験やスキルが不足しているのが現実です。
そのため
- 市場分析の方法が分からない
- 収支計画をどう書けば良いか分からない
- 事業計画書以外に必要な書類が分からない
という事態になってしまいがちです。
おそらく社内のスタッフでも事業計画書作成に専念できれば、不可能ではないでしょう。ただし、その場合は通常業務がおざなりになってしまうというデメリットがあります。
こうした悩みを解決するには、専門家の伴走支援が非常に有効です。

事業計画書を作成しようとして疲れ切った社内スタッフ
「CAGR」ってなに?専門用語もあちこちに登場
事業計画書の中には、意味を知っていないと対応出来ない、「CAGR(年平均成長率)」や「付加価値」などの専門用語が登場することもあります。
CAGRとは?
複数年にわたる売上などの成長率を平均的に表した指標で、たとえば:
- 2023年:売上5,000万円
- 2026年:売上7,000万円
この場合、CAGRは約11.2%(毎年平均11.2%で成長しているという意味)になります。
採択審査では「この事業に投資すれば、売上や利益がどれくらい伸びるのか」が問われるため、こうした数値目標を正しく設定した事業計画書を作る必要があります。
付加価値とは?
「付加価値」という言葉は様々な場面で使われますが、補助金の事業計画書で使われる場合は
付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費
という意味で使うと決まっています。
事業計画書の差癖にあたって、売上だけでなく付加価値がどのように成長するかも書かなくてはならないので、意味を知らないと作成がそこで停まってしまいます。
こういった計算が必要な訳は?
これらの指標は「補助金によりこの事業を実施することでどれくらいの効果があるか」を明らかにするためのものです。
税金を投入するという補助金の性格上、売上や付加価値の成長率が高い(=地域経済への貢献度が高い)事業が優先的に採択されやすくなります。
結論:社内での事業計画書作成はかなり大変
現代では分からない用語が有ってもインターネットで調べることは可能です。とはいえ、分からないことだらけの状態から一つずつ調べていくのは相当大変であることは想像がつくと思います。
ということで、人手が限られている中小企業や個人事業主の方が自力で事業計画書を書き上げたり、必要書類を全て揃えるのはかなり大変と言わざるを得ません。
そこで外部の専門家の手を借りるのが有効な手段となります。
次回の記事は 申請に必要な他の書類とは? について解説予定です。