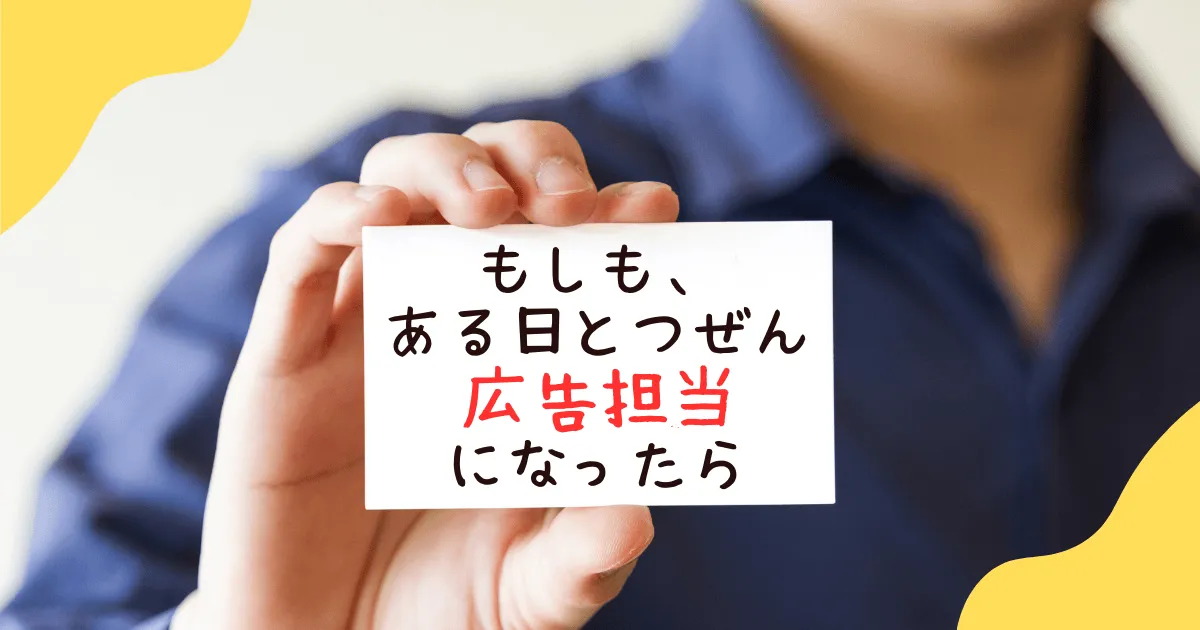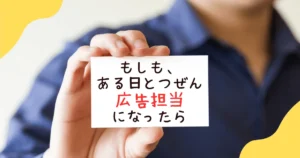※本ページにはアフィリエイト広告が含まれています。
こんにちは、柴山です。
今回の記事は大企業勤務の方にはほとんど(というか全く)関係無い話です。
私が見てきた範囲では、中小企業では専任の広告担当者がいないことが多く、従業員50名以上、場合によっては100名以上の企業でも営業や事務の担当者が「ついでに」と任されることがありました。
ですので仮に、今この記事を読んでいる方が中小企業に勤めているとすると
〇〇さん、来月から広告もやってね。
突然そんな指名をされる。これは普通に起こりうる事態、ある種の悲劇です。

前からの担当業務も変わらずやらないといけない…、どうしろと。
広告は企業の売上やブランドイメージに直結する重要な仕事なので、
やってやるから、せめて専任にしてくれ
と言いたいところですが、ここはいったんこらえるしかありません。
不本意でもとりあえず、やるべきことをやらないといけないでしょう。
(もちろん文句を言うことが許される、自由な社風であれば別ですが)
ということで今回は、そういった悲劇が明日あなたの身に起こっても大丈夫なように広告業務の基本知識について解説してみました。
なお、ここでは
細かい作業は広告代理店にやらせよう!
という精神に基づき、細部の説明を意図的に省略している部分もあります。あらかじめご了承ください。
1.なぜ、中小企業に広告担当が必要なのか?
近年、スマートフォンの普及やインターネットの進化により、人々の情報収集の方法は大きく変化しました。従来の紙媒体の広告だけでは、ターゲットとする顧客に情報を届けにくくなっているのが現状です。
うちの会社は昔ながらのやり方でやってきたから大丈夫
実際、業種(業界)によっては紙媒体の広告が最近でも有効だったこともあるからです。ですが、上のように考えていた経営者でも「さすがにこれはマズイ」と思われているのではないでしょうか?
競合他社が新しい広告戦略を取り入れ、成果を上げている中で、自社だけが変わらないというのは、ビジネスチャンスを逃していると言わざるを得ません。
中小企業こそ、限られた予算の中で効果を最大化するために、戦略的な広告活動が求められています。そして、その中心となるのが「広告担当」です。
本来なら当然、広告の専任担当者を置くべきです。ただ人的余裕が無い中小企業だと、やむを得ず誰かが兼任する形をとることになります。
2.最初にやるべきこと
ということで、兼任であろうとなかろうと、担当になったあなたが最初にやるべきことは以下の通りです。
- 自社の強みと弱みを理解する
まずは、自社の製品やサービスがどのような顧客に支持されているのか、競合他社と比較してどのような強みがあるのかを明確にしましょう。逆に、顧客からの不満点や、改善すべき点なども把握しておく必要があります。
強み等を分析する方法には、SWOT分析・3C分析・4P分析などがあります。
- ターゲット顧客を明確にする
どんな人に広告を見てもらいたいのか、具体的なターゲット顧客像(年齢、性別、職業、興味関心など)を明確にすることが重要です。ターゲットが曖昧なままでは、効果的な広告戦略を立てることはできません。
- 競合他社の広告戦略を分析する
競合他社がどのような広告を出しているのか、どのようなターゲットにアプローチしているのかを調査しましょう。競合の成功事例や失敗事例から学ぶことは多くあります。
ポイント:
競合他社のウェブサイトやSNSアカウント、出稿している広告などをチェックしてみましょう。どんなメッセージを発信しているのか、どんなデザインを使っているのかなどを分析することで、自社の広告戦略のヒントが見つかるはずです。
3. 広告媒体の基礎知識
次に広告が掲載される「媒体」について説明します。
- 紙媒体広告:新聞、雑誌、チラシなどの印刷物に掲載される広告
- 屋外広告:電車内、バス停、看板などに表示される広告
- テレビ・ラジオ広告:特定の時間枠で放映される広告
そして今や広告の主流となったデジタル広告があります。この記事の内容は主にデジタル広告に焦点を当てたものになっています。
デジタル広告とホームページの関係
ホームページを作ったのに、全然問い合わせが来ない…
という声をよく耳にします。
その原因の多くは「ただホームページを作っただけ」となっていて、顧客がホームページに辿り着くまでの誘導が何も行われていないことです。
例えば自動車メーカーのように、そもそも全国的な知名度があり、何もしなくても顧客が会社名や製品名で検索してくれれば良いのですが、多くの中小企業はそういった立場にありません。
なので、そういった場合は以下のような「広告による誘導」を行うことになります。
- リスティング広告:検索結果に連動して表示され、今すぐに商品やサービスを探している人に効果的
- ディスプレイ広告:バナー画像として表示され、認知度向上に効果的
- SNS広告:Facebook、Instagram、X(旧Twitter)などを利用し、興味・関心を持つユーザーにアプローチ
- 動画広告:YouTube動画や各種動画配信サイトで表示される広告です。
これら広告は「どのあたりに住んでいる人」・「過去にどのような検索をした人」、など届けたい相手の属性をある程度は指定することができます。
例えば車検や住宅リフォームなどを検索した後には、やたらとその関連の広告バナーが画面にあらわれるようになった、などの経験がある方も多いはずです。
4. 広告用語の基礎知識
今度は広告用語の基礎知識です。
現在、主流となっているデジタルマーケティング(WEBやSNS上で行われる広告・マーケティング)では、やたら略語やカタカナ用語が多くなっています。これらを覚えるのは面倒ではありますが、後ほど出てくる効果測定にも必要な指標もあるため、最初に押さえておくのがおすすめです。
- インプレッション(Imp):広告が表示された回数
- クリック率(CTR):広告がクリックされた割合(クリック数 ÷ インプレッション数)
- CV(コンバージョン):問い合わせや資料請求、購入といった成果につながる行動
- CVR(コンバージョン率):CVに至った割合(CV ÷ セッション数)
- CPA(顧客獲得単価):1件のコンバージョンにかかった広告費
- CTA(Call to Action):行動喚起のためのボタンやリンクのこと
- セッション:Webサイトへの訪問回数
- PV(ページビュー):Webページが表示された回数
- エンゲージメント:SNSなどで「いいね」「シェア」などの反応があった回数
- リスティング広告:検索結果に連動して表示される広告
- ディスプレイ広告:Webサイトのバナーや画像として表示される広告
- SEO(検索エンジン最適化):検索結果で上位表示させる施策
- MEO(マップエンジン最適化):Googleマップなどの地図検索で上位表示させる施策
- LP(ランディングページ):特定の目的に特化した専用のWebページ
気にすべき用語は他にもありますが、難しくならないように、ひとまずここまでを押さえておけば十分です。
5. 広告にかかる費用とは
大きく分けて、広告には次の3つの費用が発生します。
制作費用:広告デザインやキャッチコピー制作にかかる費用
制作費用は広告制作物のデザインやキャッチコピー制作、必要な画像素材の確保などにかかる費用です。チラシやパンフレットの場合は印刷代も必要です。
費用としては、一番これが単純でイメージしやすいと思います。
媒体費用:広告が実際に掲載されるための費用
せっかく広告を制作しても顧客の目に触れなければ意味がありません。
そこで例えば
・TVでCMを流す
・雑誌に載せてもらう
・Yahoo!ニュースのトップにバナーを表示してもらう
・YouTube動画の途中で動画広告を入れる
など、いずれをするのにも媒体費が必要です。
例えば雑誌広告の場合だと、発行部数が多い雑誌ほど広告掲載料は高く、同じ雑誌ならより目立つところに大きな面積で掲載するほど高くなります。(例:表紙をめくってすぐのページに見開き広告とか)また、当然ながら1回だけ掲載するより、年間通して掲載する方が高くなります。
同じようにデジタル広告の場合は、画面上での露出頻度を上げたり、より人目に触れる機会が多いWEBサイトに表示させるには、より多くの費用が必要です。
ただ、
この広告はオーガニック野菜に興味がある人だけに見てもらえればいい
○○市に住む人だけに届けたい
など、顧客の属性を絞り込むことで、予算を抑えつつターゲット顧客に届けることは可能です。
運営費用:広告運用の管理費やレポート作成のための費用
デジタル広告を継続的に行おうとすると、上のようにどんな属性の人に届けたいのかなど、各種設定が必要です。これを社内で行っても良いのですが、専任の担当者がいない場合は広告代理店に依頼することがよく行われます。
その依頼にかかるのが運営費用です。
ホームページを作っただけで、デジタル広告を全く行わない中小企業が多いのは、
媒体費用+運営費用を出すのがもったいない
何でそんなお金が必要なのか理解できない(理解したくない)
という気持ちによるようです。
6.広告代理店との付き合い方
広告に関する知識や経験が少ない場合、広告代理店は非常に頼りになるパートナーとなります。
広告代理店には、得意な分野や規模など、様々な特徴があります。自社の課題や予算に合わせて、最適な代理店を選びましょう。
といっても、少なくとも最初にうちは以前から取引のあった広告代理店との打ち合わせから始まり、その担当者からあれこれ現状などを教えてもらうことになります。
広告代理店との効果的なコミュニケーション
広告代理店と協力して成果を出すためには、密なコミュニケーションが不可欠です。
ポイント:
- 自社の課題や目標を明確に伝える
- 広告の目的やターゲット顧客を共有する
- 進捗状況や効果測定の結果を定期的に確認する
- 疑問点や要望は遠慮せずに伝える
ちなみに、専門用語を連発して顧客を煙に巻くような広告代理店と取引するのはやめましょう。きちんとした広告代理店なら、専門用語は分かり易い言葉に置き換えて説明してくれるはずです。
その上で、例えば
CVRを0.5%から1%に引き上げたい
契約1件当たりの広告費を○○万円以内に押さえたい
など、数字目標を立てましょう
具体的な施策については広告代理店が提案してくるはずです。
先ほど書いたように運用についても依頼すれば(お金はかかりますが)広告代理店がやってくれるため、広告担当者になったからといって、デジタル広告の細かな設定まで自力で出来るようになる必要は必ずしもありません。
ただし目標設定をせずに広告代理店の言われるがままに発注してしまう、というのは禁物です。
7. 経営者や営業スタッフとの向き合い方
ある意味(というか、ほぼ間違いなく)広告代理店とのつきあいよりも社内の人間関係の方が面倒くさいと思われます。なぜなら広告代理店は相性が悪いと思ったら替えることもできますが、社内の人間関係はリセットできないからです。
経営者に対して
経営者に対しては、広告の目的や戦略、期待される効果などを分かりやすく説明することが重要です。また、広告予算の承認を得る際には、費用対効果の見込みを具体的に示す必要があります。
ただ、中には
任せるからやっといて
と言いながら、後になって気に食わないことがあると怒り出す人もいます。

つい先月まで
君に任せる!
って言ってたのは何だったのか…
そういう傾向が明らかな経営者に対してはメールなり証拠が残る形で資料を送付しておく、というのが現実的なサバイバル戦術となります。
営業スタッフに対して
営業スタッフは、顧客の生の声を知る貴重な存在です。広告の効果測定の結果や、顧客からのフィードバックなどを共有してもらい、今後の広告戦略に活かしましょう。
本来、広告は売上拡大のために行うものである以上、営業スタッフからは応援されたり感謝されたりするのが当然のような気もします。が、実際には営業とのいがみあいになることは多々あります。
それは営業の立場からすると
効果が未知数の広告をうつくらいなら、
その予算分だけ販促(値引きなど)の枠をくれ
という考え方もできるからです。
そこで仲違いを防ぐために
広告予算と販促予算は別
ということを、経営者・営業部を巻き込んで最初に明確にしておく方がスッキリします。
さらに営業部の面々と対峙する上で「社長の了承を得ていますので」と言えるような根回しが出来ているとだいぶ心理的に楽です。なお、このセリフをあんまり乱発すると嫌われます。
8. 効果測定の基本
広告の効果を最大限に高めるためには、広告代理店とともに効果測定を行い、その結果に基づいて改善を繰り返すPDCAサイクルを回すことが重要です。
効果測定の具体的な方法
- ウェブサイトのアクセス数や問い合わせ件数を定期的にチェックする
- 広告代理店から効果測定レポートを提出してもらう
- 顧客アンケートを実施し、広告を見たかどうかを確認する
費用対効果の考え方
広告にかけた費用に対して、どれだけの効果が得られたのかを評価することが重要です。デジタル広告を始めた以上、以前に行っていた広告よりも反響単価や成約(購買)単価が下がっている必要があります。
対策の例(ほんの一部)
セッションは多いがCVが少ない
問合せ・注文のフォームがどこにあるのか分かりづらくないか、入力項目が多すぎないかなど見直します。
離脱が多い
魅力的なホームページになっているか、に加えてページの表示速度が遅くないか、などもチェックします。
とはいえ、こういった対策が打てるのも、ある程度セッション数があって(ある程度の閲覧数があって)初めて分析できることです。まずはホームページを見てもらうための誘導が必要となります。
【まとめ】広告担当の道は1日にして成らず
売上を拡大していくには戦略的な広告活動は不可欠であり、その中心となる広告担当者の役割は非常に重要です。場合によっては広告担当になったことを機会に、経営者の直属のような立ち位置となることも考えられます。
兼任での広告担当業務は誰がどう考えても大変ですが、せっかくなので社長と直接話せるポジションになる(かもしれない)ことを前向きにとらえていきましょう。
そして、困った時には遠慮せずに、広告代理店や社内の経験豊富な人に相談しましょう。
ということで、今回はここまで。