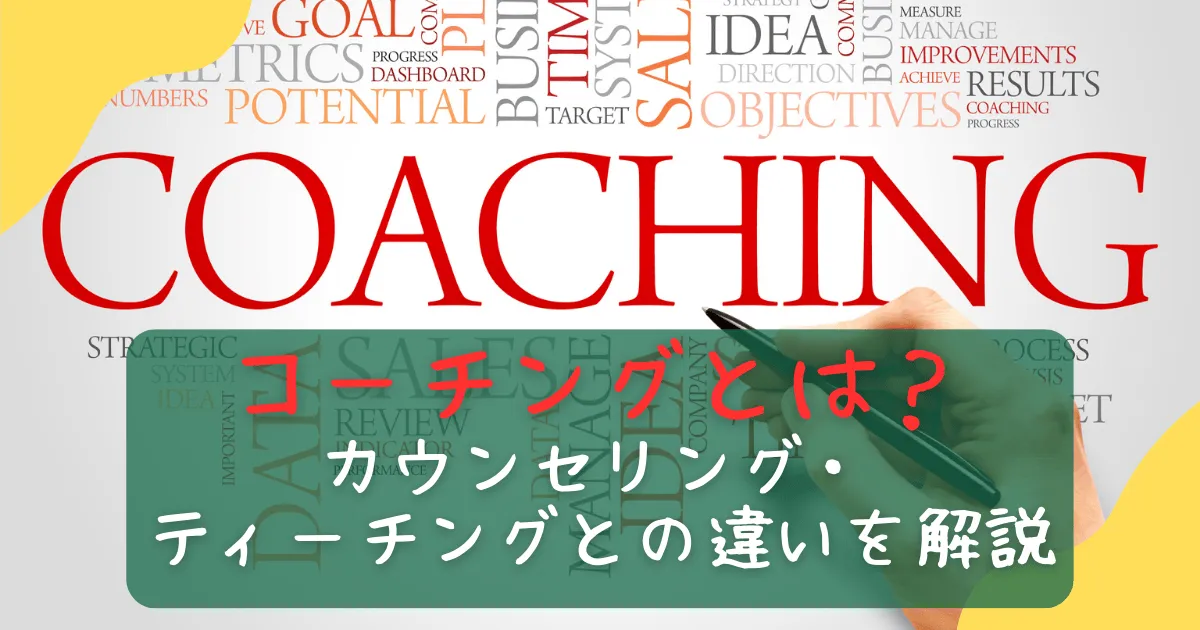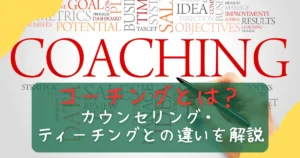※本ページにはアフィリエイト広告が含まれています。
こんにちは、柴山です。
大企業の経営者やプロスポーツ選手が受けていることで話題となった、コーチングをご存じでしょうか?テレビや本でその名前を見たことはあっても、どこか「別世界の話」だと感じるかもしれません。
「そんなすごい人にアドバイスできるなんて、コーチってどれだけ偉い人なの?」
あるいは、
「そもそも、コーチって何をしてるの?」
と疑問を抱いた方もいるかもしれません。
実は──
コーチングは、アドバイスや答えを与えるものではありません。むしろ、本人の中にすでにある“気づきのタネ”を引き出すための会話なのです。
もし、あなたが
- 「このままでいいのか」と漠然と感じている
- モヤモヤするけど、理由がうまく言語化できない
- 誰かに相談したいけど、誰がいいか分からない
そんな気がかりを抱えているなら、コーチングは“今のあなた”のための対話になるかもしれません。
この記事では、コーチングの本質と、他の相談手段との違い、そして「実際どんなふうに進むの?」という疑問まで、解説していきます。
コーチングとは? 他の相談手段との違い
「コーチング」と聞くと、部活動のコーチや、企業研修のイメージが浮かぶかもしれません。
でも実際には、もっと広く、「人生の節目で自分の進み方を見直す」ためのツールとして注目されています。
● コーチングとは?
コーチングは「教える」「導く」といったイメージではなく、
「質問によって気づきを引き出す」というスタンスが特徴です。
コーチ = 正解を教えてくれるアドバイザーではありません。
「どうしたらいいか」を与えるのではなく、「あなたはどうしたいか?」をともに探ります。
その結果、自分自身の中にある答えに気づき、自然と前に進む力が湧いてくるのです。
他の相談手段との違い
| 相談手段 | アプローチ | 主な目的 | 向いているケース |
| ティーチング | 教える (答えを与える) | スキルや知識の習得 | 既存のスキルや知識を学びたいとき |
| カウンセリング | 傾聴・受容 (心のケア) | 心の問題の整理・回復 | 気分が沈む、過去の経験にとらわれているとき |
| コンサルティング | 分析・助言 (問題解決を主導) | 業務や戦略上の課題解決 | ビジネスの課題や改善策を求めているとき |
| コーチング | 傾聴・質問・対話 (内面から引き出す) | 自分の目標や考えの明確化 | 進み方が分からない、迷っているとき |
→ コーチングは「自分の中の答え」にスポットライトを当てる手法。
明確な問題があるわけではないけれど、「このままでいいのか」と感じたときにこそ、その力を発揮します。
“このままでいいのか?”と思ったとき──心のモヤモヤの正体
「今の仕事、このままで続けていいんだろうか」
「なんとなくモヤモヤするけど、理由が分からない」
「周りはみんな頑張ってるのに、自分だけ止まっている気がする」
このような気持ちになるのは珍しいことではありません。
むしろ、「はっきりとした不満はないけれど、なんとなく心がざわつく」そんな感覚を抱えている人はとても多いと思います。
正体の見えない“不安”の中身
人の感情は、必ずしも言葉で説明できるものばかりではありません。
「やる気が出ない」
「先が見えない」
「周りに合わせているだけ」──
こうした感覚の根っこには、自分自身の価値観や「本当はこうしたい」という思いが埋もれていることがあります。
その思いは、忙しさや周囲との関係性、責任感などに押し込められ、やがて「漠然とした不安」という形で心に現れてくることがあります。
「答えをもらう」ではなく、「自分の中の声」を聴くという選択
このような“モヤモヤ”には、明確な正解や処方箋が存在しないことがほとんどです。
従って、「誰かに正解を尋ねる」ということもできません。むしろ他人に判断をゆだねるのではなく、自分の気持ちや本音を整理してみることが大切です。
コーチングが力を発揮するのは、まさにこのような場面です。
自分の心の中を整理し、「自分なりの答え」を探す。その結果、「行動してみよう」という気持ちになる。このプロセスでコーチが果たすのは教師というよりも、伴走者の役割です。
コーチングが向いている人・向いていない人
「コーチングって、誰にでも効果があるの?」
よくあるこの問いに対しては、「相性がある」というのが答えです。
コーチングはあくまで「対話による気づきの支援」であり、万能薬ではありません。ここでは、コーチングを受ける上で、向いている人と、そうでない人の特徴を整理してみましょう。
向いている人の特徴
「今のままでいいのかな」と漠然と感じている人
大きな問題はないが、このまま進んで良いのか不安な人
自分の中に答えはある気がするが、うまく言語化できていない人
考えを整理するために、誰かと話したい人
他人に指示されるより、自分で納得してから動きたい人
こうした人にとって、コーチングは「気づきの加速装置」になりえます。話すことで思考が整理され、自分自身の本音や価値観にたどり着くことができるからです。
あまり向いていないかもしれない人
明確な答えやアドバイスが欲しい人
何をどうすればいいかを手取り足取り教えてほしい人
自分の内面と向き合うより、最短で答えを手に入れたい人
自分以外の誰かに問題を解決してもらうことを期待している人
もちろん、これらに該当する人がコーチングを受けても絶対効果が無い、というわけではありません。
ただ、最初に「コーチングとは答えをくれるもの」という誤解からスタートしてしまうと、期待外れに終わってしまうかもしれません。
コーチングは人から強制されるようなものではない
コーチングの価値は、「本人が自分の意志で向き合うこと」によって生まれます。だからこそ、人に無理にすすめられて受けるようなものではありません。
ただ、何かの考えに固執してしまい、思考が堂々巡りしているのが自分でも分かっているようなとき、コーチとの対話が抜け出すきっかけになる可能性は大いにあります。
実際どんな感じ?コーチングのやりとりのイメージ
「コーチングって、実際には何をするの?」
言葉では何となく分かっていても、いざ受けるとなるとイメージが湧かない方も多いのではないでしょうか。
ここでは、コーチングの典型的なやりとりの一例をご紹介します。
ケース:職場でのモヤモヤを抱えるAさん
クライアント(Aさん/30代・会社員):
「特に大きな不満があるわけじゃないんですけど、最近ずっと、なんとなく気持ちが晴れないんです」
コーチ:
「その“なんとなく”の感じ、どんな場面で特に強く感じますか?」
Aさん:
「うーん……会議のあととか、仕事が終わった瞬間ですかね。“今日も何も変わらなかったな”って思ってしまうんです」
コーチ:
「“何も変わらなかった”と感じるとき、Aさんの中では、どんな変化を本当は望んでいると思いますか?」
答えをもらうのではなく、考えるサポート
このように、コーチは答えを与えるのではなく、問いかけによって思考の整理を助けます。
ときには、こんなやりとりも。
コーチ:
「Aさんが“本当はこうしたい”と思っていることに、もし制限がなかったとしたら、どんな行動をとってみたいですか?」
Aさん:
「……実は、自分の意見をもっと提案してみたいんです。だけど、“そんなの通らないよ”って言われるのが怖くて」
コーチ:
「その怖さを超えるような“目的”や“意味”があるとしたら、それはどんなものでしょうか?」
会話を通して「自分の中の言葉」を取り戻す
コーチングの中では、沈黙も歓迎されます。
話しながら「自分が何にこだわっていたのか」に気づいたり、言葉にしたことで「もう一歩前に進めそう」と思えたりする──
こうした小さな変化を、会話の中で少しずつ積み重ねていきます。
まとめ──「答えを出す力」は、自分の中にある
なにか気になることがあった時、まずは外に答えを探してしまう。例えば、手元にあるスマホで検索する、といったことは日常的にあると思います。
ただ、それが自分自身のこれからのこととなると、ネットの中には答えはありません。そこで自分と同じ分野で活躍している誰かに相談する、アドバイスをもらう、という選択もあるでしょう。
そういった「外から与えられた答え」に納得できればそれで良し。そうでなければコーチングを受けてみることが有効かもしれません。コーチングは決して万能ではありませんが、自分自身の中にある答えを見つけるきっかけになり得ると思います。
ということで、今回はここまで。