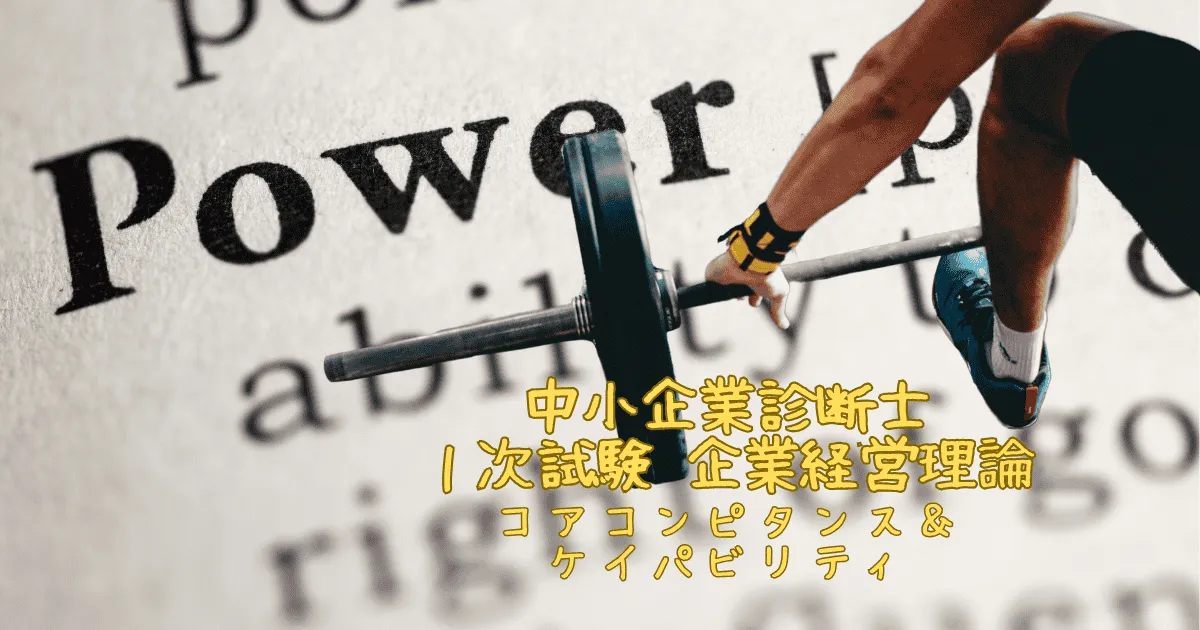※本ページにはアフィリエイト広告が含まれています。
こんにちは、柴山です。
企業の強みについて説明するのに使われる概念として、
- コアコンピタンス( core competenc)
- ケイパビリティ(capability)
というものがあります。
この2つは区別のしにくさ、紛らわしさ加減が丁度良いのか、中小企業診断士の1次試験科目「企業経営理論」でも、ちょくちょく出題されています。
この記事は中小企業診断士の受験生を意識してはいるものの、そうでない方でも試験問題を解いてみることで2つの概念が理解できるようにしてみました。
受験生に対して
試験本番のプレッシャー下では落ち着いて考えるのが難しいので、うろ覚えのまま本番に臨むと混乱する可能性がある。
⇒ この2つの意味するものと違いを定着させる。
それ以外の方に対して
組織の強みを分析する視点にも、様々なものがあることを知る
⇒ 自社や競合他社の分析がより客観的になる。プレゼンなどのビジネスシーンで区別して使い分けることができる。
こういった効果があるはずです。
まずは王道的な解説:コアコンピタンス とケイパビリティ
教科書に載っている解説は次のようなものです。
コアコンピタンス
自社ならではの「特別な技術」や「独自のノウハウ」といった競争力の中核となる能力。顧客に価値をもたらし、一つの製品のためだけでなく幅広く展開が可能なもの。
ケイパビリティ
組織全体の学習能力や変化への適応力、そして顧客との関係構築能力など、より広範囲な能力を指す
いかがでしょうか?
これだけの解説で
俺はもう分かった、充分。
という方は、これ以降を読んで頂く必要はないと思います。
大抵の人は
なんか分かったような気もするし、分かってないような気もする
くらいではないでしょうか?
コアコンピタンス とケイパビリティが3秒で理解できる替え歌(?)
コアコンピタンス とケイパビリティについて、受験生が3秒(くらい)で脳に定着させる方法として
コアコンピタンス は競争力
ケイパビリティは組織力
…と、覚えておくと良いです
読者の世代によっては分かると思いますが、元ネタはTVアニメ「デビルマン」のOPの
デビルチョップはパンチ力
デビルキックは破壊力
です。
「そんな歌は聞いたこともない」という若い方はYouTubeで視聴してみてください。なお改めて考えると何故デビルチョップがパンチ力なのか不明です。(そこは「打撃力」か「切断力」だろと思います)
とりあえず、これを暗記、さらに前述の定義を再確認の上で、練習問題をやってみてください。
練習問題:コアコンピタンス とケイパビリティを区別せよ
いきなり診断士の過去問だと難易度が高いため、簡単な練習問題を作ってみました。
下記①~⑥は「トヨタ自動車」の特徴を表しています。
これらを コアコンピタンス、ケイパビリティ、または いずれでもない に分類してください。
① ハイブリッド技術の開発と普及で業界をリードしている。
② ジャストインタイム生産方式の導入による高い生産効率
③ 自動車の電動化や水素燃料電池車など新技術の開発に取り組む積極性
④ 現地市場に合わせた製品開発やマーケティング戦略を柔軟に展開している。
⑤ 世界中で販売台数トップクラスの実績を持つ。
⑥世界中のユーザーから支持される品質管理体制
正解:
コアコンピタンス ①②⑥
ケイパビリティ ③④
いずれでもない ⑤
①は疑いようもないトヨタの技術的な強みそのもの ⇒コアコンピタンス
②⑥は分かりづらいかもしれませんが、これもトヨタの自動車が世界から支持される要因の一つになっている生産体制の強みのことです。 ⇒コアコンピタンス
③④も若干分かりづらいかもしれませんが、積極性・柔軟性といった組織の特長を指しています。 ⇒ケイパビリティ
⑤はコアコンピタンス やケイパビリティではなく、それらによりもたらされた結果です。
なおトヨタのハイブリッド技術や生産効率、品質管理は単一車種(例:プリウス)だけに活かされるものではないことに注意してください。「一つの製品のためだけでなく幅広く展開が可能」なのがコアコンピタンスです。
ウォーミングアップが出来たところで、いよいよ1次試験の過去問です。
過去問① 令和元年 企業経営理論 第4問
G.ハメルとC.K.プラハラードによるコア・コンピタンスに関する記述として、最も適切なものはどれか。
ア コア・コンピタンスは、企業内部で育成していくものであるため、コア・コンピタンスを構成するスキルや技術を使った製品やサービス間で競争が行われるものの、コア・コンピタンスの構成要素であるスキルや技術を獲得するプロセスで企業間の競争が起きることはない。
イ コア・コンピタンスは、企業の未来を切り拓くものであり、所有するスキルや技術が現在の製品やサービスの競争力を支えていることに加えて、そのスキルや技術は将来の新製品や新サービスの開発につながるようなものであることが必要である。
ウ コア・コンピタンスは、顧客が認知する価値を高めるスキルや技術の集合体であるから、その価値をもたらす個々のスキルや技術を顧客も理解していることが必要である。
エ コア・コンピタンスは、他の競争優位の源泉となり得る生産設備や特許権のような会計用語上の「資産」ではないので、貸借対照表上に表れることはなく、コア・コンピタンスの価値が減少することもない。
オ コア・コンピタンスは、ユニークな競争能力であり、個々のスキルや技術を束ねたものであるから、束ねられたスキルや技術を独占的に所有していることに加えて、競合会社の模倣を避けるために個々のスキルや技術も独占的に所有していることが必要である。
一通り読んで頂くと分かると思いますが。1次試験7科目のうち「企業経営理論」の問題文や選択肢は
- 抽象的
- 回りくどい
- 必要以上に長い
など、試験本番の時間が限られている状況下で、受験生を苛立たせるのに必要な条件を完璧に備えていると思います。
解答するためのヒントは先ほどの通り、
コアコンピタンスは競争力
ケイパビリティは組織力
です。(繰り返し覚えよう)
この問題ではケイパビリティは出てこないので、競争力についてどう説明しているかを意識してみてください。
選択肢ア ×
「スキルや技術を獲得するプロセスで企業間の競争が起きることはない」
⇒人材獲得から始まり社員教育、研究開発など「スキルや技術を獲得するプロセス」でも企業間での競争要素はてんこ盛りです。
例:トヨタが品質管理を高めるための社員教育をしているところをイメージしてください。社員教育そのものにもトヨタのノウハウが詰まっているはずです。
選択肢イ 〇
コアコンピタンスは幅広く応用可能なコア技術で、「将来の新製品や新サービスの開発につながるようなもの」でもあります。
例:前述の通り、トヨタのハイブリッド技術はプリウスだけでなくハリアーその他、様々な車種に使えます。
選択肢ウ ×
「個々のスキルや技術を顧客も理解していることが必要」が間違い
例:トヨタプリウスに乗るからといってハイブリット技術を理解している必要はありません。
選択肢エ ×
コアコンピタンスは特許を取得することもあります。コアコンピタンスだった技術が、より優れた技術の登場により価値が失われることもあります。
例:より優れた技術を他社が開発することで、トヨタのハイブリッドが時代遅れになる可能性が無いわけではありません。
選択肢オ ×
「個々のスキルや技術も独占的に所有していることが必要である。」
コアコンピタンスの構成要素となる技術の一部が他社に模倣されても、それが競争力低下に直結するわけではありません。
例:トヨタはハイブリッド技術に関する特許の実施権を公開しているそうです。だからといってトヨタと同等のレベルで良い自動車を、安定した品質で生産できるとは限りません。(というかできない)
※過去問では「コア・コンピタンス」と、途中で「・」が入っていましたので、そのまま表記しています。
過去問② 令和3年 企業経営理論 第4問
G.ハメル(G. Hamel)とC.K.プラハラード(C. K. Prahalad)によると、コア製品とは、コア・コンピタンスによって生み出された製品であり、最終製品の一部を形成するものである。このコア製品に関する記述として、最も適切なものはどれか。
ア コア製品で獲得したマーケットシェアが、最終製品で獲得したマーケットシェアを上回ることはない。
イ コア製品のマーケットシェアを拡大することは、コア製品への投資機会の増加につながり、コア・コンピタンスを強化する機会になる。
ウ コア製品は、特定の製品や業界につながっているものであり、複数の製品や業界に展開することはない。
エ コア製品を同業他社に販売すると、コア製品を販売した企業の最終製品の競争力は低下する。
難易度はともかく、先ほどの問題よりは短い文章なので、読んでいてイライラすることはないと思います。
この問題では「コア製品」と「最終製品」という用語が出てきます。例えばトヨタが自社でも最終製品(自動車)を作っているが、他社にもコア製品(例:エンジン)をOEMで供給している、みたいな場合ををイメージしてみてください。
選択肢ア ×
自社で作る最終製品のシェアが低くとも、部品としてはシェアが高いことはありえます。
例えばシマノが自転車の完成品も作り、販売を開始したとします(実際のシマノは完成品の販売は行っていない)。そうすると、シマノはギアなど自転車部品では世界のトップシェアですが、完成品は参入したばかりなのでシェアは低い、ということが普通に起こります。
選択肢イ 〇
コア製品のマーケットシェアが高まれば、追加投資もしやすくなりますのでコアコンピタンスにもつながります。これは例を挙げるまでもなく、好調に売れているので追加投資もしやすいと考えるのが妥当です。
選択肢ウ ×
「複数の製品や業界に展開することはない」
⇒前半で書いた通りなので、誤りです。
選択肢エ ×
部品を他社に供給しても、別の部分で商品の魅力を高めることは出来るので、自社の最終製品の「競争力が低下する」とは言い切れません。「競争力が低下する可能性がある」なら適切かと思われます。
ちなみに気づいた人もいるかと思いますが、中小企業診断士1次試験は4択の場合と5択の場合があります。
過去問③ 平成28年 企業経営理論 第3問
近年、自社の経営資源を活用して成長を図る内部成長とともに、外部企業の経営資源を使用する権利を獲得するライセンシングや、外部企業の持つ経営資源を取得して成長を目指していく買収が活発になっている。これらの戦略に関する記述として、最も適切なものはどれか。
ア 相手企業のコア・コンピタンスとなっている技術を自社に吸収し、自社の技術水準を上げていくためには、買収よりも独占的ライセンシングを活用する方が適している。
イ 既存の事業が衰退期に入っている場合、当該業界における市場支配力を高めるには、既存の経営資源を活用するための投資を増強していく内部成長よりも、競合企業を買収する方が適している。
ウ 国内で高価格な製品を製造・販売している企業が、新興国で新たに低価格製品を販売して短期間のうちに軌道に乗せるためには、現地の同業企業を買収するよりも、独自に販売ルートを開拓していく内部成長の方が適している。
エ 製品メーカーが、稀少性の高い原材料メーカーとの取引を安定化し、取引費用の削減をしていくためには、買収によって自社に取り込むよりも、ライセンシングによって関係を構築する方が適している。
再度、文章が長い問題です。メインテーマはコアコンピタンスではなくライセンシングや買収ですが、出来るに越したことはありません。
選択肢ア ×
「自社に吸収し、自社の技術水準を上げていくため」
⇒この目的を達成するなら、買収により相手企業を丸ごと手に入れた方が良いです。
選択肢イ 〇
衰退期に入っている事業で市場支配力を高めるには、競合企業を買収してしまう方が有効な手段です。ちなみに「衰退期に入っている事業」は「衰退期に入っている市場」とした方が選択肢として適切ではないかと思います。
選択肢ウ ×
「短期間のうちに軌道に乗せるためには」
⇒この目的を達成するなら買収の方が向いています。
選択肢エ ×
「稀少性の高い原材料メーカーとの取引を安定化」
⇒この目的を達成するなら買収の方が向いています。
この問題は難易度は高くなく、中小企業診断士の受験勉強中の方でなくても割と解けると思います。
ということで、今回はコアコンピタンス とケイパビリティについて整理しました。今後も紛らわしいビジネス用語を整理するのに役立つような記事を書いていきたいと思います。
今回はここまで。
中小企業診断士 試験対策について(⇒クリックすると開きます)
時間的・地理的な制約を受ける通学講座はいったん除外するとして、独学と通信講座それぞれのメリットは以下のようになります。
独学のメリット
自分のペースで勉強できるのが最大のメリットです。
特に2次試験において、自分なりの解答プロセス構築にじっくりと取り組めるメリットがあります。
通信講座利用のメリット
①質問することができる
②スマホアプリを使って学習できる
③2次を意識した1次の学習ができる
④2次試験の添削を受けることができる
⇒2次の独学にありがちな独りよがりの解答を防げます。
反面、受身になってしまうことで自分なりの工夫・試行錯誤がおろそかになる可能性があります。
過去問について:1次・2次共通で中小企業診断士協会の公式サイトからダウンロードできます。
⇒こちら
解答について:1次のみ公式サイトで正解が公開されています。
⇒こちら(最新年度のみ別ページです)