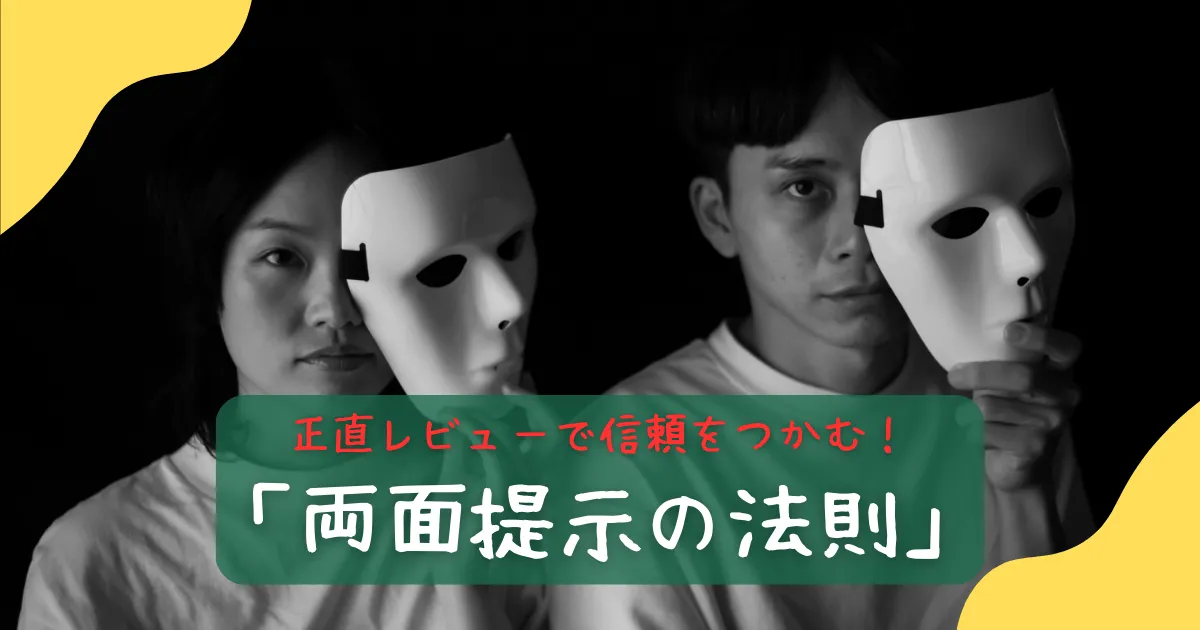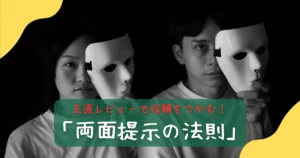※本ページにはアフィリエイト広告が含まれています。
こんにちは、柴山です。
唐突ですが、私は釣りが趣味です。(最近は全然行けていませんが)

だいぶ前に福井県沖で釣った真鯛です。
手が空いた時に気になる釣具について検索してみると、たくさんのブログやYouTube動画がヒットします。そんな中で、私が「あ、この人の言うこと信頼できそうだな」と思える人たちには共通の特徴があります。
それは、スポンサー契約したメーカーとか関係無く、
良いものは良い
悪いものは悪い
そんな風にはっきり発言している人たちです。
(もちろん、こういった方たちは言いたい放題のように見えても慎重に言葉を選んでいるとは思いますが)
皆さんも気になる商品について
「辛口レビュー」
「忖度なし」
「本音トーク」
などのタイトルで解説している動画やSNS投稿を見つけると、ついつい見たくなるのではないでしょうか?
ということで今回は、信頼度アップに効果的な「両面提示の法則」(two-sided presentation)にまつわる心理学について解説してみました。
心理学における「両面提示の法則」とは?
最近の消費者は、メーカー提供のCMよりも、YouTuberによるレビュー動画など、良い点も悪い点も包み隠さず語られる情報を重視するようになっています。

自動車の試乗動画は、かなりの再生数があるようです。
こういったレビュー動画が支持を集め、購買行動に大きな影響を与えているのは、「本当のことが知りたい」という消費者として当然の欲求が背景にあります。
ですが、よく考えてみてください。
「辛口」「忖度なし」とうたっているからといって、それの動画の内容が真実とは限りません。つまり、嘘だったり間違っていたりする可能性があります。
ですが、人の心理としては
「この人はメーカーが触れて欲しくなさそうなことも言っているし、多分本当のことを言っているのだろう」
と、なんとなく思ってしまいます。
このようなに「メリット・デメリット」または「良い面・悪い面」を示されると、ついつい信じたくなってしまう心理を「両面提示の法則」と呼びます。
この法則を理解の上で、メリットだけでなくデメリットや弱点も提示することで、説得力アップが可能になります。
「両面提示の法則」が効果的な広告の例
「両面提示の法則」は、その性質上、広告の分野と強い結びつきがあります。
あらかじめメリット・デメリットの情報が公開されることにより、以下のような効果があります。
- 警戒心を緩和:
特に高額商品の場合、消費者は購入する上で慎重になります。一方的なメリットだけを提示された場合、人は「何か裏があるのでは?」と警戒します。しかし、あえてデメリットも提示することは警戒心を解き、メッセージを素直に受け入れやすくします。 - 納得の上での購入(接種理論):
あらかじめデメリットを伝えておくことで、消費者は「全部、分かった上で購入したから」という心理状態になります。このためクレーム発生やブランドイメージ低下にはつながりません。
まずい、もう一杯!|青汁の例
キューサイ株式会社は、かつて青汁のテレビCMの際に、あえて
「まずい、もう一杯!」
という、CM史上に残る?名セリフを入れました。
これにより、「確かに不味いが、それを上回る健康効果がある」というイメージ作りに成功しました。
 | 価格:4520円~ |
あえて2位を強調|エイビスレンタカー
エイビスレンタカーは1960年代のアメリカにて、あえて自社が2位であることを広告で提示しました。
その上で「2位だからこそ、より顧客のニーズに応えようと努力している」(「We try harder」)というポジティブなメッセージを伝え、顧客の共感を呼びました。
燃費が悪いのは承知の上|スバル車の例
再び唐突ですが、私はスバルの車に乗っています。
スバル車の燃費の悪さはさんざんあちこちで(それこそ日本中、もしくは世界中で)言われています。スバル自体が広告で燃費の悪さをうたっている訳ではありませんが、反対に無理に燃費の良さを伝えようともしていません。
が、それでも一定数のユーザーが承知の上でスバル車を選んでおり、買った後で文句を言う人はあまりいないはずです。(全然いないとは言いません)
「両面提示の法則」 活用事例集
「両面提示」は広告だけでなく、様々な場面で効果を発揮します。ここでは活用できそうな場面をイメージしてみました。
営業・プレゼンにおける活用事例
- 営業トーク:
営業トークにて、自社の強みだけでなく弱みも示すことで、消費者の信頼を獲得し、最終的な購買意欲を高めます。
例:「〇〇という機能はライバル製品に劣りますが、△△という点で優れています」 - 企画のプレゼン:
企画や施策について説明する際に、あらかじめデメリットを説明しておくことで信頼性が高まります。
マネジメントにおける活用事例
- 部下へのフィードバック:
〇〇はOK!△△は改善の余地あり
のような両面からのフィードバックとすることで、部下との信頼関係を築きます。
いきなりダメ出しから始まってしまうよりも、部下のメンタルに優しく、受け入れやすくなります。 - プロジェクトの進捗報告:
プロジェクトの進捗状況を報告する際、順調な点だけでなく、遅延や課題も共有します。よく言われることですが、良いことばかりでなく、悪いこともちゃんと上に伝わるのが、意思疎通がちゃんとできている組織だと思います。
日常生活における活用事例
- 自己紹介での「自己開示」:
初対面の人に自己紹介をする際、自分の長所だけでなく、短所や失敗談も交えることで親近感を与え、打ち解けやすくなります。
例:「明るく社交的な性格ですが、慎重さに欠けると言われることがあります」 - 人の相談にのる場面:
相談にきた相手に、「自分はこうやったら上手くいった」といったことばかりを話すと単なる自慢話になってしまい、相手は聞くだけで疲れてしまいます。むしろ自分の失敗談も交えてを話した方が、相談者は素直に受け止めやすくなります。
「両面提示」のメリット・デメリットと注意点
自分からデメリットを言ってしまったら、時と場合によってはマイナスになるのでは?
…という危険性も確かにあります。
ここでは「両面提示」自体のメリットとデメリットを伝えることで、「両面提示」への信頼度が高めようと思います。つまり、これは言わば「両面提示の法則」のメタ的な実例です。
「両面提示」のメリット
- 信頼性の向上(再確認):
「何を言ったか」より「誰が言ったか」が大事
という言葉を聞いたことがある方は多いと思います。最初にデメリットを伝えることで「この人は正直者だ!」と思ってもらうことは大きな意味があります。 - 長期的な関係構築:
信頼を一度獲得すると、長期的な関係を築く上でも有利になります。
例えば取引先に見積書を提示する度に
これ、ちょっと高いんじゃないの~?
と、疑いの目を向けられるのと、
まぁ、いつも正直な○○さんが出した見積もりなら妥当でしょ!
と、ある程度信頼されているところからスタートするのではだいぶ違うはずです。
「両面提示」のデメリット
- デメリットが強調されるリスク:
当然ながらデメリットの伝え方を間違えて
え?そんなにダメなところがあるの?
と思われたら、元も子もありません。
特に相手が重視するポイントにおいて競合より劣っている場合は、慎重さが必要です。 - 聞き手を選ぶ:
論理を重視するタイプには有効ですが、感情的な人には響きにくいかもしれません。
特に、人の話を最後まで聞こうとしないタイプには、完全に逆効果となる可能性が有ります。(デメリットを聞いた時点で、話を打ち切ってしまう恐れがあるため)最初に相手をよく見極めましょう。 - 高度なコミュニケーションスキルが必要:
デメリットを提示するタイミングや言い回しは非常に重要です。間違えると、ただの自虐や言い訳に聞こえてしまう可能性があります。
「両面提示」を使う上での注意点
- デメリットはほどほどに:
デメリットは、あくまでメリットを引き立てるための材料です。伝えすぎには注意しましょう。 - デメリットの後に、必ずメリットを強調:
「〇〇は少し弱いですが、△△は非常に優れています」というように、デメリットを打ち消す以上のメリットを提示することが重要です。 - テクニックに頼らず、誠意をもって伝える:
そもそも「両面提示」は相手から信頼を得るための一手段です。話術にこだわり過ぎるよりも、誠実な態度で伝えることが最重要です
これらに注意を払い、用法を間違えなければ「両面提示」は、あなたの言葉に深みと説得力を与える強力なツールになり得ます。
メリット・デメリット、そして注意点を踏まえることで、
あなたが同僚、取引先、家族、友人その他から
○○さんの言うことは信頼できる!
という評価を得ることができれば幸いです。
まとめ:「両面提示」で、あなたの言葉を最強の武器に
今回は心理学に則った「両面提示の法則」について、基本から具体的な活用事例などを解説しました。
最初に書いたように、自動車を紹介するYouTuberは既にメーカーからも無視できない存在になっているようです。消費者は高価な商品ほど慎重に情報集めをする傾向がありますので、特に高額商品のマーケティングでは「両面提示」は知らずには済まないテクニックになっています。
また仕事だけでなく、プライベートの人間関係でも「忖度なし」の両面提示は説得力を増すための強力な武器となります。日頃のコミュニケーションに活用することで、周囲からの信頼をがっちりつかんでいきましょう。
ということで、今回はここまで。