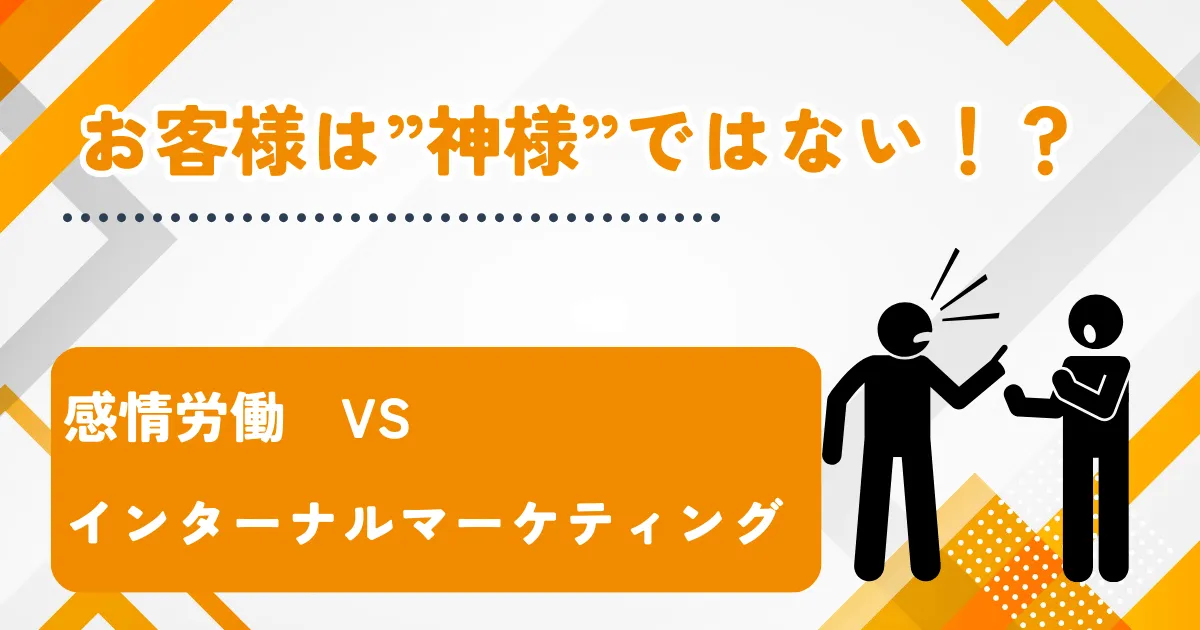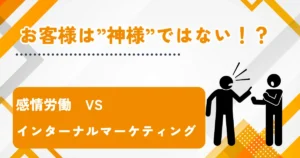※本ページにはアフィリエイト広告が含まれています。
こんにちは、柴山です。
日本には
お客様は神様です
という超有名な言葉あります。
この考えに沿って、我が社はクレームの際にはお客様の言い分を全部受け入れます!という前提であれば良いのですが、
新品交換や値引きは認めない
それでもお客様が納得するように
現場でなんとか対応せよ
ということになると、小売店などの販売現場のスタッフの心労は相当なものになります。
私は以前にインターナルマーケティングについて記事を書いたことがあるのですが、顧客の理不尽な言い分を現場対応だけで全て何とかしろ、と言われたら従業員の満足が高まるどころではありません。
ということで、今回はインターナルマーケティングの視点から、従業員の心をすり減らすような仕事(感情労働)について考えてみました。
今回記事はこんな方におすすめ
- クレームやカスハラ対応をすると、精神的ダメージでしばらく落ち込む
- 理不尽なクレームがあっても上司のヘルプがない
- 顧客以前に、上司の無茶ぶりがひどい
- 上↑のような方が勤める会社の経営者(⇦むしろこちらの方がメイン)
まずはインターナルマーケティングについておさらい
インターナルマーケティングとは企業の行う施策のうち、
まず従業員満足度(ES = Employee Satisfaction)の向上を図り、
↓
それにより顧客へのサービスの質が向上、
↓
結果として顧客満足度(CS = Customer Satisfaction)も向上
こういった効果を狙っていくものを指します。
普通に考えて
こんな会社大嫌い!
早く転職しなきゃ!!
そう思っている従業員が、顧客に対して質の高いサービスを提供できるとは思えないので、理にかなった考え方だと思います。
具体的には、
- 社員教育の充実
- 福利厚生の充実
- 社員割引など、自社製品に親しみやすい環境
- 現場のアイデアを積極活用
など、従業員のモチベーションやエンゲージメント(組織との心理的なつながり)を高め、それによりサービスレベルの向上、最終的には顧客満足度の向上を図ります。
感情労働が従業員の心をすり減らす?
次に感情労働について説明します。
感情労働(エモーショナル・レイバー)とは、アメリカの社会学者アーリー・ホックシールドが提唱した概念です。
この用語は2つの意味で使われます。
- 本来の自分の感情を抑えて「職業的に求められる感情表現」を演じなければならない業務
- 上のような仕事によって生じる心理的負担そのもの
この記事内では、分かりづらくなることを防ぐために前者(業務)の意味で使い、後者は文脈に合った別の言葉に置き換えることにします。
さて、本来の自分の感情を抑えなくてはならない、具体的な場面としては
- 店頭や電話窓口でのクレーム処理
- 常に笑顔が求められる接客
- 値引きを要求してくる取引先との交渉
- 言うことを聞かない生徒の指導
- 医療や介護の現場対応
こういった怒りの感情などが湧いても、それを表に出すことが許されないものが該当します。ジャンルとしては、接客や営業の他に、教育、医療、看護が代表的なものです。
なお感情労働には社内的な事も含まれます。
例:
- 言うことを聞かない部下への指導
- 気に入らないことがあるとすぐ感情的になる上司への対応
このため、広い意味で考えるなら、対人的な仕事全般ということになります。
対人の仕事には「演技」が要求される
こういった仕事に従事する上では、次のような演技が必要になります。
- 表面的演技(Surface Acting):
→ 内心ではイライラしていても、表情だけ笑顔にするような演技 - 深層的演技(Deep Acting):
→ 本心から相手の立場を理解しようとし、感情そのものを調整する努力
どちらが良い/悪いというものではありませんが、表面的演技とは要するに自分を取り繕うことなので、これが続くと本心とのギャップが大きくなりやすく、心身の負担も大きくなります。
それに対して深層的演技はより前向きと言えるものの、相手の言っていることが理不尽だったり、自身の価値観と合わないものだったりすると、やはり心の負担になります。こうした、無理に相手に共感しようとして心が消耗することを「情緒的消耗」・「共感疲労」と呼んだりします。
こういった心の消耗は、酷いときは燃え尽き症候群(バーンアウト)からの退職につながる可能性さえあります。
感情労働を軽減するために組織ができること
感情労働を、個人の我慢や現場の努力だけで乗り切らせようとする組織では、嫌な役割や責任を押し付け合う風潮がまん延し、職場の雰囲気も悪くなります。
そういった事態を防ぐうえで、産業医によるストレスチェックなど、メンタルヘルスの見地から考える方法もあります。が、この記事では最初に書いたように、インターナルマーケティングの視点から経営者や上司が何をすべきかを考えることにします。
接客マニュアルに「どこまですべきか」を明記する
クレームがあった際に
お客様は神様
等と考えずに、
- どこまで現場で対応するか、そのためにどれだけの権限を与えておくのか
- 本部(本社)はどうやってサポートするのか
- どのような言動が許されないか
といったことをマニュアルに明記すれば、従業員が自分を守りながら業務にあたることができます。最初に書いたような、新品交換や値引きの権限は無いのに何とか対応しろ、というのは無理な話です。
逆に言えば現場にある程度の権限を与えておくことで、いちいち本部で判断しなくても良くなるので、クレーム対応の迅速化と同時に無駄な仕事を減らせます。
決めごとの例
- 顧客からの暴言・威圧・人格否定発言には毅然と対応し、一定回数で上長に代わる
- 土下座要求、写真・動画の撮影強要、SNSでの脅迫などがあった場合は、即時退席・警察連絡も視野に入れる
- 過剰・不合理な謝罪要求については、「対応を打ち切る権限」が現場にあることを明示する
なお、顧客の言い分の方が理にかなっているならば、それに沿って対応するのは言うまでもありません。
カスハラ事例は「チームで対応する」体制を作る
マニュアル作成以外にも、カスハラへの対応をチーム制にすることは従業員を守ることにつながります。
- トラブル発生時は、すぐにフォロー役が現場に入るルールを明示しておく
- 状況を共有できる「トラブル対応ノート」やチャットツールを活用し、社内で情報共有
- 定期的な「対応振り返りミーティング」や「メンタルフォロー面談」を設ける
こうした情報共有やミーティングにおいては、担当者が責められることが無い「心理的安全性の確保」が重要です。
当然ながら、対応が終わってから
俺が担当だったら、
もっと上手く対応できた!
とか
あんな客の言い分なんか
無視すれば良かったのに!
など、外野が無責任な発言をすることはNGです。
「そんなことを言うなら今度からお前が全部対応しろ!」という不毛な言い争いにしかなりません。
マニュアル作成(と、それに伴う権限の委譲)やチーム制にすることの目的は、両方とも担当者1人のせいにしない、あくまで組織で対応する、ということを忘れてはいけません。
まとめ──インターナルマーケティングに感情労働の視点を
従業員満足を高め、組織の力を底上げするインターナルマーケティング。
その効果を真に発揮するためには、「従業員の感情への負担」への理解が欠かせません。
接客やチーム内の人間関係など、目に見えない場面で、従業員たちは「こう振る舞わなければいけない」という空気の中で日々感情を調整しています。
このような“演じることの負荷”に対して組織が無関心であれば、いくら理念やビジョンを掲げたとしても、現場にとっては意味をなさず、ただの綺麗ごとに終わってしまいます。
さらに、マニュアルやチーム制を作ったとしても、問題を見て見ぬふりをする事なかれ主義の社員を責任者にしてしまったら全てはぶち壊しです。そういう意味ではインターナルマーケティングをやり切るには人事の果たす役割も非常に大きいと言えます。
ということで、今回はここまで