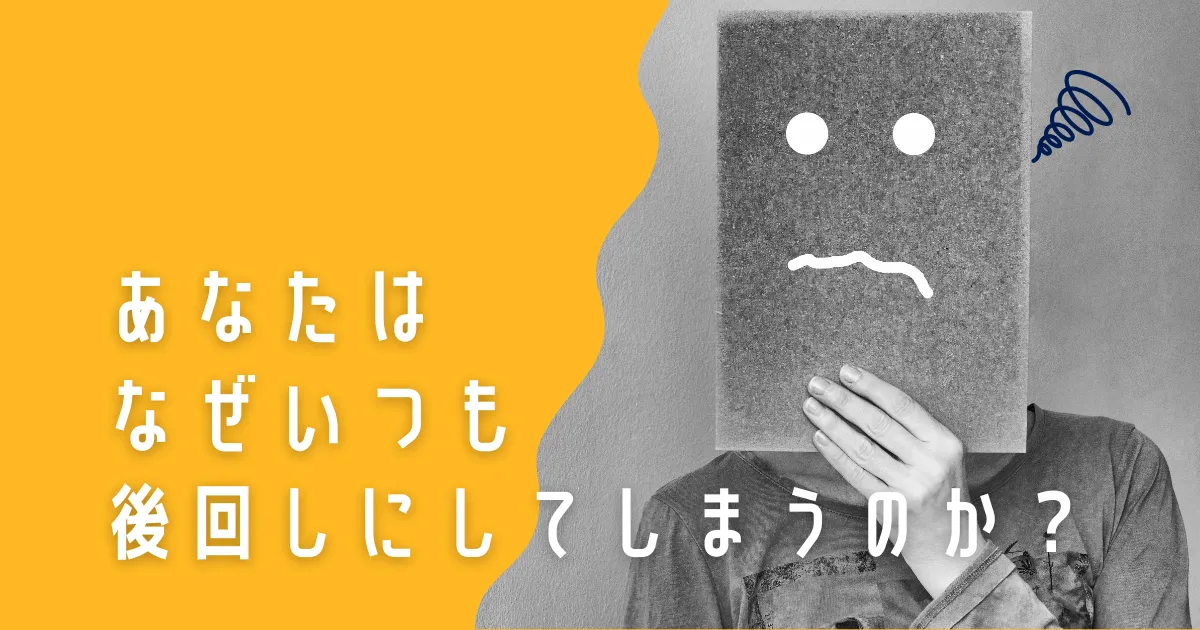※本ページにはアフィリエイト広告が含まれています。
こんにちは。柴山です。
今回は「グレシャムの法則」(Gresham’s Law)です。
これは元々は経済学の用語で、悪貨は良貨を駆逐するという格言の根拠となった考え方です。
例えば金の含有量が低い金貨(悪貨)が出回るようになると、額面価値が同じでも金の含有量が高い金貨(良貨)は皆が手放さず手元に保管するようになるので、市中には悪貨ばかり流通するようになる、といった現象が起こるそうです。
今回はこの現象に関して経済学の話を…最後の方で少しします。どちらかと言えばマネジメント・意思決定の文脈で「グレシャムの法則」が使われる場合のことをメインに、身近な例を挙げて説明します。
その他、中小企業診断士の1次試験科目「企業経営理論」の過去問解説もあります。予備知識が無くても解ける問題をピックアップしましたので、受験生以外の方でも良かったらチャレンジしてみてください。
急ぎか?重要か?経営判断における「グレシャムの法則」
マネジメントの分野で「グレシャムの法則」が言及される場合は、経済学とは異なる文脈で使われます。
それは、
重要だけど急ぎではなく、
かつ定型化されていない仕事について
考えるのが面倒臭いからといって
意思決定を後回しにしないように!
というものです。
これだけでは分かりにくいので、例えば仮に下記4つような案件があったとします。
①今月末の支払いの為の資金繰り
②次世代の幹部社員の育成
③今日のランチを何にするか
④来年のGWの過ごし方
これを表に落とし込んでみると…
| 急ぎ | 急ぎではない | |
| 重要 | ①重要かつ急ぎの案件 | ②重要だが急ぎではない案件 |
| 非重要 | ③重要ではないが急ぎの案件 | ④重要でも急ぎでもない案件 |
さすがに①をないがしろにする人は普通にいないと思います。
③④はもともと重要性が低いので、適当に決めたとしても、あるいは先送りにしたとしてもダメージは小さいでしょう。
ということで、問題は②です。
これを切羽詰まってからあわてて決めるのか、時間に余裕があるうちにしっかり考えるのか、その違いは会社の未来を左右します。こういった案件を考えることにきちんと時間とエネルギーを割くのが、優れた経営者、マネージャーの条件ではないかと思います。
ルーチン化してる業務・していない業務と「グレシャムの法則」
上では案件を「急ぎか急ぎでないか」「重要か重要でないか」によって区別しました。これとは別の観点として、その案件が定型化されている、つまり既にやり方が分かっているのかそうでないかで区別する考え方があります。
例えば、貴方が設立したばかりのECサイト運営会社では、クレーム処理の仕組みづくりがまだだったとします。
いずれはクレーム案件が発生する可能性はあるものの、幸いにも現時点ではこれといった苦情も無かったとすると、貴方は次のように考えるはずです。
早くクレーム対応マニュアルを作らないといけないけど、それより先に今日A社に送る見積書を作らないと…
これはつまりこういう心理です。
◇見積書作成(日常的にやってる)
→既に自分の中でやり方が分かっている仕事なので、考える要素が少なくラク
◇クレーム対応マニュアル作成(やったことがない)
→あれこれ調べたり考えたりしないといけないので面倒
人間は基本的に面倒臭がりなので、やり方が分かっている定型的な仕事(=ルーチンワーク)が目の前にあることを言い訳にして、面倒臭いけれど重要な仕事を後回しにしてしまう、ということをやりがちです。
先ほどの「次世代の幹部社員の育成」と同様、こういう落とし穴にはまらないようにね、というのが「グレシャムの法則」が伝えるメッセージとなります。
そこで考える、経営者・上司の本来の役割とは
経営者を含む上司、つまり部下を持つ立場の方は自分の仕事を部下に振ることが出来ます。
そこで仮に貴方が営業部長だったとして、貴方がやるべきことは事務作業を部下に押し付けて自分は仲の良い取引先の方と飲みに行く…、ではありません。
いや、別に飲みに行ってもいいんですが、部下に仕事を振ることができる立場の方がすべきことは他に有ります。もう、お分かりかと思いますが
◇今はまだ急ぎではないけど重要な案件
◇社内でやり方が定まっていない(=誰かがじっくり考えないと進まない案件)
ここらへんのことを、
貴方が先送りにした場合、そしてライバル企業が先送りしなかった場合、貴方の会社はライバルに後れを取ることになります。
そのような事態を回避するために貴方がすべきことは、部下がパンクしない程度に仕事を移譲してしまい、自らは考える時間を確保した上で、上のようなタイプの案件ときちんと向き合うことです。
ここで、
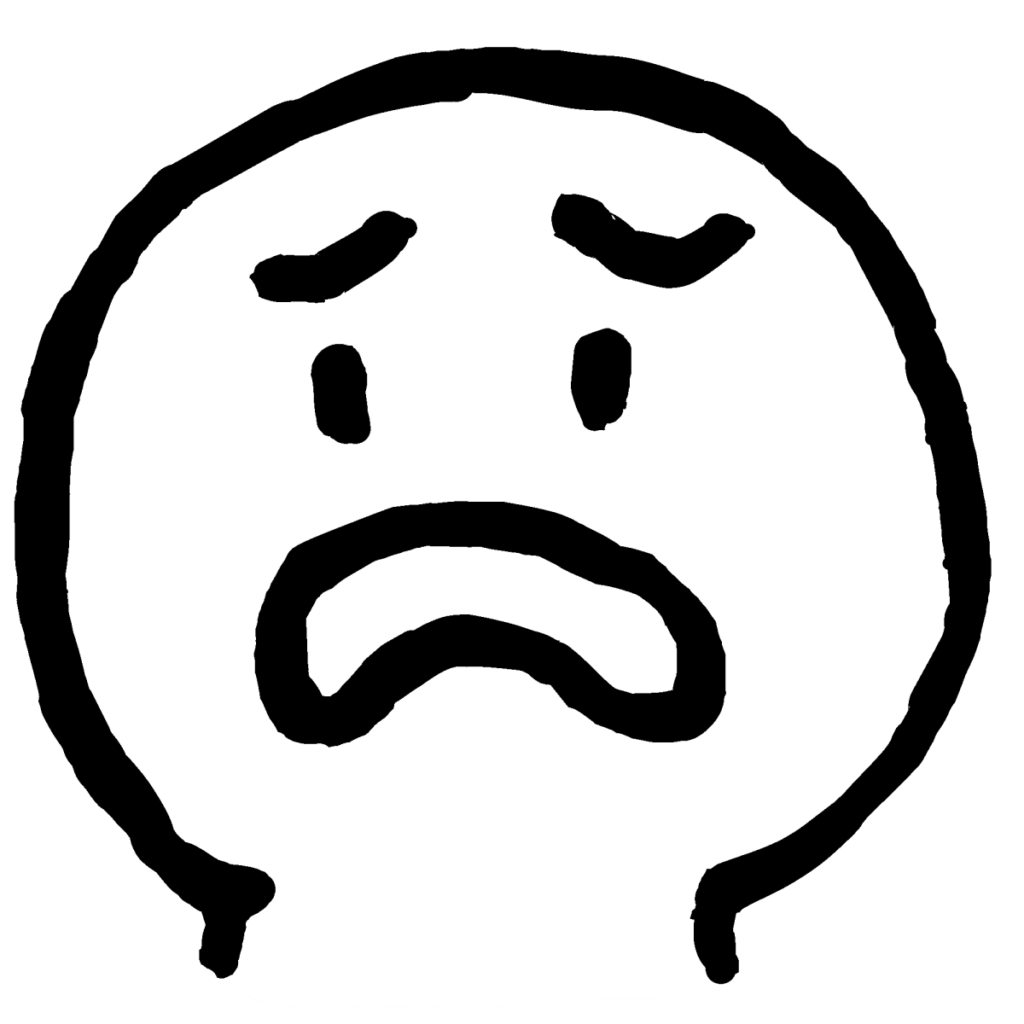
いやだ、面倒臭い…
そう思った方は、このブログの主旨(というかグレシャムの法則)を全く理解できていない可能性がありますので、最初から読み直してください。
過去問解説 H28年1次試験 企業経営理論 第14問
さて、それでは中小企業診断士試験の過去問をやってみます。興味が無い方はスルーして頂いて結構ですが、せっかくなので、ここまでに読んだことが理解できているかどうか、ぜひ試してみてください。
第14問
官僚制の逆機能といわれる現象に関する説明として、最も不適切なものはどれか。
ア 革新的な計画に抵抗するために、日常のルーティン対応を探し求める、グレシャムの法則。
イ 規則や手続きそのものを絶対視するような態度が、杓子(しゃくし)定規な画一的対応を生み出す、形式主義。
ウ 組織全体の利益よりも、自分が所属する部局の利益を優先する、セクショナリズム。
エ 膨大な手続きと書類作成に煩わされる、繁文縟礼(はんぶんじょくれい)。
オ 本来は手段にすぎない規則や手続きが目的に転じてしまう、目的置換。
ひとくちに1次試験の問題といっても難易度は様々ですが、これは比較的易しい問題かと思います。ちなみに官僚制の逆機能とは官僚制組織のデメリットくらいに読み替えて頂けば問題ありません。
「グレシャムの法則」が指摘する、
- 重要だけど急ぎではない
- 定型化されていない
こういった案件が先送りされる傾向は、選択肢 ア にあるような「革新的な計画に抵抗するために」などという意図的なものではありません。むしろどちらかというと意思の弱さや怠惰に由来するものです。
ということで正解(=最も不適切)は選択肢 ア です。イ~エには普段あまり見かけないような4文字熟語が含まれていますが、落ち着いて読めば不適切な内容が無いことは判別可能だと思います。
様々な文脈での「グレシャムの法則」
歴史・経済におけるグレシャムの法則
最初に書いた「悪貨は良貨を駆逐する」という意味でのグレシャムの法則は、貨幣制度の歴史において重要な役割を果たしてきたようです。
例えばローマ帝国の衰退期には純度の低い貨幣が大量に鋳造された結果、人々が価値の高い貨幣を隠して低品質の貨幣ばかり流通させるようになったため、経済が混乱しました。
16世紀イギリスの財政顧問トーマス・グレシャムがこれを提唱した当時には、金や銀の含有量が異なる貨幣が同時に流通しており、人々は価値の高い「良貨」を手元に残し、価値の低い「悪貨」だけを使用するようになっていました。この行動が文字通り「悪貨は良貨を駆逐する」という現象を引き起こしたのです。
ちなみに、「地動説」で有名なニコラウス・コペルニクスも同じような学説を唱えていたそうです。
「計画のグレシャムの法則」
以上のように元々は貨幣制度について説明するためだった「グレシャムの法則」ですが、とある経済学者によって違う意味に使われるようになります。
それが今回の記事の前半で書いたようなマネジメント・意思決定の文脈で、「人々は日常業務(悪貨)に追われていると長期的で重要な計画(良貨)のことを考えられなくなってしまう」というものです。この考え方は「計画のグレシャムの法則」と言われることもあります。
現代のSNS社会における「グレシャムの法則」
この法則は、現代のインターネット空間でも見られます。
例えば、SNSやブログ上で質の低い情報(噂・煽り・極端な意見)が拡散されやすく、時間と手間をかけた良質な記事が埋もれてしまう現象も、まさにグレシャムの法則が示す構造です。「短絡的な情報」が「本質的な知見」を駆逐する、そんなジレンマがデジタル時代に再現されています。
インパクトのある情報、怒りや嫉妬など人の感情に働きかけやすい情報が人々の注目を集めやすい傾向は、読者の皆さんも日頃から感じているかと思います。
おわりに
ということで、今回は様々な意味で使われる「グレシャムの法則」について解説してみました。
ある日、重要な問題を先送りにしてルーチンワークに没頭している自分に気が付いたら
やばい、今の自分は「グレシャムの法則」発動中だ!
みたいな危機感とともに我に返って頂ければと思います。
今回はここまで。
中小企業診断士 試験対策について(⇒クリックすると開きます)
時間的・地理的な制約を受ける通学講座はいったん除外するとして、独学と通信講座それぞれのメリットは以下のようになります。
独学のメリット
自分のペースで勉強できるのが最大のメリットです。
特に2次試験において、自分なりの解答プロセス構築にじっくりと取り組めるメリットがあります。
通信講座利用のメリット
①質問することができる
②スマホアプリを使って学習できる
③2次を意識した1次の学習ができる
④2次試験の添削を受けることができる
⇒2次の独学にありがちな独りよがりの解答を防げます。
反面、受身になってしまうことで自分なりの工夫・試行錯誤がおろそかになる可能性があります。
過去問について:1次・2次共通で中小企業診断士協会の公式サイトからダウンロードできます。
⇒こちら
解答について:1次のみ公式サイトで正解が公開されています。
⇒こちら(最新年度のみ別ページです)