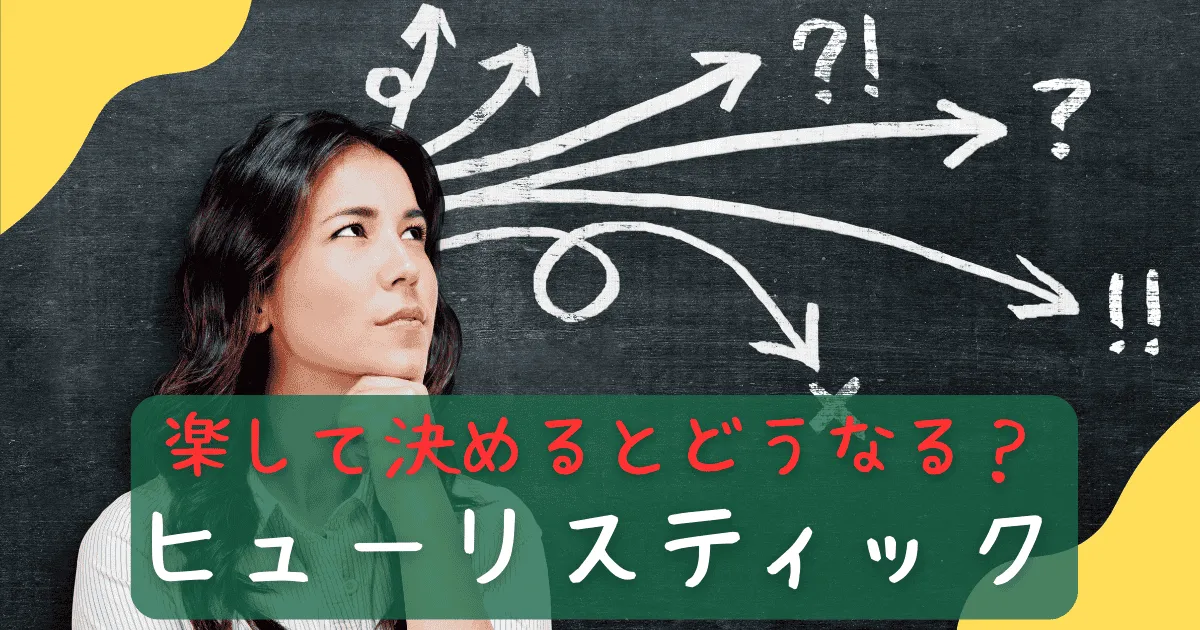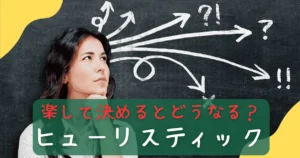※本ページにはアフィリエイト広告が含まれています。
こんにちは、柴山です。
仕事や日常生活の様々な場面で、「長年の勘」みたいなものが働くときがあります。
例えば、初対面の人に対して、
ん…?
なんかこの人、
変かも…
みたいに感じたことはないでしょうか?
どことは具体的には言えないけど違和感がある、と思っていたら、後々その人とトラブルになった…。そういった経験がある方も多いのではないかと思います。一方で、それとは真逆に第一印象は当てにならないという経験がある方も多いはずです。
今回はこうした
「なんとなく~だろう」
「なんか~ではないか」
といった経験則に基づく直観的な判断、すなわちヒューリスティックについて、その特徴や活用方法、注意点などをまとめてみました。
注意:IT分野におけるヒューリスティックとは?
ヒューリスティックアルゴリズムとも言い、最適解を保証するわけではないものの、経験則や直感に基づいて、実用的な時間で許容できる品質の解(近似解)を見つけることを目的としたアルゴリズムの総称のことです。(この記事では扱いません)
まずはヒューリスティックの意味と考え方を整理
ヒューリスティックに限らず、人間の心理に関する用語・概念を説明しようとすると、どうしても抽象的になりがちです。
この章ではヒューリスティックおよび関連用語について、例え話を用いるなどして、なるべく分かり易く説明してみます。
前置き:直感と直観の違いとは?
少し脱線しますが、皆さんは「直感」と「直観」の違いを説明できますか?
この2つの区別は日常生活をする上でほとんど意識することはなく、もしかしたら一生の間に一度も意識することも無い人の方が多いかもしれません。ちなみに私は今回の記事を書くために調べて、初めてこの2つの違いを知りました。
異論はあるかもしれませんが、おおむね以下のようになります。
直感:動物的、本能的な感覚
意識的な思考を介さずに身体や感情の動きとして現れる、生き残るための反応。
直観:経験や学習にもとづく感覚
長年の経験や知識の蓄積に基づき、無意識のうちに発揮される洞察力。
ちなみに日本語には「勘」という言葉がありますが、上記の考え方にあてはめると…
- 野生の勘は「直感」
- 長年の勘は「直観」
ということになります。
ヒューリスティックは「直観」または「思考の近道」と捉えると分かり易い
ヒューリスティックは1970年代に心理学者のダニエル・カーネマンとエイモス・トヴェルスキーらによって研究が進み、行動経済学の礎となった概念です。
従来の経済学では「人間は合理的に判断する」という前提を元に理論が組み立てられていました。一方、行動経済学では、経済学に心理学の要素を取り入れ、人間の非合理的な行動に焦点を当てています。
それによると、人間の判断には「経験にもとづく思考の近道」を使うことで意思決定のスピードを優先しており、それをヒューリスティックと呼びます。
つまり前述の「直観」と「直感」の2つで言うと、ヒューリスティックは前者「直観」に該当します。
典型的な例:
- 数えきれない程の面接を行ってきた人事担当が、第一印象で相手の人柄をある程度見抜く
- 小売業界のバイヤーが、売れそうな商品とそうでない商品を感覚的に見分ける
- 飲食店経営のベテランが、店に入った第一印象で繁盛しそうか言い当てる
このようなプロフェッショナル的な経験に基づいた「なんとなくそう感じた」でなくても、初対面の人の第一印象が割と正確だった、といった経験は誰にでもあるのではないでしょうか?
そういった場合も、皆さんそれぞれの人生経験、つまり直観に基づいて
「あ、この人を信用するとヤバいかも」
のように意識下で判断が行われています。
 | ファスト&スロー 上 あなたの意思はどのように決まるか? (ハヤカワ文庫NF) [ ダニエル・カーネマン ] 価格:1210円 |
 | ファスト&スロー(下) あなたの意思はどのように決まるか? (ハヤカワ文庫NF ハヤカワ・ノンフィクション文庫) [ ダニエル・カーネマン ] 価格:1056円 |
ヒューリスティックは素早い判断に役立つ
人間は生きていく上で数多くの判断、つまり意思決定をしなければなりません。
細かいこと、重要性が低いことまで、いちいち真剣に考えるとすると…
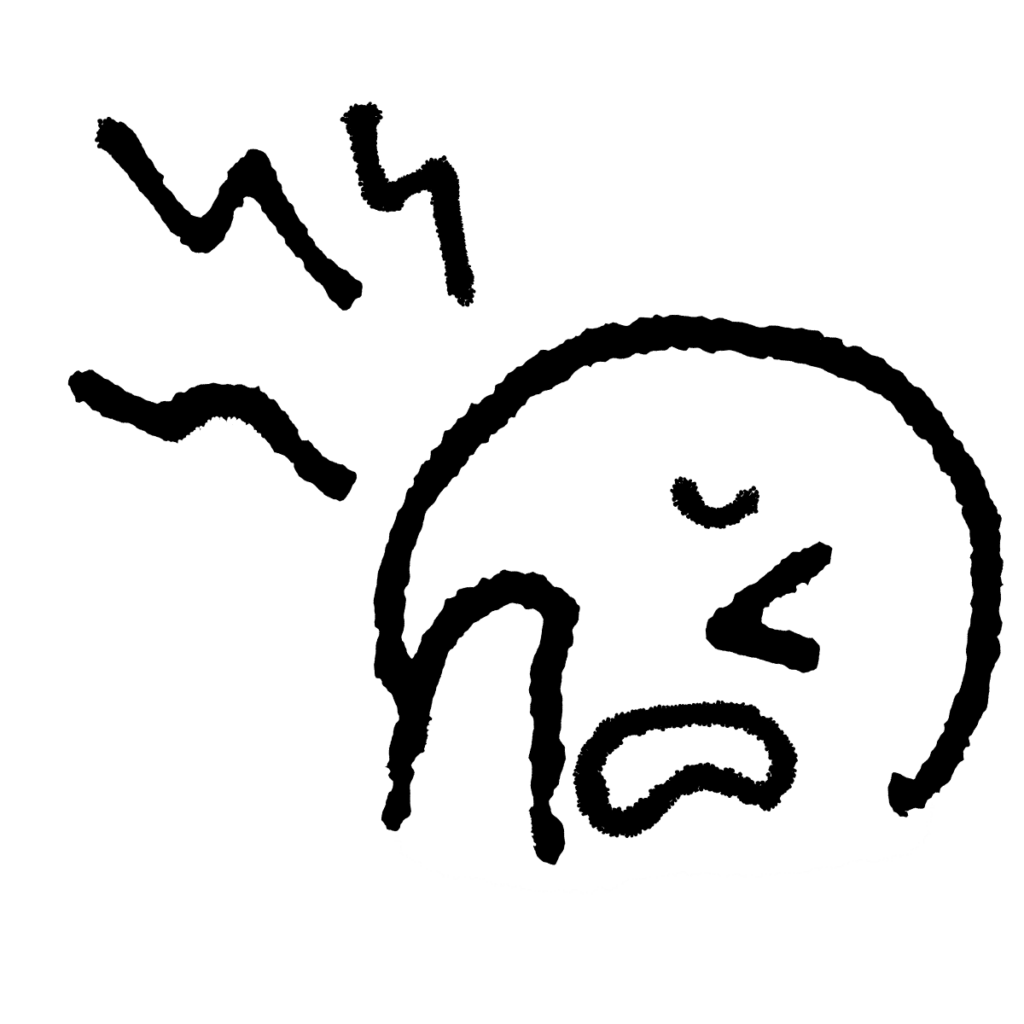
今日の晩御飯どうしよう、
明日まで考えるわけにはいかない…
このように時間がいくらあっても足りないので、「なんとなく決める」ことは、ある意味で理にかなっているとも言えます。
つまり、ヒューリスティックは
慎重さ、正確さよりも「とりあえず」の速さを優先する
という思考のメカニズムです。
考えるのを省いた結果生まれる、「認知バイアス」とは?
ヒューリスティックに関連する用語として、「認知バイアス」について例え話を使って解説します。
間違った(偏った)思考と結論の例
採用人事の場合
①過去の採用経験から「最近の若者は忍耐力がない」という印象を持つ
②面接の応募者全員を「この人もすぐに辞めそう」という先入観で見てしまい、有望な若者を見落とす
商品開発の場合
①過去にヒット商品を生み出したベテラン社員の意見を重視
②結果的に若手社員の意見を軽視してしまい、競合他社に後れを取る
つまり、
- ヒューリスティック:過去の経験などに基づき、近道して判断する思考法
- 認知バイアス:ヒューリスティックの結果として生まれた偏った判断
こんな感じになります。
経験に基づく判断を過信してしまい情報収集を怠った、情報は有ったのに自分の考えと合わなかったので無視した、などにより判断の誤りが発生します。
なお、ヒューリスティックに頼った判断をしても、必ず間違えるというわけではありません。最初の方で書いたように、「長年の勘」が有効に働く場合も多々あります。
ヒューリスティックの主な種類と具体例
ヒューリスティックにはさまざまな種類がありますが、ここでは代表的なものをいくつか押さえておきます。
代表性ヒューリスティック(Representativeness Heuristic)
面接時に応募者Aさんが物静かで几帳面なタイプだと「この人は経理職に向いていそうだ」と感じ、逆にBさんが社交的でプレゼン巧みだと「営業向きだな」と即断してしまうことがあります。
こんな感じで「○○は典型的な□□」と推測してしまうのが、代表性ヒューリスティックです。実際にはAさんが営業の才能を持っていたり、Bさんが実は対人ストレスを抱えやすい性格かもしれません。
代表性ヒューリスティックによって表面的な印象に引っ張られることで、客観的な判断ができなくなる可能性があります。
利用可能性ヒューリスティック(Availability Heuristic)
利用可能性ヒューリスティックとは、頭の中で思い出しやすい情報に頼って判断してしまう思考パターンです。
たまたま直近に見聞きした出来事や強く印象に残ったニュースなどがあると、その情報だけを判断の根拠にしてしまいがちです。
利用可能性ヒューリスティックの例:
街頭インタビューで
「最近の若者のことをどう思うか?」と聞かれた場合
◇今朝、たまたま電車で席を譲る学生を見たAさんは、
「最近の若者は見所がある。日本の将来が楽しみだ」と解答
◇今朝、たまたまニュースで若者による凶悪犯罪を知ったBさんは、
「最近の若者はダメだ…、日本はもう終わってる」と解答
こんな感じで、自分がその場ですぐ思いだせる情報(=利用可能な情報)だけで判断した結果、偏った結論となる可能性があります。
当然ながら、これでは判断ミスとなる可能性がありますので、重要な意思決定時には自分がすぐに思いだせる情報だけに頼らないように注意する必要があります。
アンカリング(係留)と調整ヒューリスティック(Anchoring & Adjustment)
通常価格:〇〇〇〇円
⇒今なら30%OFFで、驚きの〇〇〇〇円
…こんな感じで表示されていると、すごくお得に見えます。ただ、そもそも通常価格:〇〇〇〇円が他店よりも高かったらどうでしょうか?
アンカリングと調整のヒューリスティックとは、最初に提示された数字や情報(アンカー:錨)を基準にしてしまい、その後の判断が引きずられる現象です。
最初に提示する情報の選び方ひとつでユーザーの判断基準を誘導できてしまう点は怖くもありますが、活用方法次第では有効な心理テクニックにもなります。
ヒューリスティックのメリットとデメリット
ヒューリスティックのメリット
ヒューリスティック最大の利点は、なんといっても判断のスピードと省力化です。
限られた情報でも即座に「だいたいこんなものだろう」と結論を出せるため、日常生活やビジネスの現場で私たちは大量の小さな決断を短時間でこなせています。
とは言っても、重要な場面ではきちんと情報収集してから判断するなど、慎重さが必要なのは言うまでもありません。
ヒューリスティックのデメリット
重要な意思決定や新規性の高い問題、複雑な案件に対して「なんとなく」で判断すると、大きな損失につながりかねません。
ヒューリスティックによる判断は
「自分の経験値から、このように確信しております」
…のように本人が自信たっぷりな場合があります。
周囲から見ると明らかに非合理な結論でも「自分は正しいはずだ」と思い込んでしまっており、しかも実績のある人の意見だけに覆すのが難しい、となると厄介です。
特に即断即決型の経営者の判断は、本人もいかにも自信たっぷりで、周囲の人からも頼もしく見えるかもしれません。が、後から振り返ってみると何の根拠も無い、とんでもない間違いだったというのはあり得る話です。

「あの時、みんなで社長を止めてさえいれば…」
…とか悔やんでも後の祭り
ヒューリスティック活用術:マーケティングや意思決定に
ヒューリスティックの特徴およびメリット・デメリットを理解すると、ビジネスでは主に二つの方向で役立てることができます。
一つは広告やマーケティングに活用、自社の製品を選んでもらうよう顧客を誘導するやり方です。
もう一つは反対に、自分および自分が属する組織が、重要な意思決定を直観任せにしないようにすることです。
マーケティングで「なんとなく選んでもらう」には?
消費者の購買行動においては、多くの場合は直観的な判断が行われています。
自社の製品が競合他社と比べてスペックで見劣りしていたとしても、やり方次第では直感的な判断を促すことで顧客に選んでもらえるかもしれません。
みんな使っている
「利用者数No.1」「○○万人が愛用」といった実績データを示し、多数派の安心感で判断してもらう(=多くの人に選ばれている商品はきっと良いはずだ、というヒューリスティックを促す)。
とっても希少
「期間限定〇〇」「残り在庫わずか!」など希少性を強調して急いで選択させる(=手に入れ損ねたら損だと感じ、深く考える前に行動させる。これは行動経済学で言うプロスペクト理論(後述)の損失回避の心理とも合わさっています)。
これを選べば間違いない
「当店人気No.1ランチ!」など、おすすめ品を明確にする(選択肢を絞り、迷わせないことで直感的に選びやすくします)。
ただし、消費者をミスリードするような手法には注意が必要です。
商品の本質とズレたイメージを与えすぎると、購買後に「こんなはずじゃなかった」と感じさせてしまい信頼を損ねる恐れがあります。あるいは、「あの店は変なものばかりすすめてくる」と、信用を堕としてしまうかもしれません。
ヒューリスティックはあくまで意思決定を後押しするものと考え、日頃の誠実な情報提供とのバランスをとることが重要です。
判断ミスを防ぐには:経営者・担当者ができること
一方、私たち自身がヒューリスティックに振り回されないようにする工夫も欠かせません。
人の心の中にヒューリスティックという仕組みがあることを知っていれば、特に経営判断や意思決定が必要な場面で、思い込みに左右されることを防げます。
根拠を確認する
直感で判断しそうになったら一呼吸おき、「それはデータや論理に裏付けされた結論か?それともなんとなくの印象か?」と問い直すクセをつける。
ファクトチェックと第三者の視点
部下や同僚に意見を求めたり、客観的な数値データを確認したりして、思い込みを排除する。
意思決定プロセスの標準化
組織として重要な意思決定はチェックリストや投票制など定型のプロセスを設ける。複数人の評価を集めて平均をとるといった手法で個人の直感偏重を防ぐ。
経験からくる直感を完全になくしてしまうとスピード感や創造性が損なわれてしまいます。ヒューリスティックは使い方次第だと言えますので、直感に頼る場面と論理検証する場面のメリハリをつけることがポイントです。
例えば会議終了後に
今日の会議で
「根拠が曖昧なのになんとなく決めた」
「あの人が言うならそうなんだろうと決めた」
などは無かったろうか?
…のように振り返ってみるのは有効かもしれません。
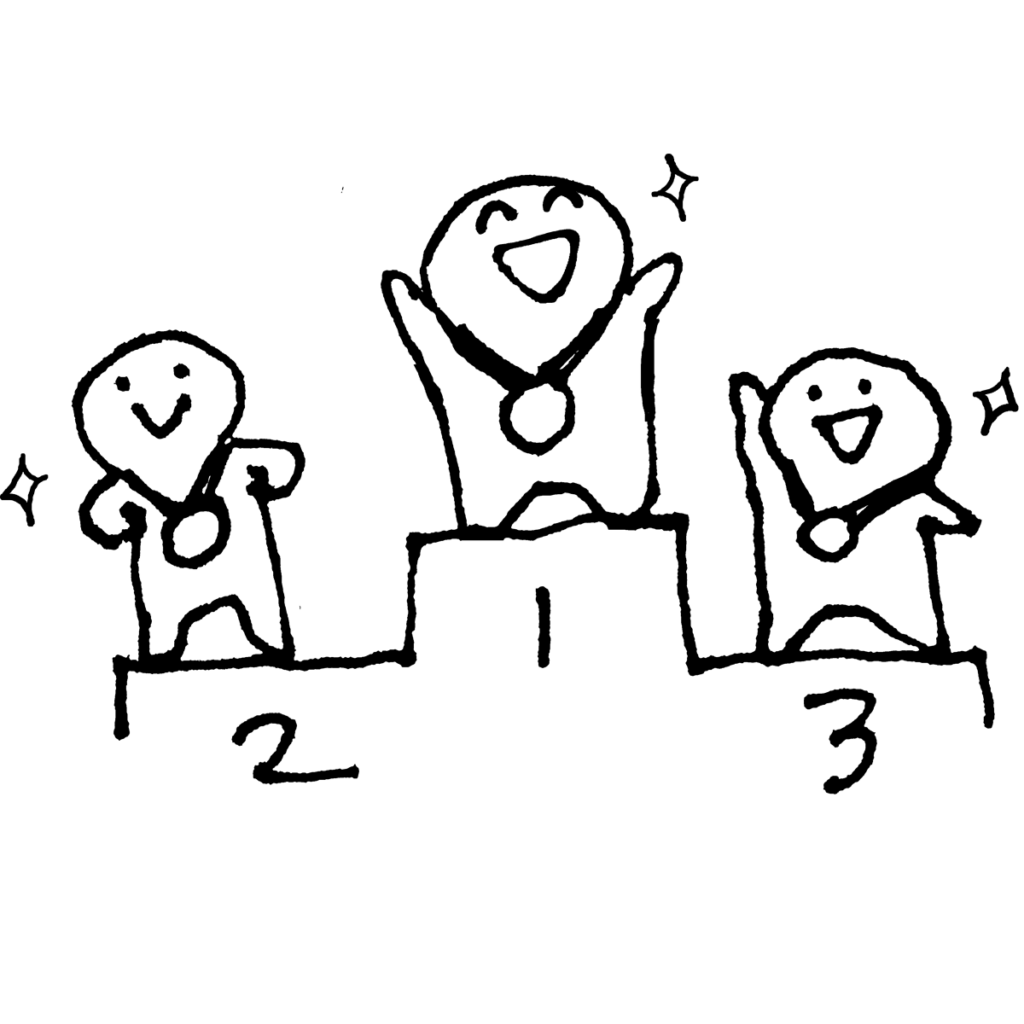
スポーツの採点では「○○の技が決まったら何点」と厳密に決めることで、採点が主観的になることを防いでいます。(それでも変な採点結果になることはありますが…)
他の心理効果・行動経済学理論とのつながり
前述の通り、行動経済学は経済学に心理学の要素を取り入れた、人間の非合理的な行動を分析する学問です。
ヒューリスティックは人間の非合理な判断パターンを理解するうえで、行動経済学の基本となる考え方です。ここではヒューリスティックに関連が深い心理効果や理論をまとめてみました。
フレーミング効果:
ヒューリスティックと同じくカーネマンらの研究で知られる現象で、伝え方(フレーム)次第で判断が変わってしまう効果です。例えば「90%の確率で成功する」と聞くのと「10%の確率で失敗する」と聞くのでは、同じ事実でも受ける印象が異なり意思決定に影響を与えます。
プロスペクト理論:
こちらも行動経済学の代表的理論で、「人は利益より損失を過大評価する」という傾向を示したものです。たとえば「1000円得する可能性」より「1000円失う可能性」のほうを強く意識して行動を選ぶ、といった人間心理をモデル化しています。
スキーマ:
ヒューリスティックの元になる思考の枠組みを「スキーマ」と呼びます。
以上のように、ヒューリスティックは多くの心理効果・バイアスの土台にある考え方です。マーケティングなど、様々なことに応用できる可能性を秘めています。
中小企業診断士 1次試験 平成27年「企業経営理論」第13問
ちなみに、出題頻度は低いものの、ヒューリスティックは中小企業診断士の試験にも登場します。ここまで読んで頂いた方は、ヒューリスティックについての理解がかなり進んでいると思いますので、是非挑戦してみてください。
ちなみに「企業経営理論」の問題文および選択肢は、必要以上に抽象的で分かりづらいのが特徴です。
人間や組織は、単純化や経験則に頼って意思決定をすることが多い。こうした単純化の方法は、ヒューリスティックと呼ばれ、時には論理的な意思決定に対してバイアスをかけてしまうこともある。このようなヒューリスティックやバイアスに関する記述として、最も適切なものはどれか。
ア ある選択肢に好意を抱いた人は、その選択肢を支持するような証拠を探し求め、データをそのように解釈する「後知恵バイアス hindsight bias」に陥りやすい。
イ 同じ業績であっても、上司のそばに席を置いている部下の方が、遠くの席の部下よりも高く評価される傾向がある場合には、「確証バイアス confirmationias」が作用している可能性が高い。
ウ 肯定的仮説検証現象が起きると、結果が出たあとにものごとを振り返った場合、他の結果も起こりえた可能性を無視してしまう「感情ヒューリスティックaffect heuristic」に陥りやすい。
エ 人間が意思決定する際に、「営業に適した人は社交性が必要だ」といったように、あらかじめ抱いている固定観念に合った特性を見いだそうとする「代表性ヒューリスティック representativeness heuristic」を利用する傾向がある。
オ 人間は天気の良い日には楽観的になって、株価が上昇したりするが、このような効果は「利用可能性ヒューリスティック available heuristic」に依拠する。
ヒント:
選択肢の中にはこの記事の中には無い「○○バイアス」・「○○ヒューリスティック」もありますが、正解の選択肢はこの記事内に解説があるものです。
まとめ:直感と思考を使い分け、賢い意思決定を
ヒューリスティックは、私たち人間が日常的に用いている、思考・判断のショートカットです。
そのおかげで効率よく意思決定できる反面、場合によっては認知バイアスという形で誤った結論に導かれることもあります。ビジネスパーソンにとって重要なのは、この両刃の剣を正しく理解しコントロールすることです。
- 日常業務では経験にもとづく勘を活かす
- 重要場面では一歩立ち止まって論理やデータを検証する
- マーケティングではヒューリスティックを上手に利用して顧客の心を動かす
- 経営判断では自らのヒューリスティックに囚われすぎないようにする
そうしたバランス感覚こそが、現代のビジネスに求められるスキルと言えるでしょう。皆さんも日々の意思決定プロセスを振り返り、ヒューリスティックと上手に付き合うヒントにしてみてください。
ということで、今回はここまで。
問題の解答
正解:エ