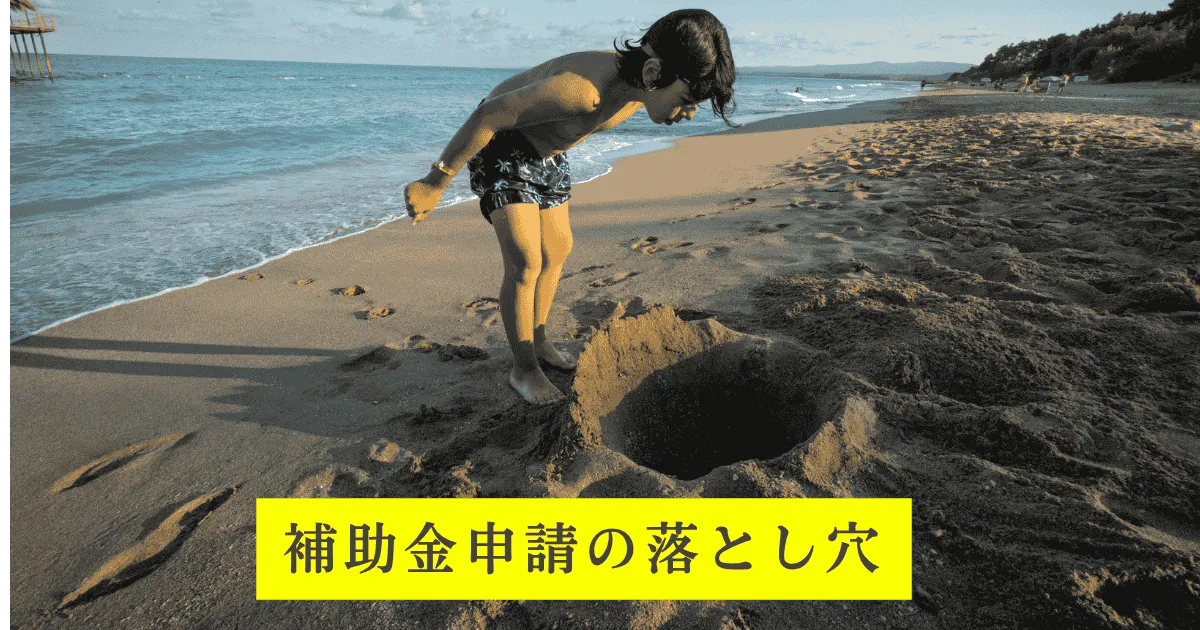※本ページにはアフィリエイト広告が含まれています。
こんにちは、柴山です。
前回記事にて補助金の基本的な仕組みをご紹介しました。
今回は補助金について最初に知っておくべき「誤解されやすいポイント」について解説します。ここを勘違いしたまま申請を進めると、後になって「こんなはずじゃなかった!」と後悔する羽目になります。
申請前にこれらのポイントを理解しておくことが、後悔しない補助金活用につながります。
勘違い①:補助金は「申請した全員がもらえるもの」ではない
補助金には予算があり、申請内容を審査のうえ「採択」された事業者のみが受け取れます。
そのため申請書類が要件を満たしていたとしても、以下のような理由で不採択となることもあります。
- 事業内容が補助金の目的に合っていない
- 自社の特徴(強みや課題)とマッチしていない
- 事業計画の実現性や完成度が低い
- 加点項目が不足している
- 応募他社の申請内容に対して見劣りする
補助金は応募すればもらえる制度ではなく、応募した中から優秀(有望)な事業者だけが獲得できる「競争型」の資金支援制度です。
このため応募した他社に対して見劣りする申請内容であれば、採択されることは難しくなります。

補助金を獲得するには、他の応募企業よりも優れた事業計画を立てる必要があります。
過去の補助金の採択率は?
参考までに最近の補助金の採択率をまとめてみました。
ものづくり補助金
19次 申請数5,336 採択数1,698 採択率約32% (採択発表日:令和7年7月28日)
20次 申請数2,453 採択数825 採択率約34% (採択発表日:令和7年10月27日)
省力化投資補助金
第1回 申請数1,809 採択数1,240 採択率約69% (採択発表日:令和7年6月16日)
第2回 申請数1,160 採択数707 採択率約61% (採択発表日:令和7年8月8日)
小規模事業者持続化補助金
16回 申請数7,371 採択数2,741 採択率約34% (採択発表日:令和6年8月8日)
17回 申請数23,365 採択数11,928 採択率約51% (採択発表日:令和7年9月26日)
このように、各補助金により採択率には大きな差が有ります。
このように補助金の現状は「とりあえず出せば採択される」というものではありません。
専門家のサポートを受ける場合であっても「社外に全部お任せ」で、
- 自社の強み・弱み
- 課題
- 市場環境や競合
などの分析がいい加減だと完成度が低い事業計画となり、採択は難しくなります。逆に言えば、他社に勝つためにはとことんまで事業計画書を見直し、説得力のあるものにする必要があります。
勘違い②:補助金は「投資した全額分もらえる」わけではない
補助金はあくまで「投資の一部を補助するもの」です。
多くの補助金では金額の上限に加えて、補助率が2/3や1/2に設定されており、残りは自己資金や借入金で負担する必要があります。
たとえば、1,000万円の設備を導入する場合:
- 補助率2/3 → 補助金額は最大666万円
- 残り334万円は自己資金や借入金で用意
さらに補助対象外の経費もあります。
例えば
小規模事業者持続化補助金の場合
◇販路拡大に使える補助金ですが、会社のPR広告に使うことは不可
⇒例えば新製品の販路拡大を目的として採択された補助金であれば、その新製品の販売に関わる広告にのみ使用できます。
◇ウエブサイトの為に使えるのは補助金交付申請額の4分の1(最大50万円)まで
⇒チラシや新聞、雑誌など他の広告媒体を組み合わせる必要があります。
ものづくり補助金の場合
◇設備投資には使えても、設置場所の整備工事や基礎工事に要する費用は対象外
◇試作品の原材料費には使えても、量産品(通常販売品)の原材料費は対象外
いずれの補助金も、申請する事業以外で使えてしまう費用(営業車や汎用PCの購入など)には使えません。これらを認めてしまうと際限が無くなり、それこそ税金の垂れ流しになってしまうからです。
補助金にはこういった制約があるため、資金計画を事前にしっかりと検討する必要があります。
勘違い③:補助金は「後払い」方式が基本
補助金は基本的に後払い(精算払い)方式です。
つまり、自社で先に設備を購入し、実績報告を行った後に補助金が振り込まれるという流れです。従って自己負担分も含めて、当面必要となる資金を金融機関からの借入などで調達する必要があります。
設備の購入等が終わり「申請した内容に沿ってこれだけの投資をしたので補助金●●●●万円をください」という段階では、銀行の振込履歴など、支払いを証明するものが必要です。このため購入していないのに補助金をもらう、または実際の投資額よりも多くもらう、といったことはできません。
さらに補助金を無事受け取るためには、いつまでに設備を導入して運用を開始しなければならないか、といったスケジュール上の制約もあります。
このため事業計画を立てる際には設備の試運転に必要な期間などもあらかじめ見込んでいく必要があります。
例:1億円の設備を補助金(補助率2分の1)を活用して購入したい企業の場合
| 投資金額 | 資金調達の内訳 | 備考 |
| 1億円 | 補助金5000万円※ | ※補助金は後払いの為、5000万円についても「つなぎ融資」または自己資金による調達がいったん必要。 |
| 自己資金2500万円 | ||
| 借入金2500万円 |
勘違い④:「返還義務」が発生することもある
原則として補助金は返済不要ですが、以下のような場合には返還を求められる可能性があります。
- 虚偽の申請をしていた(不正受給)
- 補助対象の事業を中止した
- 報告義務を怠った
- 補助金を目的外の事に使用した
- 指定された要件(賃上げ等)を達成できなかった
当然ながら①が最も悪質で、補助金の全額返還と加算金の支払いが課せられ、さらに事業者名の公表などが行われます。

不正受給はもちろんNG
勘違い⑤:全ての収益が自分のものになるとは限らない
「収益納付」という言葉を聞いたことがありますか?
これは補助事業によって直接収益(収入から経費を差し引いた純利益)が生じた場合、その利益が一定の基準(主に自己負担額)を超えた分について、交付された補助金を上限として国に返還する義務です。
収益納付は全ての補助金で義務付けられている訳ではないため、応募の際には補助金ごとに確認が必要です。
勘違い⑥:補助対象の設備等は勝手に処分できない
補助金で購入した設備を売却して利益を得るような行為はもちろんNGです。
補助金で購入した設備やソフトウェアなどの「補助対象資産」には、一定期間の使用義務や管理義務があります。
- 事前の承認を得ずに売却・廃棄するのはNG(5年~の処分制限期間における保有義務)
- 資産台帳での管理、報告義務あり
知らずに処分してしまうと、補助金の一部返還対象になる可能性もあるため、慎重な管理が求められます。なお災害時などやむを得ない場合には特例が認められています。

補助金で購入した設備を許可なく売却、監督省庁に怒られる経営者
まとめ
補助金は企業にとって魅力的な支援制度ですが、利用にあたっては注意事項が有ります。
- 補助金は「競争型」であり、採択される必要がある
- 投資額の全額が補助されるわけではない
- 原則後払いであり、資金繰りが重要
- 補助金の返還や収益納付をしなければならない場合がある
- 補助対象資産の管理にも注意が必要
これらを理解したうえで、計画的に活用することが成功のカギです。
次回は、補助金申請に不可欠な「事業計画書」の作り方について、実務の視点で解説します。
次回の記事はこちら 補助金を巡るスケジュールとは?