※本ページにはアフィリエイト広告が含まれています。
こんにちは、柴山です。
私(50代)が子どもの頃から売っているお菓子で「おにぎりせんべい」(製造元:株式会社マスヤ)というのがあります。

おにぎりせんべい
「おにぎりせんべい」にも商品ラインナップがいろいろあるようですが、ここでは一番昔からある、これを指すことにします。
調べてみたら販売エリアは静岡以西~九州だそうなので、関東にお住まいの方には馴染みが薄いかもしれません。
なんで唐突に「おにぎりせんべい」を取り上げるかというと、
こいつはマーケティング的に結構スゴイ商品なのではないか
と前から思っていたからです。
ということで今回は「おにぎりせんべい」の特徴を紹介しつつ、マーケティングの重要な概念であるカテゴリーエントリーポイント(CEP)とユニークセリングプロポジション(USP)の観点から、その魅力を探ってみました。
「おにぎりせんべい」はココがスゴイ!
「おにぎりせんべい」のスペック(?)は次の通りです。
- 形状が三角形
- きざみ海苔がふってある
- 子供でも食べやすい甘辛の味付け
- スナック感覚で食べられる軽い食感
- パッケージデザインも独特
こうして並べてみると、一つ一つの特徴は特別物凄い技術とかがある訳では無いように思えます。
(もちろん、そこに至るまでには開発された方々の創意工夫や苦労はあるにしても)
しかし「おにぎりせんべい」のネーミングの元に、これら特徴が合体したことで彼は覚醒したのです。
「おにぎりせんべい」のCEPとUSP
次に中小企業診断士らしく(?)、マーケティング用語の「CEP」と「USP」について解説します。
カテゴリーエントリーポイント(CEP)とは
カテゴリーエントリーポイント(CEP)とは、特定の製品カテゴリーを購入する際に、消費者が特定のブランドを思い浮かべるきっかけのことを指します。
例えば、人がコーヒーを飲みたい(買いたい)と考えるのは
・眠気を覚ましたい時
・一服して気持ちを切り替えたい時
・朝食時
などではないでしょうか?
このようなとき、家にいる人は家の中にあるコーヒーを飲むでしょう。一方、営業で外回りをしている時に頭をスッキリさせたいと思った人はコンビニに立ち寄り、そこから商品を選ぶことになります。
ユニークセリングプロポジション(USP)とは
ユニークセリングプロポジション(USP)とは、製品やサービスが競合他社と差別化される独自の強みや特徴を指します。
さきほどの例でいうとコンビニに立ち寄った人は、数あるコーヒーの中からパッケージデザインやキャッチコピー、または
あ、これ
人気YouTuberが「美味しいコーヒー第1位」
って言ってたやつだ
といった記憶を元に、特定のコーヒーを選択、購入することになります。もちろん、以前に飲んだら美味しかったという体験があれば、それが何よりも強いUSPとなります。
同じコーヒーでも、CEPによって選択は変わる
もう少し掘り下げて考えると、コンビニに来店した消費者が
移動中なのでフタができるのが欲しい!
と思っているなら、缶コーヒーではなくペットボトル入りのものが選択肢となります。その中で一番「買いたい!」と思わせるなんらかの強み(USP)があったものが選ばれるわけです。
一方で、
氷が入ってキンキンに冷えたコーヒーが飲みたい!
と思っている人にとっては、缶でもペットボトルでもなく、レジ横にあるドリップタイプのアイスコーヒーを選ぶことになります。

時と場合によって、飲みたいコーヒーは変わる!
考えてみれば当たり前ですが、消費者が「コーヒーを飲みたい」と思う気持ちは一見同じでも、どんな場面でコーヒーを求めているかによって選択肢が変わってくることになります。
ということで「おにぎりせんべい」のCEPとUSPは
前述の「おにぎりせんべい」の特徴をあらためて要約すると
和風の味付け + スナック菓子の軽い食感 + 独特なネーミングとパッケージ
といった感じになります。
それによって
あ~、緑茶を飲みながら煎餅食べたい!
手軽なビールのツマミが欲しい!
いずれの消費者(およびCEP)に対しても、応えることができます。また、昔ながらの硬い煎餅だと小さい子供や高齢者が食べるのには不安がありますが、「おにぎりせんべい」なら心配は無さそうです。
つまり「おにぎりせんべい」は「煎餅カテゴリー」「スナック菓子カテゴリー」の両方で消費者から選んでもらえるチャンスがあり、CEPを多く持っていることになります。
おまけに煎餅、スナック菓子のどちらを買いに来た消費者に対しても、味付け+パッケージ+ネーミング、加えてロングセラー商品であることによる知名度で訴求可能です。(これがUSP)
おおげさに言うと、「おにぎりせんべい」は「煎餅カテゴリー」、「スナック菓子カテゴリー」のどちらにも所属せず、独自カテゴリーを形成しているようなものです。
ちょっと変な例えですが、ヒト属の動物が人間(=現生人類)しかいないのに似ている感じがします。(こういうのを生物学では1属1種というらしいです)
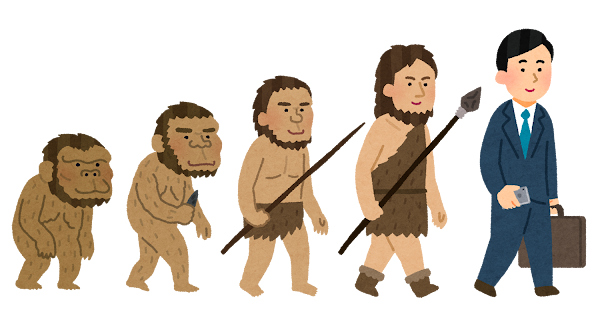
まめちしき:1属1種
ヒト科ヒト属にはヒト(ホモ・サピエンス=現生人類)しかいないらしいです。
ちなみにヒト科の中にはオランウータンやゴリラ、チンパンジーがいます。
「おにぎりせんべい」のライバルは?
「おにぎりせんべい」の競合として考えられるスナック菓子は
- カレーせんべい
- スナックえんどう
- カール
おそらくこの辺の「おやつにもなるし、つまみにもなるポテトチップス以外のやつら」ではないでしょうか。
なぜ「ポテチ以外」なのかと言えば、ポテチを買っている人は「どのポテチを買うか」に意識がいっているので、この辺のスナックは選択外、つまり競合ではない思います。(少なくとも私的には)

おにぎりせんべい と カレーせんべい
カレーせんべいは色々な種類が販売されているので、その中から自社の商品を消費者に選んでもらう必要があります。
これに対して「おにぎりせんべい」は1属1種なので、食べたい人にとっては、これ一択です。
これらと比較検討されたとしても、「おにぎりせんべい」の和風テイストは独特の存在感を放っていると思うのは私だけではないはずです。
| 煎餅・スナック・ポテトチップスの勢力図(?) | ||
| 煎餅カテゴリー (参入メーカー複数) | スナック菓子カテゴリー (参入メーカー複数) | 絶対王者ポテトチップス (参入メーカー複数) |
| 堅焼きせんべい | カレーせんべい | うすしお |
| 海苔せんべい | スナックえんどう | のり |
| ごませんべい など | カール など | コンソメ |
| おにぎりせんべい(1社のみ) | その他(季節限定品など) | |
※話がややこしくなるので、贈答用の高級煎餅、海老煎餅、甘いお菓子系はここではいったん除きます。
昭和40年代のマーケティング&経営判断
「おにぎりせんべい」は、その独自の特徴とマーケティング戦略により長年にわたり多くの人々に愛されてきました。
誕生したのは昭和44年(1969年)だそうで、普通に考えて今ほどマーケティングの概念は普及していなかったはずです。もしかしたら当時開発された方が「マーケティング」という言葉を知らなかった可能性すらあります。
それにも関わらず、他の商品との差別化をしっかりと果たし、50年以上経った現在まで生き残り続けているというのは凄いことだと思います。(当時からある煎餅だけでなく、現代のスナック菓子とも差別化できているので、なお凄い)
あと、社内で一風変わったアイデアが出されたとき、それを「ふざけたこと言うな」とか言って切り捨てずに、ちゃんと検討・採用に至った経営判断も素晴らしいのではないでしょうか。

社風によっては
三角形の煎餅とかダメに決まってるだろ!
「おにぎり」って、ふざけてんのか!!
…と、ボツになる可能性だってあったはずです。
(ちなみに私は製造元に知り合いがいるわけではないので、内情とかは全く知らずにこれを書いています)
最後に、中小企業診断士の「ヒアリングあるある」
事業計画書の作成などでヒアリングした際に、
いや~、
ウチの会社や商品に特にこれといった特徴とかないからね~
…みたいな返答が返ってくるのは「中小企業診断士あるある」ですが、中小企業・中堅企業だって立派に差別化できるという好例を「おにぎりせんべい」製造元の株式会社マスヤ様は示しているように思われます。
(調べているうちに2次試験・事例Ⅱの事例企業に向いているのではと思えてきました)
事業の規模に関係無く、カテゴリーエントリーポイント(CEP)とユニークセリングプロポジション(USP)を効果的に活用することで、他社との差別化を図ることは可能です。現場の声・お客様の声をきっちり追いかけていけば、差別化や商品開発のヒントはきっとあるでしょう。
ということで、今回はここまで。



