こんにちは、柴山です。
あの頃は大変だった…
あなたは創業の頃を振り返ります。
営業活動はもちろん、オフィスの準備から備品の買い出しまで、経営者である自分と少数のメンバーだけで何から何までやらなくてはいけなかった…。
大きな会社ではないものの、事業の安定した今では日常業務は部下たちが進めてくれる。セロテープが無くなったからと、自ら買いに行ったのはいつが最後だったけ…。
ほっとするのも束の間、次の「火種」はもうくすぶり始めています。
今回の記事はこんな方におすすめ
- 将来有望だと思っていた若手に最近辞められた
- 新卒採用は大変なので、しばらく止めようと思っている
- 少し前までやる気に燃えていたはずの若手社員が、やたらテンションが低い
…といった中小企業の経営者の方におすすめです。
中小企業の成長フェーズと「人材育成」のギャップ
ここで、中小企業の創業~事業が安定するまでの成長フェーズを簡単にまとめてみます。
創業期:何でも自分でやる「経営者と少数精鋭の時代」
* 創業メンバーが文字通り「一人何役」もこなし、雑務から戦略立案まですべてを担う時期。
* 役割分担は曖昧で、なんでも「出来る人がやればいい」という状態
事業規模拡大期:社員を雇い「分業と成長」が始まる
- 社員を雇用し、創業メンバーが雑務から解放され、より戦略的な業務に集中できるようになる。
- 新人が次々と入社し、既存社員は後輩指導を通じてステップアップする機会を得る。
事業安定期:新人が入ってこなくなる「成長停滞の危機」
- 市場環境の変化や経営判断により成長が減速し、新人が入社することが少なくなる。
こういった企業の成長段階により、人事組織の課題が表面化します。
事業安定期に顕在化する問題とは?
一般社員の焦燥感:
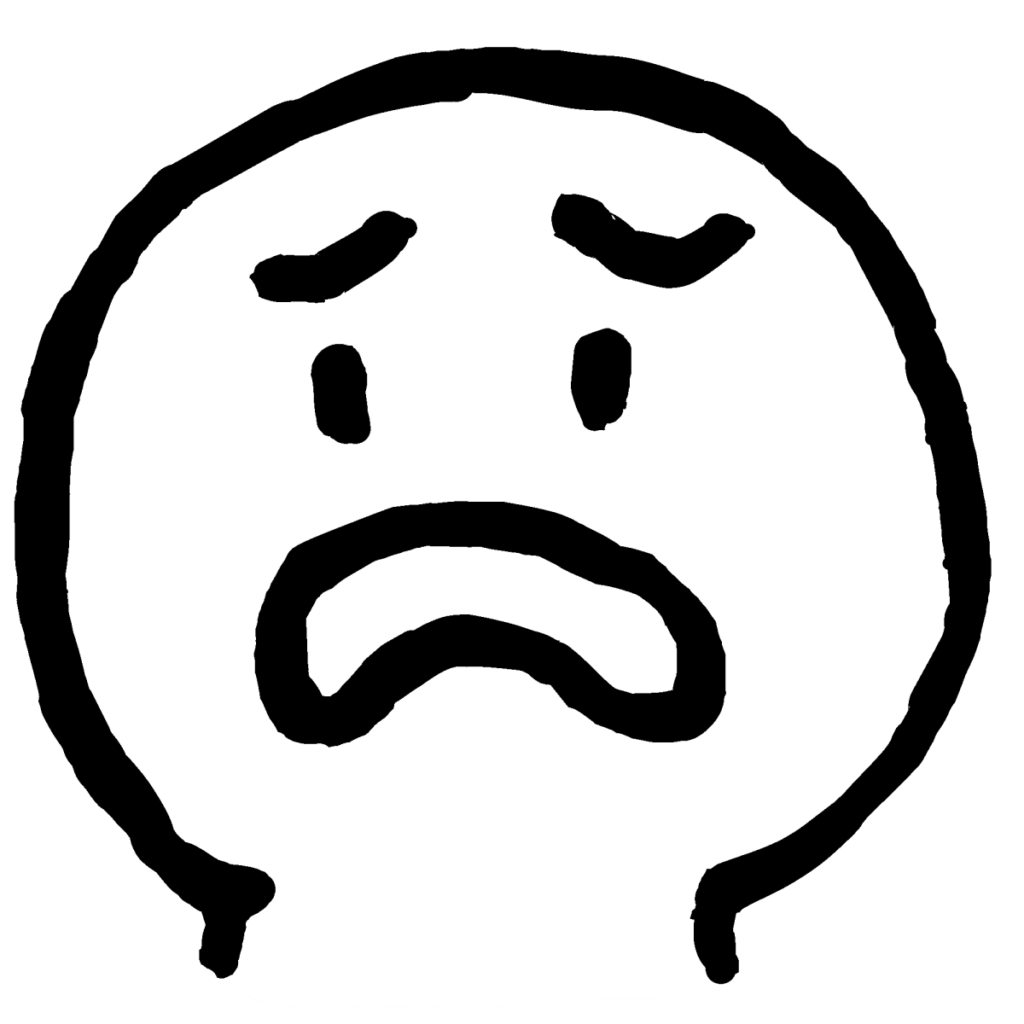
入社3年目のAさん
自分、いつまでこんな単純作業をやらなくちゃいけないんだろ…。
もっと色んな仕事をやってみたいのに。
20代の若手を始めとした社歴の浅い社員の中には
「自分の仕事を振る相手がいない」
「この先ずっと同じ仕事をするのか?」
といった危機感が芽生え始めます。
自身のキャリアパスが見えなくなるため、将来を真剣に考えている者ほど閉塞感を感じる可能性が高いです。
一方、経営陣(=創業メンバー)の認識は?
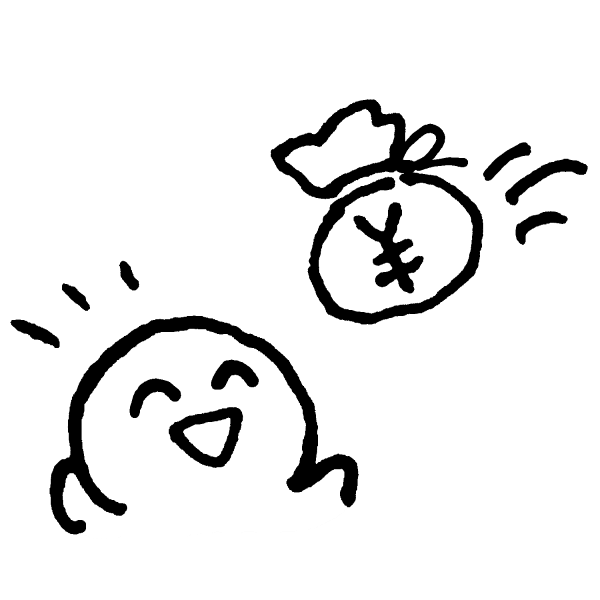
経営者
現状でも利益も出てるし、
少子高齢化で若者の採用は難しいらしいし
人件費も増やしたくないから当面はこのままでいっか!
あ!Bさん、お客様にお茶を!
- 自分には仕事を頼める部下がいる
- 全ての業務をこなした頃から時間が経ち、その時の気持ちを忘れている
こういった環境により、現役の若手社員の焦燥感がピンときません。
その結果、待つものは…
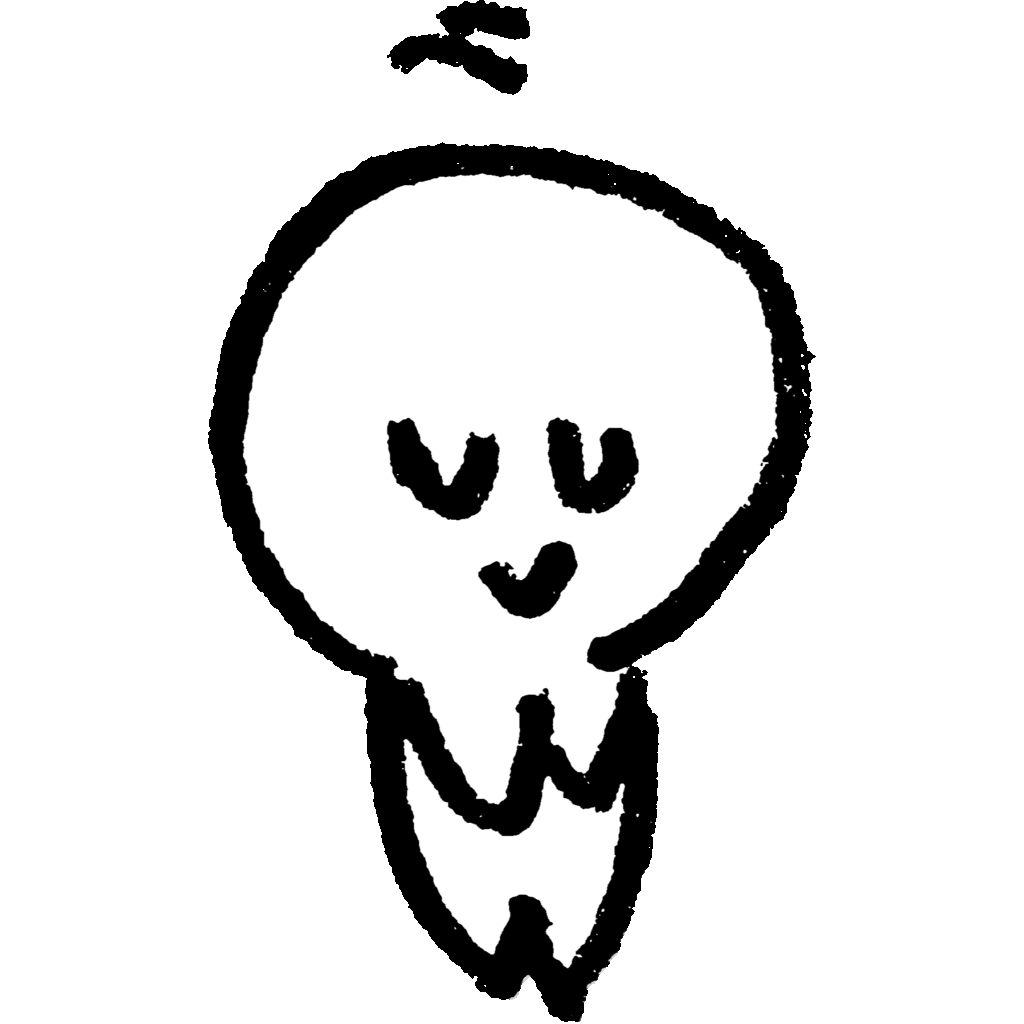
Aさんの決断
短い間でしたが、
お世話になりました。
新しい仕事にチャレンジする意欲を持っている者から次々に離職、という結果を招いてしまいます。
やむなくそこから求人を開始したとしても…
- 採用には時間とお金がかかる
- めでたく新しい人が入ったとしても、仕事を覚えてもらうのにはさらに時間がかかる
そもそも根本原因(この会社にいると将来が不安)が解決していないので、新たな退職者が出る可能性もあります。若手や中堅社員の退職が相次いでしまったら、会社の将来が危ぶまれるのは言うまでもありません。
安定期だからこそ若手社員の「ステップアップ環境」を考える
若手社員を現在の仕事からステップアップさせる方法はいくつか考えられます。
事業規模に見合った範囲内で、今後も定期的な新規採用を実施
若手社員にとっては教育係になることが成長の機会にもなります。若者人口の減少により新卒採用が難しくても、第2新卒の募集などの方法があります。
「人」以外の選択肢で成長機会を創る
業務の効率化と自動化:
AIツールやRPA導入で、若手社員がルーティンワークから解放され、より付加価値の高い業務に集中できる環境づくり
外部リソースの活用:
フリーランスへの業務委託も含めた外注により、社内スタッフはより高度な業務やプロジェクトマネジメントに専念できるようにする
ここまでは、若手社員の余力を作るためにできること(すべきこと)です。将来の不安を解消するために、やるべきことがまだ残っています。
社内でのキャリアパスの明確化
中小企業では独立した人事部が無いことが多いため、社員の定着を促すには経営陣の役割が重要です。
様々な選択肢を用意:
管理職への昇進、新規事業部への参加の他に、外部研修を受ける機会を与えて専門職としてのキャリアパスも描けるようにする。
役員への登用:
ジョブローテーションで全社の業務に理解を深めた上で役員に登用する。それまで同族会社だった企業で、役員になる道が開かれることが士気に与える影響は大きい。
まとめ:安定期こそ、攻めの人材戦略で未来を拓く
安定期に入った企業こそ、既存社員、特に若手社員のモチベーションを維持し、成長させるための「攻めの人材戦略」が不可欠です。
新規採用と並行して、業務効率化や外部連携など複合的な視点から、若手が「この会社には未来がある」と感じられる環境を作り出しましょう。
特に現経営者が自分一代で会社を終わらせるつもりがない場合、次の代で会社が発展できるか、それとも衰退するかはこれらの施策を実施するかどうかにかかっています。
ということで、今回はここまで。



