※本ページにはアフィリエイト広告が含まれています。
こんにちは、柴山です。
たとえば、あなたがひどい花粉症に悩まされているとします。
何か良い薬はないかな…
と、ネットで「花粉症 効く 薬」を検索したところ
「オススメの市販薬10選」
「2025年版 花粉症薬ランキング」
といった見出しが見つかりました。
さっそく期待に胸を膨らませて記事を読み始めましたが、どれも似たような内容ばかりです。いくつかの記事に目を通してから、あなたは思いました。
これって、
薬を実際に使ってみたわけじゃなく、
メーカーホームページなど
ネット上にある情報をまとめたでけでは?
こんな経験が、誰しもあるのではないでしょうか?
「体験なきレビュー記事」の正体とは?
検索するとやたら出てくる「○○〇〇(商品カテゴリー名)おすすめランキング」みたいな記事は、いわゆる「まとめサイト」で公開されていることが多いです。
「まとめサイト」は特定のテーマや話題の情報を収集・整理して提供するWebサイトで、「キュレーションサイト」とも呼ばれます。あくまで既出の情報を整理しているだけなので、独自の情報はほとんどありません。
それでも「今起きている出来事(戦争とか)について、短時間で概要を知りたい」といった人にとってはキュレーションサイトも有用だと思います。
ただ、特定の商品について実際に使ってみた意見・感想(=独自の情報、一次情報)を知りたい人にとって、検索結果の画面がこれらの記事で埋め尽くされてしまうのは迷惑な話ではないでしょうか?
こういった記事があふれている原因は、SEO対策とかアフィリエイトが関係しています。

私だったら、情報量は少なくても実際に使ってみた人の意見・感想が知りたいです。
【SEO対策】検索結果に上位表示させるための工夫
「SEO」(=Search Engine Optimization 検索エンジン最適化)というのは、検索された際に、少しでも上位表示されるようにするようにあれこれ工夫することです。なぜそんなことをするかといえば、上位表示された方が当然クリックしてもらえる(=記事を見てもらえる)可能性が高くなるからです。
最初の例でいくと、あなたが「花粉症 効く 薬」で検索した場合、Googleなどの検索エンジンは「どの記事が一番役立ちそうか?」とネット上の情報を探します。
それから検索結果が表示されるわけですが、どれを上位表示するかの判断基準の一つが「キーワードの数」です。
たとえば、検索エンジンは「花粉症の薬」という言葉がたくさん出てくる記事を「このサイトは花粉症の薬に関する情報が充実してる」と判断する傾向があります。
そのため、実際に花粉症の薬を試して
「くしゃみが減った」
「鼻づまりが改善した」
という具体的な体験が書かれた記事よりも、単に「花粉症の薬」「効く薬」という言葉が繰り返されているだけの記事のほうが、検索で上位に表示されてしまう事態が発生するわけです。
残念ながら実際に薬を試した人による記事は、そんなにたくさんの薬については書かれていないことが多いです。これは、「実際に試したものについてだけ書く」という制約があるので、どうしてもそうなります。
それに対して、その制約がない「まとめサイト」の記事の方が情報が充実していると検索エンジンにも判断されてしまうわけです。困ったもんです。
【アフィリエイト】商品リンクで収益を得る仕組み
もう一つがアフィリエイトとの関連です。
たとえば、あなたが「おすすめの花粉症薬10選」の記事を見て、その記事の中に薬が買える通販サイトへのリンクがあったら、そこからの流れで買ってしまうことも考えられます。
そうして買い物が成立すると記事を書いた人にお金が入る仕組み、それがアフィリエイトです。
なのでアフィリエイトで儲けたい人はできるだけ多くの商品を紹介して、記事にリンクを貼ります。その方がいろんな人がクリックしてくれて、買ってもらえる可能性が高いからです。
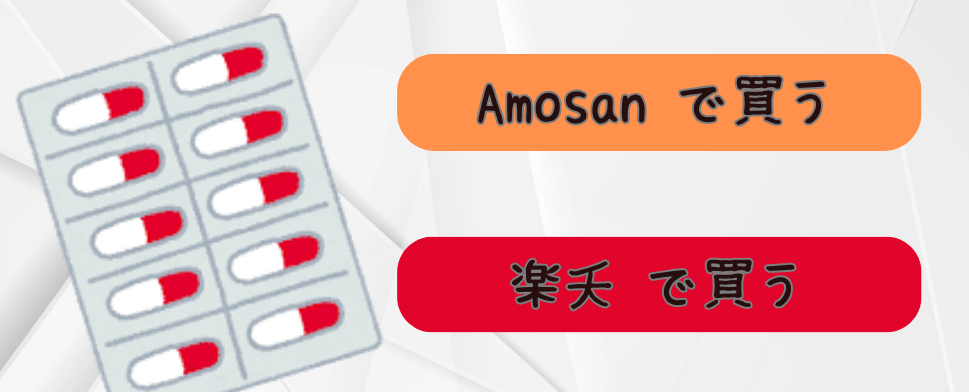
アフィリエイトリンクの雑なイメージ。
ちなみに別にアフィリエイトの仕組み自体が悪いという訳ではありません。
【WEBマーケティング】記事量を増やして目立つ作戦
記事単体でのSEO対策としてキーワードの数を増やすように、サイト全体のSEO対策としては「記事の数を増やす」ことが行われます。
たとえば、あるまとめサイトが「おすすめ冷蔵庫5選」という記事を書いたら、競合のサイトは「おすすめ冷蔵庫15選」とか「最新冷蔵庫20選」といった記事を作ったりします。さらに冷蔵庫についての記事の本数自体を増やしたりもします。情報量が多いと検索エンジンは「詳しいサイトだ」と評価する傾向があるからです。
とはいえ、これらは読む人にとって有効な情報量が増えたわけではありません。
検索サービスも、より良い検索結果を目指して頑張っている
ただ、最近はGoogleも頑張っています。
Googleは「ユーザーの役に立つ記事をちゃんと評価しよう」という方針で、検索エンジンの仕組みに対して改良に次ぐ改良を重ねています。
なので最近では数年前に比べて、実際に使った人の体験談が詳しく書かれた記事、またはその分野での専門知識がある方が書いた記事が上位に出るように変わってきています。
私の体感的には3~4年くらい前は本当に酷く、検索結果に上位表示されるのが役に立たない「まとめサイト」の記事ばかりということが頻発しました。個人的に「Google検索終わったかも」などと思ったりしたものです。
現在(2025年3月)では状況はかなり改善されていて、例えば「花粉症 効く 薬」で検索すると医療関係者の方が書いた、成分ごとの薬効などを解説した記事がちゃんと上位表示されるようです。
Googleの掲げる、E-E-A-Tとは?
2022年にGoogleが発表したガイドラインでは「E-E-A-T」の4つの要素が評価に導入されているとのことです。
- E:Experience(経験)
- E:Expertise(専門性)
- A:Authoritativeness(権威性)
- T:Trustworthiness(信頼性)
花粉症の薬の例だと、ドクターや薬剤師など世間的に専門家とみなされる方が実名を出し、根拠となる公的な情報を交えつつ、さらに自分や周囲の人が実際に使ってみた体験など独自の情報も加えて説明すれば最強の情報源ということになります。
逆に、誰とも分からない人が匿名で製薬会社のWEBサイトにある内容をコピペしただけでは良い記事だと判定されません。
普通に考えてそういった記事は、読む人から「こんな記事、読むだけ時間の無駄だった」と思われるであろうことは容易に想像がつくと思います。なおGoogleでは特に、医療やお金に関する記事は特に厳しくチェックされるとのことです。
信頼できる情報にたどり着くためには?
20代の人に聞いたりすると、GoogleではなくインスタグラムなどSNSで欲しい商品について情報収集したりしているようです。
またYouTubeでも、いろんな人がいろんな商品のレビュー動画をアップしています。たとえば自動車のニューモデルが発表されると、多数の試乗動画が一斉にアップされたりします。ただ、その内容にはメーカーに対する忖度があるのかないのか微妙なところだと思います。

自動車ジャーナリストやYouTuberの方たちは、メーカーに忖度し過ぎると視聴者・読者から信頼されず、本音で話し過ぎるとメーカーからうるさがられそうなので、表現には結構気を使っているはずです。
他にクチコミサイトがあります。商品によって、ほとんどの人が褒めているものもあれば、意見が割れるものもあり、最終的には自分で買って試してみるしかありません。
とはいえ、
こいつだけは明らかにダメそう
みたいな商品を選択肢から外せるだけでも下調べをすることの意味はあるはずです。
今後は情報を発信する側からSEOを考えてみる
ここまでを踏まえて、今度は自分がブログなどで情報を発信する場合を考えてみます。
そうすると、
- 実名を出し
- 肩書や所有資格、経歴で自分がその分野の専門知識があることを示し
- 公的データなど裏付けも示しつつ
- 実体験など他にはない独自の情報を掲載し
- 検索に使われそうなキーワードを踏まえた記事を作る
(とくにタイトルや見出しにキーワードに反映)
ここまですれば、検索された場合に上位表示されやすくなるということが分かります。ちなみに、ある程度は記事のボリューム(文字数)があった方が良いようです。(2000文字以上は書くべしとか言われたりします)
やってはいけないこともチェック
そうすると人によっては
だったら記事の中にキーワードをとにかくたくさん入れればいいじゃん
とか
読者に見えないような白文字で、画面の余白部分をキーワードで埋め尽くせばいいじゃん
みたいな、良からぬことを思いつくかもしれません。
こういったことは「ブラックハットSEO」と呼ばれており、Googleに発覚すると検索順位が下がる、そもそも検索結果で表示自体されなくなるなどのペナルティの対象になる場合があります。なのでキーワードを過剰に盛り込むことは厳禁です。
その他のブラックハットSEOとしては、お金を出して外部サイトからリンクをはってもらうのもNGです。WEBの世界では、外部からリンクをたくさん貼ってもらえると有力なサイトとみなされる傾向があります。それを悪用して「リンクを買う」ような行為は御法度ということです。
結局、SEOで一番大事なことは?
SEO対策として「やって良いこと・悪いこと」の知識はあった方が良いのは間違いないと思います。
ただ、あまりテクニック的なことを意識するよりも、まずは読者にとって役に立つ記事作りを心掛けることの方が重要です。とりあえず私は自分で書く記事について「読むだけ時間のムダだった」と読者の方々に思われないように、頑張っていこうと思います。
ということで、今回はここまで。



