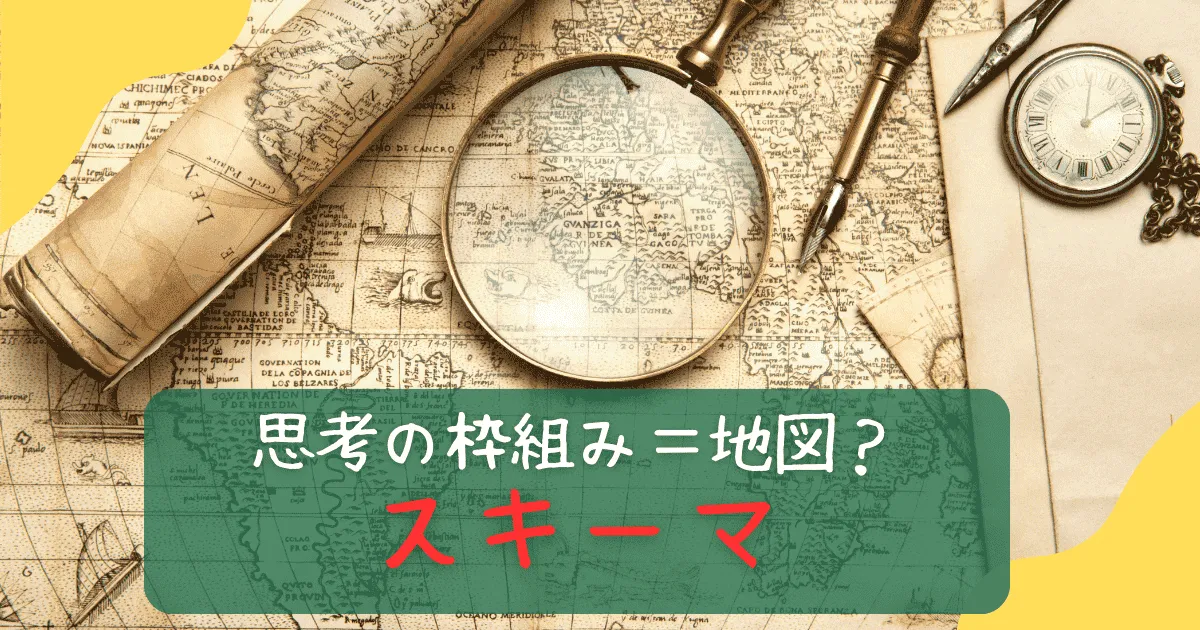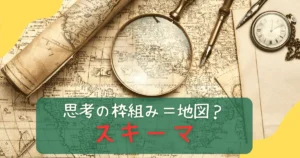※本ページにはアフィリエイト広告が含まれています。
こんにちは、柴山です。
以前の記事の中で「A社の出社ルール」にまつわる、以下のエピソードをご紹介しました。
台風でも、大雪でも、とにかく定時に出社するのが当たり前のA社。
大型台風の接近がニュースで報じられたある日、新入社員がぽつりとつぶやきました。
「どうせ明日なんて出社しても仕事にならないんだから、休みにした方がよくないですか?」
古株社員は激怒して怒鳴りました。
「社会人とはそういうもんじゃないんだ!お前はなにも分かってない!!」
社内がしんと静まり返った中で、実は多くの社員が内心では新入社員の意見にうなずいていました。
元の記事はこちらです。
このエピソードは、「コンフリクト(対立)」として見ることもできますが、同時に「スキーマ」(schema)という思考の枠組みのズレの問題と見ることも可能です。
──「とにかく出社するのが会社員の務め」という古株社員のスキーマ
──「成果につながらない稼働など無意味」という新入社員のスキーマ
このような、お互いの常識の食い違いこそが、組織や家庭、社会の中での摩擦の原因になることがあります。
本記事では、「スキーマ=無意識の思考テンプレート」がどのように対話や判断を左右しているのかを探っていきます。
認知スキーマとは何か?
スキーマとは、
- IT分野ではデータベースの構造を定義する用語として、
- 心理学では思考の枠組みや知識の構造を指す用語として
それぞれ使われています。
この記事では主に私たちが物事を理解したり判断したりするときに使う、無意識の思考の枠組みという意味で、正確には「認知スキーマ」を指します。「テンプレート」「自動思考のクセ」「常識のようなもの」と言い換えてもよいでしょう。
- 商談といえばスーツ
(ビジネスカジュアルなどもってのほか!) - この業界では、こうするのが常識
- 我が社では、昔からこうだった
これらは一見「当たり前」に聞こえますが、すべてが過去の経験や文化、環境から自動的に形成されたスキーマです。
なぜスキーマは生まれるのか?
スキーマは以前の記事で紹介した「ヒューリスティック」と並んで、本来は人間が生き残るのに必要な仕組みです。
例:
湯気が出ているもの ⇒原理は分からないけど熱いに決まってる
こう決めつけることにより、湯気が出ているものは慎重に対応することで火傷を回避することができます。
毎回すべてをゼロから判断していたら時間もエネルギーも足りません。そこで、こんな風に「○○とは、こういうものだ」と思考をパターン化することで、危険を回避しやすくするのです。
そのために頭の中に一種の型として仕込まれた思考の枠、それがスキーマです。
なお「ヒューリスティック」については、こちらの記事をご覧ください。
心理学ではどう扱われている?
心理学では、ジャン・ピアジェが「スキーマ=知識の構造」として概念化し、人の認知発達や学習、行動パターンを説明する際の基本要素とされています。
ビジネスや組織論の世界でも、無意識のスキーマが対話や意思決定に与える影響は大きく、“見えない障害物”として注目されつつあります。
スキーマがもたらす誤解と対立
台風の日に出社するかどうか──
意見の食い違いがあったのは、合理性 vs. 忠誠心の対立にも見えましたが、本質的には、「社会人とはこうあるべき」という考えのスキーマの違いです。
- 古株社員のスキーマ:「何があっても出社する」という姿勢を示すのが社会人
- 新入社員のスキーマ:「やる気アピール」ではなく成果を残すのが社会人
これが、表面的には「言葉のズレ」でもありながら、深いところでは「それぞれの正しさ」の根っこそのものが異なる状態。
──いわば別の地図を使って会話している状態なのです。
よくある「スキーマのズレ」実例
以下のようなやりとりも、実はスキーマの衝突によって起こっています。
上司と部下のケース
部下:「この資料、ちょっと改善したいので納期を1日延ばしていいですか?」
上司:「いやいや、納期を守るのがビジネスマンの基本だろ!」
→ 上司のスキーマ:信頼=納期を守ること
→ 部下のスキーマ:成果=品質の高さ
親子のケース
娘(30代):「子どもが泣くのは当たり前だから、できるだけ見守るようにしてる」
母(60代):「あんたの甘やかしが原因よ。3歳までは厳しくしつけるべき!」
→ 母のスキーマ:しつけ=親の責任と厳しさ
→ 娘のスキーマ:しつけ=子どもであっても人格を尊重
部門間のケース(社内あるある)
営業部門:「これ、お得様からの注文だから最優先で!!」
生産管理:「一度立てた生産計画に割り込むのはやめて!」
→ 営業のスキーマ:顧客第一/売上が正義
→ 生産管理のスキーマ:計画通りに生産/品質保持/コスト削減
ちなみに製造業における部門間のすれ違いについては、こちらもご覧ください。
(中小企業診断士の受験生向き記事です)
すれ違いは「前提のズレ」から生まれる
上記のすれ違いは、そもそも物事の捉え方・優先順位が違うところから生じています。
そしてこのズレが、
「どうせあの人は分かってくれない」
「話してもムダ」
という感情にまで発展すると、信頼や協力が損なわれ、チームや組織のパフォーマンス全体が下がっていくのです。
大切なのは、「相手の正しさ」を一旦理解しようとすること
上に書いたような対立は、多くの場合どちらかが一方的に間違っているというわけではありません。それぞれが異なる前提、異なる枠組みで、別々の「正解」に辿り着いた結果です。
このため双方が
「自分が正しくて、相手が間違っている」
と思っているうちは対立の構図はずっと続きます。
1つの課題について、複数のスキーマが同時に存在することに気づけるかどうかが、対立を乗り越えるカギです。
スキーマは創造性を阻害する
ここで再び、冒頭に出てきたA社の登場です。
とある会議の場にて
部長:「…と、いうことで、現状を変えるためには今までにないアイデアが必要だ。各自、何でもいいから思いついたことを発言してくれ」
社員一同:「・・・・・」
部長:「なんだぁ、君ら?アイデアの1つも出せないのか!?」(怒)
新入社員:「では部長。私が思うに、かくかくしかじかで…」
部長:「ふざけるな!そんなやり方で上手くいくと本気で思っているのか!!??」(激怒)
こんな感じで、創造的になることが必要な場面でも、従来の考えから抜け出せないということが普通に起こります。
ちなみに既にお分かりかと思いますが
部長が考えている
「そんなやり方で上手くいくか!」
はもちろん、
社員一同が心の中で考えている
「部長は、どうせ我々の意見なんて聞かない」
というのもスキーマです。
こうなってしまうのは、自分たちを縛っているスキーマの自覚が無いまま、その枠の中の思考しかできていないせいだといえます。
創造性を取り戻す第一歩は、「自分の枠」に気づくこと
創造的な提案や変化の芽を摘んでしまわないために大切なことは
「これまで当たり前だと思っていることは、実は当たり前ではないのかも」
と一度立ち止まってみることです。
そこで、こうした思考の枠組みからどうやって自由になるのかを考えていきます。
スキーマを乗り越えるためのヒント
先に書いたようにスキーマ自体が悪なのではありません。問題は、それを「唯一の正解」と決めつけてしまうことです。ここでは、前提を疑うことによりスキーマから自由になる方法を考えてみます。
A社が三度目の登場です。
部長:「最近、営業部では事務処理のミスが多い。早急に対策を考えるように!」
課長:「で、では、ダブルチェック、またはトリプルチェックして、それでも足りなければ…」
部長:「本当にそれで改善できるのか?以前みたいに出来るのか!?」
ここで疑うべき前提
そもそも「最近の営業部では事務処理のミスが多い」は本当か?
⇩
隠れていた事実
実は営業部では以前からミスが多かったものの、部長も課長も事務処理に無関心で放置されていた。それを経理のKさんがこっそり修正してから社長に提出してくれていた。今回、Kさんが退職したタイミングで問題が発覚しただけで、営業部のやっていることは以前と変わらない。
あくまで一つの例ですが、何かの問題に対して
「さあ、みんなで考えよう!」
と盛り上がる前に、様々な角度から前提条件を疑ってみることが役立つことがあります。
自分のスキーマに気づく──「メタ認知」の活用
メタ認知とは、「自分がどう考えているかを客観視する力」です。自分自身の考えを一歩引いた視点で検証する、と言っても良いかもしれません。
たとえば会議中に、
「え、それは常識的におかしいだろ」
と思った瞬間に、
「そもそも常識ってなんだっけ?」
と疑ってみる。
他人の意見を否定する前に、
「この意見を間違いだと思う根拠はなに?それって自分だけの思い込みでは?」
と、立ち止まってほんの数秒でも考えてみることが有効です。
メタ認知について詳しくはこちらの記事をどうぞ。

他人のスキーマを尊重する──「違っていて当然」の姿勢
メタ認知を向上させる上で、自分の考えの前提を疑うことに加えて、相手の考えの前提に注意を払うことにも意味があります。
おすすめの質問:
- 「そう思った背景にはどんな経験がありますか?」
- 「あなたにとっての“普通”ってどんな感じですか?」
こうした問いかけは、「正しさの衝突」から「価値観のすり合わせ」へと会話を進化させます。
NLPの視点──「地図」は人によって違う
NLP(神経言語プログラミング)はコーチングなどにも応用される理論です。
NLPでは、
「人は現実そのものではなく、自分なりに解釈された地図をもとに行動している」
と考えます。
つまり、同じ職場の仲間ではあっても、元々異なる「地図」を持った他人同士ということになります。そのことへの理解が深まれば、「地図」をすり合わせる努力の必要性も浸透するはずです。
上司がコミュニケーションを面倒くさがり、「察して欲しい」に逃げるようでは進歩はありません。
心理的安全性がある場所では、スキーマは柔らかくなる
人は「否定されない」という安心感があるときに、自由な思考がしやすくなります。
そのためには、
- 意見を途中で遮らない
- 反論、否定の前にいったん受け止める
- 立場や年齢に関係なくアイデアを歓迎する
といった、異論を歓迎する空気が重要です。
社員が心をすり減らさなくて良い職場については「感情労働」の記事をご覧ください。
まとめ──「当たり前」を疑うことから始まる
「話が通じない」
「理解してもらえない」
そんなとき、相手の問題だと思ってしまいがちです。
ですが、そのすれ違いの原因は、お互いの中にある“スキーマ”──思考と認知の枠組みが原因かもしれません。
スキーマは私たちの判断を効率化してくれる一方で、アイデア創造や他者との対話の妨げにもなります。
そこで大切なのは相手を論破するために死力を尽くす…のではなく
「なぜ自分はそう感じるのか」
「相手はどんな前提で考えているのか」
と、メタ認知を働かせることです。
事例のA社のようにならないために、お互いの「地図」のすり合わせに挑戦してみてください。
ということで、今回はここまで。