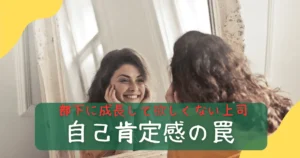※本ページにはアフィリエイト広告が含まれています。
こんにちは、柴山です。
もしも、
資格取得を目指している人が、職場で上司に言われがちなセリフ あるあるランキング
が発表されたら、間違いなく上位に食い込んでくるのが

そんな資格とっても意味ないだろ!!
…みたいなセリフだと思います。
ひょっとしたら、これがぶっちぎりの1位かもしれません。
誰から言われてもモチベーションは下がるセリフですが、SNS投稿などでも職場の上司から言われて腹が立った、または落ち込んだ、といった声が目立つ気がします。
せっかく頑張っている人に対して何故こんなことを言ってしまうのか、今回は他人の成長を喜べない心理について「自己肯定感」をキーワードにして考えてみます。
今回記事はこんな方におすすめ
- まさに今、「そんな資格とっても意味ないだろ」と言われてムカついている
- 自己肯定感を下げてくる上司の元で働いている
- 自分はそういう上司にはなりたくない
- そういう人たちと、どう向き合えばいいか知りたい
- 立場を問わず、わざわざ人のモチベーションを下げる発言ばかりする人の真意を知りたい
- もしかしたら「私が自己肯定感が低いのは他人の影響では?」と疑っている
自己肯定感:「自分には価値がある」と思える感覚

弱い犬ほど、よく吠える
ということわざがあります。
強い犬は自分のテリトリーに誰かが侵入してきても撃退する自信があるので、そうそう吠えません。反対に弱い犬は、いざとなった時の戦闘能力に自信が無いので、そうならないように敵の接近を必死で食い止める必要があります。
話が飛躍しているように思えるかもしれませんが、自己肯定感についても似たようなことが言えるのではないか、と私は考えています。
自己肯定感=これでいいのだ、と思える感覚
そもそも、自己肯定感という概念を提唱したのは高垣忠一郎さんという方です。
自己肯定感が高い人、というと容姿や収入などに優れた、いわゆる「ハイスペック」な人を連想する方も多いかもしれません。が、この方が特に子供たちに伝えたかったのは、ハイスペック人間を目指せということではなく、「自分が自分であって大丈夫」という感覚だそうです。
私なりに少し表現を変えると、
自分という人間は完璧には程遠いけど、
まあまあ頑張ってるし、これでいっか!
…みたいな感じで、自分を受け入れる力(自己受容)ということではないかと思います。
そういう意味では
これでいいのだ!
という、「天才バカボン」のセリフはなかなかに奥深いものがあります。
(世代的に知らない方は調べてみてください)
 | 何があっても「大丈夫。」と思えるようになる自己肯定感の教科書 [ 中島 輝 ] 価格:1430円 |
自己肯定感が低い上司 = 自信が無い上司 = 弱い犬?
自己肯定感が高い人の反対に、ありのままの自分を受け入れることができていない人は常に不安の中を生きていることになります。
このため自分を脅かされるような事態には、まるで「弱い犬」のように、自分を守るために過剰に反応してしまいます。
たとえば、
- 他人の成功
- 他人の成長(特に現時点では自分より下の立場の人の成長)
などにより、自分という存在そのもの、自分の立場が脅かされるように受け取ります。こういう方にとっては部下の成長などもっての他です。また酷い場合は自分の子供が成長して独自の意見を持つようになることすら許せないようです。
ちなみに私の過去の経験では、自分の部下が役員に褒められているのを見ると機嫌が悪くなる、という人がいました。
「悔しい」と「劣等感」の違い
たいていの場合、何かの分野で優れた能力を持っていても、より優れた人が世の中にたくさんいるのが現実です。
自己肯定感の高い・低い、また能力の優劣を問わず、人生を無双状態で過ごせる人はほとんどいません。ただ、自己肯定感が高い人と低い人では、自分より優れている人に対する反応が違うようです。
「悔しい」という感情は…
競争で負けた際に生じる普通の感情です。自分の敗北、相手の能力を認めつつも「次は自分も頑張ろう」という向上心やモチベーションに繋がります。自己肯定感が高い場合、この感情は成長の糧となり得ます。
一方、「劣等感」は…
優れた他人を見ると「自分には価値がない」と、自分の存在全体に否定的になってしまいます。自己肯定感が低い場合に現れる感情です。
部下が自分には無い知識やスキルを持っていたとしても、
- 悔しさをバネに自分も勉強する
- 部下の強みが活かせるような業務を振る
など、上司として前向きに捉える方法がいくらでもあります。
ところが自己肯定感の低い上司の場合、そういった考え方が出来ずに劣等感を感じてしまいがちです。
防衛機制:自分を守るために他人を軽蔑したい
自己肯定感の低い人の心の中で起こっていることを、もう少し掘り下げてみます。
超有名な心理学者、フロイトが提唱した概念の中に防衛機制というものがあり、それによると人には不安や葛藤、受け入れがたい感情や欲求から自分自身を守るために、無意識のうちに働く心のメカニズムがあるそうです。
その他にも、アドラー心理学でも「優越コンプレックス」といって、自信の無さを隠すため他人より優れていることを示そうとする心の働きがあるそうです。
これを読んで普通の人は
部下の成長や資格取得が
なんで「受け入れがたい感情」になるの?
むしろ、そこは祝福すべきところでは?
と、思うはずです。
たとえ心の中では「資格よりも実務が大事!」と思っていたとしても、まともな上司であれば努力している部下に対してわざわざモチベーションを下げる発言などしないと思います。
というか、そもそも部下のモチベーションが上がるよう配慮することは、本来は上司の給料のうちに含まれているはずです。
ところが自己肯定感が低い人の場合だと、他者の成功・成長によって自分の「無能さ」や「価値の低さ」が突き付けられたように感じてしまいます。
そこで部下が資格取得のために勉強中と聞くと…
自分の価値が低いなんて思いたくない…
そうだ、そんな資格なんて大したことないし
実務と資格はまた別だ。
そう考えれば自分の方が職場での地位は上だし
エラいことには変わりないんだ!
といった感じで、自尊心を保つためにその資格を否定する方向に思考が働きます。資格取得に限らず、部下が営業成績を上げた、優れた企画を出した、などの場合も似たような感じです。
ところで上に書いたように、防衛機制というのは無意識で働く心のメカニズムです。なので、部下の努力に否定的な発言をする上司は、自分では「そんな資格たいしたことない」と意識の上では本気で思っている可能性が高いです。あるいは本気でそう思おうとしている、といった方が正確かもしれませんが。
それとは別のタイプとして、自分が部下の成長を快く思っていないことを自覚した上で、意図的にモチベーションを下げる言葉を言ってくる上司もいるかもしれません。その場合はわざわざ自己肯定感の考え方を持ち出すまでもなく、一種のパワハラと考えるのが適当です。
努力するにも自己肯定感が必要という残酷な事実
そういう(自己肯定感の低い)上司の特徴として、人を褒めることよりダメ出しをする方が圧倒的に多いことがあります。
「褒める=相手の優れている点を認める」ということなので
褒めてなんかやるもんか!
などと、無意識のうちに考えているはずです。
そこで「そんなに部下のことを脅威に思うのであれば、自分も努力すればいいのに」という考え方もありますが、残念ながらなかなかそうはなりません。
努力を始めるには、あるいは継続するには、「自分ならきっとなんとかなる」という気持ちが必要です。
ところが自己肯定感が低い人は
- 「どうせ自分なんて勉強を続けられない」
- 「受かるわけない」
- 「途中で飽きて投げ出すに決まってる」
…などと考えてしまう為、そもそもスタートすることができません。
これは例えるなら、宝くじを買うためには「もしかしたら当たるかも」という期待がわずかであっても必要であることに似ています。本気で絶対当たらないと確信している人は、最初から宝くじを買ったりしません。
そういうわけで自己肯定感が低い人は、自分を信じてなにか新しいことにチャレンジする気にもなりにくく、だからこそ他人の努力を脅威に感じてしまう心理から抜け出せない、という二重苦のような状態に置かれていると言えます。
自己肯定感が低い上司=性格が悪い と決めつけてはいけない
こういった上司のもとで働くと、部下側も次第に
- 何をしてもダメ出しばかりで認めらることがない
- 提案をしても「前例がない」などと却下される
- 結果として、目立つことはしないのが一番いいと思えてくる
…のように無気力となり、自己肯定感が低下していく可能性があります。
ここから時系列を遡って考えると、今の上司も過去に自己肯定感が低い上司によってやる気を削がれたのでは、という仮説も成り立ちます。あるいは、一度も褒められることなくダメ出しばかりされるような家庭環境だったのかもしれません。
人間の心は複雑で、ほとんどの人は100%の善人でもなければ、100%の悪人でもないと思います。
部下の資格取得に対して「そんな資格は無意味」と言ってくる上司でも、家族が病気の際は「今日は早く帰っていいぞ」と言ってくれる人かもしれません。
「そんな資格は無意味」発言によって腹が立つのは間違いないですが、だからといって相手の人格全てを否定してはいけないと思います。
自己肯定感が低い上司と、どう付き合うか
書店やコンビニで「心理学を使って他人の心を操るテクニック」みたいな本が並んでいることがあります。営業やマーケティングにおいて心理学の考え方が有効な場合もあるかもしれませんが、私は心理学で他人の心を操ることはできないし、他人を変えることもできないと思っています。
ですので、ここまで書いてきた「自己肯定感が低い上司」と同じ職場にいて、相手をなんとか変えたいと思っている人に向けて言えることは、
とりあえず、その人を変えようとか思うのはやめましょう
ということです。
せっかくここまで期待して読んできたのに時間を返せ!
と言われる可能性もありますが、冷静に考えてみてください。
当人が望んでいる訳でも無いのに、その人格や考え方を変えてやろうというのは、他人を洗脳したり支配するという考えに通じており、相手の人格を無視しています。
考え方としては…
- 自分の力で相手を変えようとしない
- 相手も自己肯定感が低いことで苦しんでいるかもしれない、ということを頭の片隅に置いておく
- 自分も完璧な上司にはなれないことを認識する
- 相手に期待し過ぎず、正当な評価してくれないと感じても「そういう人もいる」と受け流す
- 耐えがたいほどのストレスを感じる場合は転属願等、物理的に距離を置くことも検討に入れる
そして何より大切なことは、資格取得その他、現在あなたが取り組んでいることをやり遂げ、あなた自身の自己肯定感を高めることだと思います。
ということで、今回はここまで。