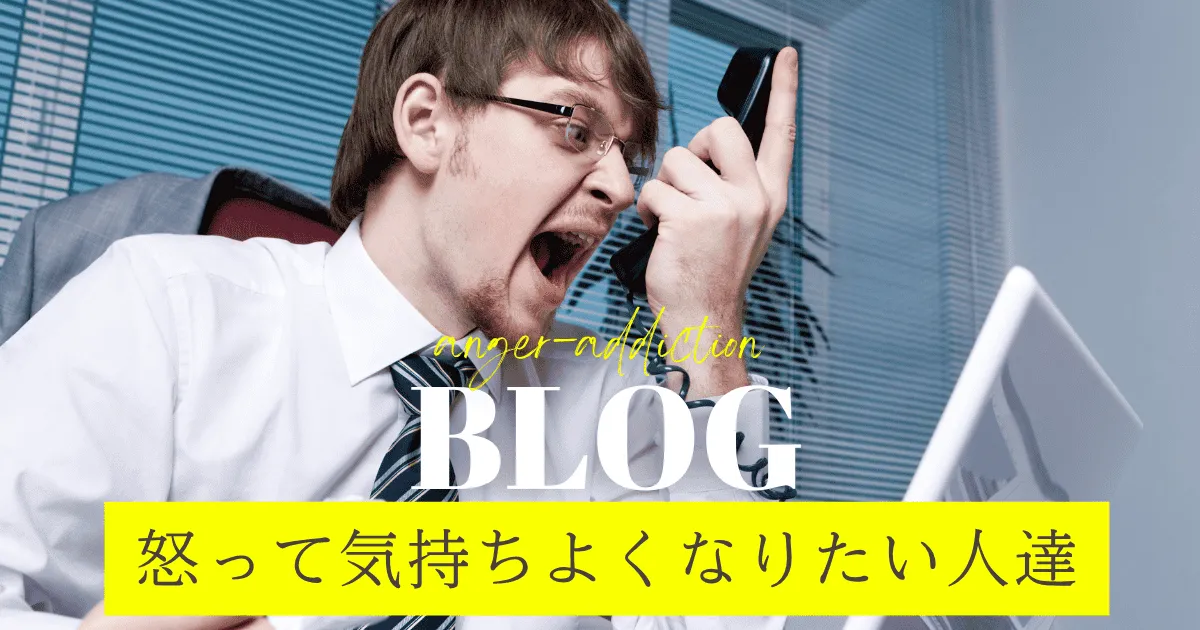※本ページにはアフィリエイト広告が含まれています。
こんにちは、柴山です。
よくある会話例:
上司:「どうしたんだ? ここ数か月間、営業成績がパッとしないじゃないか」
部下:「実はかくかくしかじかで…」
上司:「はぁ?何を言っているんだ。私の若い頃はもっと大変で…うんぬんかんぬん(延々と)」
こんな感じで
- 相談した側にとっては何の解決にもならず
- 相談された側だけが自慢話を語ることで気持ち良くなれる
…という無駄な時間は、職場だけでなく家庭や学校など、いたるところに溢れています。

自慢話を語り、優越感に浸る上司
いや、自分は部下や後輩に長々と自慢話をするような、そんなダサい真似はしていない!
そう思っている方でも別の形で優越感に浸り、部下のモチベーションを思いっきり低下させている可能性があります。
今回は、あなたが本来持っているはずのマネジメント能力、人格などの「上司力」を低下させる怪物、すなわち優越感についてまとめてみました。
優越感にも色々ある
優越感とは自分が他人よりも優れていると感じる感情のことで、自尊心や自信、自己肯定感などと関連しています。また、それは感情であると同時に一種の快楽でもあります。
まず確認しておきたいのは「優越感を得たい」と思うこと自体は悪いことではないということです。
良い優越感とは?
優越感は、人間が動物として生存し、子孫を残していく上で、非常に強力な生存本能に根ざした効果を持っていたと考えられます。
自分が属する集団の中で「有利なポジションを得たい」「賞賛されたい」と強く思うことは、食料確保や縄張り争いなどで、時には命懸けで頑張る動機になり得るからです。
現代社会においても「優越感を得たい」「周囲から認められたい(承認欲求)」という感情が、学業や仕事での頑張りにつながるのであるならば、それは本人にとっても社会にとっても有益に働く場合があります。
悪い優越感とは?
優越感を感じたいという気持ちが、他人を貶める言動につながるのであれば、害悪であるといえます。
つまり、優越感を得たいという気持ちが
- 自分を高める方向に働けば善
- 他人を下げる(貶める)方向に働けば悪
こう言えるのではないでしょうか?
(この記事ではこの考え方に沿って進めていきます)
悪の方の優越感が過剰になると、人間関係の悪化だけでなく、あなたは他人にとって耐えがたいほどのストレスの元凶になってしまうかもしれません。
職場にて、優越感(悪)に浸る行動パターン
ここでは主に上司が部下に対して取りがちな、悪の優越感に浸るための行動を分類してみました。
①自慢話
自慢話を語るのは、最もありがちな優越感を得るための行動です。
ただ単に自慢話をするだけであれば害は少ないと言えますが、自慢話から続いて
- 「お前は甘い」
- 「自分の方が大変だった」
といった「自慢話+相手を否定」の合体形態をとると、それを聞かされる人に対して強いストレスを与えます。
②否定/ダメ出し/過小評価
部下の仕事や意見に対してのダメ出しは、優越感に浸るための手段として使われることがあります。
- 意見や提案を頭ごなしに否定する
- 提出した資料などに対して、重要度が低い細部に至るまでダメ出し
- 良いところを全く評価しようとしない、または過小評価
これらも部下を成長させようという気持ちが無く、上司が優越感に浸るだけのために行われるのであれば、害悪以外の何者でもありません。
③非言語での否定
これは②の別パターンで、部下に対して
- ため息
- 舌打ち
- 机や物をたたく
などの非言語的な表現で、否定・ダメ出しを行い、自分が優越感に浸る一方で、部下の自信を失わせます。
④部下を指導しない/曖昧な指示
部下に対して優越感に浸りたいと思っている上司は、その反動として部下が自分よりも業績を上げることに対する潜在的な恐れがあります。
そのため、
- 部下の成長につながるような具体的な指導をしない
- すぐに結果につながるような具体的な指示をしない
なお「具体的な指示をしない」には、さらにいくつかのパターンに分かれます。
- 業務をいくつかのプロセスに分解して段階的に説明するなど、具体的な指示をするための能力不足
- 上手くいかなかった時に、部下のせいにできる余地を残したいなど責任回避
などです。
このような指導・指示の仕方だと部下の仕事が上手くいかないことが多いため、ここぞとばかりにダメ出しをすることで自分が優越感に浸ることができます。
曖昧な指示しかしない(できない)上司については、以下の記事もご覧ください。

⑤マイクロマネジメント
上司が部下の業務に対して過度に介入し、細部にわたって指示を出すスタイルをマイクロマネジメントと呼びます。
一見すると、④の「具体的な指導をしない」の逆で、良い事のようにも思えますが、以下のような違いが有ります。
部下を成長させるための具体的な指導/マイクロマネジメント の違い
| 種別 | ① 具体的な指導 | ② マイクロマネジメント |
| 目的・意図 | 部下の学習と成長支援。部下の能力向上と育成。 | 上司自身の不安解消や支配欲を満たすこと。ミス防止、責任回避。 |
| 行動様式 | ヒントや方向性を示す。次に活かせる知識やスキルを伝える | 過剰な監視と干渉。細かすぎる指示、頻繁な進捗確認。 |
| 焦点 | 「なぜそうするのか」、「次どうすればいいか」等、今後のための確認 | 「何をどうやったか」といった目先の作業の確認 |
| 部下への影響 | 自信と主体性の向上、スキルアップ、達成感。 | 意欲の低下、思考停止、指示待ち、ストレス、成長機会の喪失。 |
| 信頼関係 | 信頼に基づく建設的な関係構築 | 不信感の醸成、上司への依存、コミュニケーション不足。 |
| 最終目標 | 部下が自律的に成果を出せるようになること。 | 上司の指示通りに業務が完遂されること。 |
要するに、部下の成長よりも上司自身の支配欲(≒優越感)を満たすことが目的となっているとしたら、もはやマネジメントではありません。
⑥執拗な質問の繰り返し
部下の仕事に対して、「○○はどうなった?」「では、△△は?」「■■はどうなんだ?」と質問を繰り返し、応えられないことがあると、その途端に
「だめだろ!そんなんじゃ!」
…のようにダメ出しをするやり方です。
これも部下の見落とし防止のための質問であれば問題ありませんが、
部下が答えられないことを期待して、細かい質問をしつこく繰り返す
⇒答えられないと、ここぞとばかりに詰めて自分が優越感に浸る
これが目的になっているようでは、もはや指導とは言えないことは明らかです。
これはマイクロマネジメントの一形態とも言えますが、度が過ぎると部下に心理的な圧迫を与えることになりますので、パワーハラスメントに該当する可能性もあります。
「部下の成長」より「自分の優越感」を優先させているのが問題
そもそも上司、つまり管理職の人間が役職を与えられ、部下よりも高い給与をもらっているのは、
- チーム(部署)としての目標の設定および達成
- 指揮系統として機能する
- チーム代表として他のチームとの調整を行う
- チーム代表としてメンバー間での調整を行う
- チームメンバーのモチベーションを高め、成長を促す
こういった役割があるからです。
それに対して、自分が優越感に浸ることを目的として、部下のモチベーションを低下させるような行いをすることは、⑤に反しているのは明確です。さらにチームの目標達成そのものに悪影響を与える可能性も高いため、①の役割にも反しています。
人は誰しも無意識に優越感に浸るための行動を取ってしまうことはありますが、ちゃんとした「上司」たるにはそういった行動をなるべく排する必要があります。もちろん、わざとそのような行動を取るような人は上司として不適格です。
部下を預かる立場にある方は、自分が優越感に浸るための言動でチームのモチベーションを低下させていないか、時々振り返っておくべきでしょう。
部下を成長させたくない心理とは?
先に少し触れましたが、
- 自分が優越感に浸りたいがために、部下が業績を上げることを望まない
- 自分に自信が無い為に、部下が成長して自分を脅かすような存在になって欲しくない
こういう人たちは、私が見聞きしてきた範囲でも普通に(たくさん)います。
経営者の立場からすれば、管理職としての給料をちゃっかりと受け取っておきながら、その責任を果たそうとしない者には
ふざけんな!
と言いたいかと思いますが、残念ながらそれが現実です。
このため、そういう人をうっかり管理職にしてしまわないためには、単に営業成績が良かったから営業マネージャーに、といった安直な人事は避けなければなりません。部下の成長に配慮しない人に任せてしまうと、チーム全体の成績やモチベーションを下げる結果になります。
なお部下に成長して欲しくない心理については、下記の記事もご覧ください。

まとめ:ロクでもない上司にならないために
この記事は…、
「部下の成長を望まないとか、自分はそんなロクでもない上司にはなりたくない!」
という方のために書きました。
そういった方でも、うっかり部下のモチベーションを低下させるような言動をしてしまう可能性はあります。何故なら「優越感に浸りたい」というのは人の本能だからです。
この記事を読んだ方が優越感に浸るための行動パターンに自覚的になることで、そういった行動を取らないこと、および部下の成長を促進するような「上司力」の高い上司になっていただくことを切に願います。
ということで、今回はここまで。
今回記事の続編はこちらです。